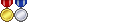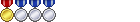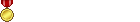ほら、昔のえらい人も言ってたじゃないですか。
「成功確率なんてのは単なる目安だ。足りない分は勇気で補え!」
と。
- Forum Top
- Japanese Forums
- ゲームシステム
- ユーザーインターフェース
- 乱数の仕様について
Thread: 乱数の仕様について
-
07-25-2014 12:12 PM #21(5)
-
07-25-2014 12:27 PM #22わざわざ実確率より下げて表示するよりも、そのまま表示してくれた方が親切だと思います。専門的なことがわからないユーザーとしては、ギャザラーで6回しか採集できないポイントで成功率が98%である場所で3回も失敗すれば、「ほんとに98%かよ?」って思うのは当然であるかと思います。
今の時期であれば降水確率がほぼ0%に近い5%で、傘も持たずに花火大会を見に行って土砂降りに遭いずぶ濡れになり裏切られたような感じです。
ギャザラーで例えますが、確率アップのスキルがそのポイントでしか使えないのであれば確率も 【全体で帳尻を合わせる】 数値ではなく、現在よりも少ない数値であってもそのポイントごとに適正に合わせた成功率にしたほうがいいと思います。
6回中98%で数回失敗するよりも60%台で失敗した方が不満は減るんじゃないでしょうか?(9)
-
07-25-2014 01:30 PM #23Player

- Join Date
- Sep 2013
- Posts
- 219
- Character
- Yukiko Snow'white
- World
- Atomos
- Main Class
- Conjurer Lv 90
スレ主さんのいいたい事は
ギャザーとかは、
連打すると一定のタイミング(リズム)になるので
そのリズムが、ランダムの同じ値を拾うんじゃないか?
っていうことなんじゃないですか?
テンポずらすと良いとかオカルトの部類だと思いますが。(8)
-
07-25-2014 02:14 PM #24Player

- Join Date
- Mar 2011
- Location
- リムサ・ロミンサ
- Posts
- 780
- Character
- Isvara Pranidhana
- World
- Aegis
- Main Class
- Miner Lv 100
最近では分解でも%が使われていますよね?!
これは体感ですが、分解の成功率は正確な感じがします。
あと、マテリア装着時の成功率も嗚呼こんなもんだなって感じますが、ギャザラーに関しては目を疑いたくなりますね。
なぜ96%の成功率で3回連続で失敗するのかと。。。(´・_・`)
ちなみに、確率の理論は充分承知していますので、サイコロがどうのとかはもう良いです。(笑)(0)
-
07-25-2014 07:32 PM #25Player

- Join Date
- Dec 2013
- Location
- Limsa Lominsa
- Posts
- 559
- Character
- Mayailurus Iriomotensis
- World
- Tonberry
- Main Class
- Machinist Lv 70
ギャザラー、特に採掘と園芸は実行回数がとても多いです。
そのため、極端に見える結果もまま見かけるかと思います。
で、極端っぽい結果は強く印象に残りやすいっていうのが答えとなり、簡単に言えば気のせいです。
また、乱数の仕様をよく知っている様なので知っているかもですが、再現性の有無が大きな要素となりますね。(5)
-
07-25-2014 09:36 PM #26
こんばんは。
何故かUIにポストされているので、担当外ですが 雑談として コメントします。
メインプログラマのK氏に確認した所、
XIVでは、有名な乱数アルゴリズムから3種を、用途によって使い分けているそうです。
当然、全てサーバ側で処理をしていますし、シード(乱数の種)は起動ごとに異なります。
なので、Ltzさんの疑問についてですが「そういう問題が起こる実装ではありませんよ」
というお答えになります。
たしかに、昔のゲームでは特定操作でパターン化できる実装や、
それを逆用した攻略が可能なタイトルはありましたが、
昨今のゲームではそういう実装方法は殆ど無いと思います。たぶん。
それでも、XIVに限らずゲーム中の確率(乱数)処理は、
昔から今に至るまで、プレイヤーに「疑惑の目」を向けられ続けています。
私の考えは 「いやー、殆どの場合は 単なる偶然 ですよ」 なのですが、
それだけでは納得行かないと思うので、ちょっと語ってみようと思います。
+ + +
これは、XIVに特定した話ではなく、プログラムの乱数が疑われやすいのは
どうしてなんだろう?というお話です。
※もちろん、本当にバグだったケースも少なくありませんが…
まずは、要点だけざっくりと。
a) XIVや昨今のゲームが使っている標準的な乱数プログラムは、実用上「正しい乱数列」を生成する。
b) 人が把握出来る範囲の回数では、「正しい乱数列」だからこそ偏りが生じる。
c) 私達の脳は、「偏り」を異常・特異点として検出する能力に長けているため「正しい乱数」を異常に感じる。
a~cを個別に補足説明します。
まずは a) の「乱数列」を出力するプログラムについて。
XIVに限らず 昨今のゲームで使われる乱数アルゴリズム(正しくは擬似乱数)は、
数学者やコンピュータサイエンスの凄い人が考案し、
様々な分野で検証され、実用されている鉄板のアルゴリズムを使っています。
一例として、メルセンヌ・ツイスタという乱数アルゴリズムの周期性の説明を抜粋します。
「周期が2^19937-1で、623次元超立方体の中に 均等に分布することが証明されています」
はい。全くわかりませんが、大丈夫です。
乱数アルゴリズムというのは、こういった純粋数学の成果によって成り立っている分野です。
少なくとも私達利用者は、生成される乱数列は正しく十分実用的だ、という事を前提にできれば十分です。
★乱数アルゴリズムと、ゲーム実装で生じた過去の問題事例を知る人は、
上記で触れていない事が気になると思います。一応、末尾に蛇足の説明を加えています。
次にb)の「正しい乱数列」について、です。
乱数には、一様乱数や正規乱数といった分布パターンの異なる種類がありますが、
試行回数が増えるほど、理想の状態に収束していきます。
逆に、試行回数(サンプリングの数)が少なければ、乱数列には偏りが生じます。
そして、私達人間が把握できる程度の、ゲーム中の試行回数程度では、
乱数には偏りが生じるのが「正常」なのです。
つまり「乱数に偏りがあるのは、おかしい」という前提が間違っているのです。
勿論、数百万回とか、数億回の試行の果てには、均一に無作為な分布に収束し、
偏りはなくなります。
これを、人間が「実際の出来事を観測」して体感するのは、ちょっと無理があります。
そのため、限られた試行回数で発生した偏りを目にするたびに、
「やっぱ、偏ってるって! 絶対に!」と声をあげてしまうわけですが、
「そうだね、偏ってるね。」としか言いようがありません。
最後に c)の、私達の「認識」の誤謬について。
私達人間は、様々なことを瞬間的に判断したり、直感したりできます。
脳みそが得意で、コンピュータが苦手といわれる分野ですね。
一方で、その能力には不得手な部分もあり、そこを突くと手品や詐欺に嵌めることができます。
この、脳が周囲の出来事を認識して判断する穴を突き、誤った判断や誤解をおこしやすい
パターンを「認知バイアス」と呼びます。
確率に生じる代表的な認知バイアスが、Gambler's fallacy (ギャンブラーの誤り)
と呼ばれるものです。
これは、
相互に関わりあうことのない出来事を、人が時間軸に沿って複数観察した場合に、
過去の出来事が 未来の出来事の結果に影響をおよぼす事を期待したり、
生じた結果に対して因果関係を理由に納得、または違和感を感じる錯覚です。
コインを投げて5回連続で表が出ようとも、6回めに表/裏のでる確率は
それぞれ変わらす50%です。
しかし、直感は「こんどこそ」と感情的な期待値の補正をかけてしまい、
結果が表なら「ありえない」と感じ、裏が出たら「やはりな!」と感じやすいものです。
これが認知バイアスです。
b)で述べた、おかしくない事なのにオカシイと直感してしまうのは、
確率が、脳が直感的に期待する因果関係とは、ぜーんぜん関係ない振る舞いするからです。
※と、断言形式で書いてますけど、所詮本の受け売りなのでご注意ください。
認知バイアスは、まるで人間の認識能力のバグみたいですが、
人が生き残る上で獲得した、緊急時に効率よく判断する仕組みなんだそうです。
この認知バイアスというのは厄介ですが非常に面白いので、
ご興味のある方にはこういった包括的な書籍もあるのでオススメします。
+ + +
以上、
私達がゲームで出会う確率が、なんかオカシイぞ!と思いがちなのはどーしてなのか考えてみた、でした。
おわり。
蛇足:乱数アルゴリズムの所で触れなかった事
乱数アルゴリズムの中でもコスト対効果が高く採用例の多い方法に、
線形合同法がありますが、このアルゴリズムは範囲の取り方で
結果に大きな偏りが生じるのは、実装者には良く知られた問題です。
事実、この関数の用い方をミスって、サンプル数が増えるほど
偏りが増していくゲームがありました。
なので「よく知られた一般的な手法だから!」いう事が、
正しさの証明になるわけではありません。
また、乱数列が正しく生成されても、アプリケーション実装が
その値をどのように用いるか次第で、最終的な結果に妙なパターンが生じる事も当然あります。
ですから、長々と述べた話は「XIVの各種確率計算の結果の正しさの証明」ではありません。
それはわかっています。ですから冒頭に述べた通りこのポストの後半は完全に雑談で、
「XIV中の確率は間違いないのか?」という問いに対する答えでは無い事をご了承ください。
(546)
-
07-25-2014 09:54 PM #27Player
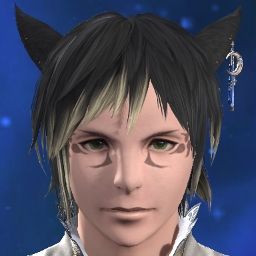
- Join Date
- Aug 2013
- Location
- ウルダハ
- Posts
- 363
- Character
- Ltz Zwei
- World
- Alexander
- Main Class
- Scholar Lv 72
UIはセクション外でしたか、すみません!orz
(コントローラによる操作から、システムを通って帰ってくるまでの過程の話だしインターフェースが一番近いかなーと思ったのです……申し訳ありません)
いやーやっぱ気のせいだよね、僕の思い込みだろうハハハッと思ってスレ立てたことを忘れてたところに、好奇心が刺激されまくりの文章、ありがとうございます。精読します。
偏りはそりゃあって当然なのですが、「どうもこれ連打してる時に限って……もしかしてBOT対策とかの一環として、短時間の入力だと効率が落ちるように仕組んでるのでは……」とM●R並みのトンデモ思考でpostして以来、
あー書くんじゃなかった確率がおかしいという話じゃないのにぃと悶々としてましたが救われた気分です。(13)PS4/PC 両環境でプレイ中。主にPS4。ゲームはゲーム機で派なのです。
-
07-25-2014 09:54 PM #28Player

- Join Date
- Mar 2011
- Location
- リムサ・ロミンサ
- Posts
- 863
- Character
- Minna Wilcke
- World
- Aegis
- Main Class
- Blacksmith Lv 59
皆川さんのポスト、勉強になるなぁ。
PLLでこういうお話聞きたいですね。(2時間枠に収まらないかもしれませんが)
認知バイアスのために、日々「ヨシダァァァァァァ!」と我々は叫ぶわけか・・・。(49)~暁の地平線に
勝利を刻み込みなさいっ!~
-
07-25-2014 09:56 PM #29
やっぱりちゃんと判りやすく判ってる人が話をすべきだし
表に出てきたほうがいいよね(17)
-
07-25-2014 09:59 PM
- Reason
- フォーラムに貢献しない内容のため、削除いたしました。
-
07-25-2014 10:00 PM #30Player

- Join Date
- Oct 2011
- Location
- グリダニア/双蛇党
- Posts
- 109
- Character
- Zilkain Braddock
- World
- Masamune
- Main Class
- Conjurer Lv 31
2/10と書いてあったら、8回失敗したら2回成功させろという話なのでは?
(12)
Quick Navigation
ユーザーインターフェース
Top
- Forums
- Japanese Forums
- ニュース
- テクニカルサポート
- 不具合報告
- プロデューサーレター
- ゲームシステム
- クラス&ジョブ
- ウェブサイト/アプリフィードバック
- 雑談
- この装備を武具投影したい!!
- あのジョブのUIレイアウトが知りたい!
- みんなとストラテジーボードを共有したい!
- ジェネラルディスカッション
- ワールド(Group JP)
- ワールド(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- 初心者用
- コミュニティイベント
- 開催中
- 終了
- 第8回14時間生放送
- 第68回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第65回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第64回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第60回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第56回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第53回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張!ひろしチャレンジ 応援プレゼント企画
- 第50回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第49回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- ハウジングコーディネートコンテスト
- 第44回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第43回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第42回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第41回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第40回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第39回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第38回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第37回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第35回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- ハウジングデコレーションコンテスト
- 第34回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第33回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LAS VEGAS (2016)
- 髙井浩の○○チャレンジ!応援企画
- 第31回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 紅蓮祭スクリーンショットコンテスト 2016
- 第30回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第28回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- サントラ発売記念!奏天のイシュガルドコンテスト
- 第27回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 星芒祭 4コマスクリーンショットコンテスト
- 第26回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第25回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- パンプキンクッキーコンテスト
- 髪型デザインコンテスト
- 第24回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第23回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第22回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エオルゼア百景 in 装備コーディネートコンテスト
- 第21回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 思い出スクリーンショットコンテスト
- フリーカンパニーPRキャンペーン
- 第20回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- FFXIVプロデューサーレターLIVE特別編
- ヴァレンティオンデーチョコレートコンテスト
- 闘会議2015 予想イベント
- 降神祭スクリーンショットコンテスト
- 星芒祭スクリーンショットコンテスト
- 第19回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第18回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LAS VEGAS
- 新生FFXIV キャプションコンテスト
- 紅蓮祭スクリーンショットコンテスト
- 第17回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 新生FFXIV 1周年記念PVコンテスト
- ミラプリ スクリーンショットコンテスト
- 第16回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第15回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第14回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エッグハントスクリーンショットコンテスト
- 出張プロデューサーレターLIVE
- 第13回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- プリンセスデースクリーンショットコンテスト
- 第12回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 降神祭スクリーンショットコンテスト
- 星芒祭スクリーンショットコンテスト
- ヴァレンティオンデースクリーンショットコンテスト
- フリーカンパニー紹介PVコンテスト
- 第11回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第10回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 守護天節スクリーンショットコンテスト
- 第9回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張プロデューサーレターLIVE in 幕張
- English Forums
- Information
- Technical Support
- Bug Reports
- Letters from the Producer
- Gameplay
- Classes & Jobs
- Feedback
- Community
- General Discussion
- Worlds(Group JP)
- Worlds(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- New Player Help
- Community Events
- Current Events
- Past Events
- Contests and Sweepstakes
- Fan Festival 2023 in London
- 10th Anniversary Mosaic Art Sweepstakes (NA/EU)
- Fan Festival 2023 in Las Vegas
- Ask Your Questions for the PAX East 2023 Q&A
- Crystalline Conflict Community Cup (North America)
- Letter from the Producer LIVE Part LXVIII
- Letter from the Producer LIVE Part LXV
- Letter from the Producer LIVE Part LXIV
- Letter from the Producer LIVE Part LX
- Everything’s on the Line! Screenshot Contest (NA)
- Ask Yusuke Mogi Your Questions for the PAX East 2020 Panel
- “A Star Light Party” Screenshot Contest (EU/PAL)
- Star Companion Screenshot Sweepstakes (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part LVI
- “This is All Saints’ Wake” Screenshot Contest (EU/PAL)
- A Glamourous Guise Screenshot Contest (NA)
- Memoirs of Adventure Creative Writing Contest (NA)
- Ask Yoshi-P and Banri Oda Your Questions for the gamescom 2019 Q&A
- Letter from the Producer LIVE Part LIII
- Cosplay Contest at gamescom 2019 (EU)
- Become the Darkness Screenshot Sweepstakes! (NA)
- From Light to Darkness Screenshot Contest (EU/PAL)
- Frights and Delights Comic Contest (EU/PAL)
- Cosplay Contest at Japan Expo 2019 (EU)
- Ogre Pumpkin Carve Off Contest: The REDUX (NA)
- My new Viera and Hrothgar" Twitter Screenshot Contest (NA/EU)
- ”Sea Breeze Celebration” Screenshot Contest (NA)
- An Egg-Squisite Season Screenshot Contest (EU/PAL)
- The Eorzean Interior Design Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XLIX
- Letter from the Producer LIVE Part L
- FLOWERS FOR ALL SCREENSHOT CONTEST
- The Eorzean Interior Design Contest (EU)
- Highlights of the Year Contest (EU)
- Fan Festival 2018 in Las Vegas (NA)
- Starlight Scenarios Comic Contest (NA)
- Fan Festival 2019 in Paris (EU)
- The "As Good As Gold" Screenshot Contest (NA)
- Glamour Extravaganza Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE: E3 2018 Edition
- Letter from the Producer LIVE Part XLIV
- Letter from the Producer LIVE Part XLIII
- The "Be My Valentione!" Creative Writing Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XLII
- Letter from the Producer LIVE Part XLI
- Holiday Greetings Contest (EU)
- Starlight Starbright Screenshot Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XL
- Ogre Pumpkin Carve Off Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIX
- Letter from the Producer LIVE Part XXXVIII
- PAX West 2017 (NA)
- Sightseeing Screenshot Contest! (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXVII
- And… Action! (NA)
- The Heavensdub Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXV
- House Party Screenshot Contest (EU)
- Bright-Eyed Superstars Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE in Frankfurt (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIV
- Starlight Celebration Haiku Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIII
- The “Eorzean Home Makeover (Extreme)” Contest (NA)
- Fan Festival 2017 (EU)
- Spooky Story Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE in Las Vegas (2016)
- The Rising Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXI
- "Do You Even /Pose?" Showdown! (NA)
- Fan Festival 2016 (NA)
- Dream Holiday Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE: E3 2016 Edition
- Heavensward Primal Haiku Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXX
- Letter from the Producer LIVE Part XXIX
- Letter from the Producer LIVE Part XXVIII
- Heavensward Music Contest (NA)
- Heavensward Music Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXVII
- Starlight Celebration Comic Strip Contest (NA)
- Starlight Celebration Comic Strip Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXVI
- Airship Components: Research and Development (NA)
- All Saints’ Wake Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXV
- Retainer Ad-Venture Contest (EU)
- Cartographers and Seekers Contest (NA)
- Hairstyle Design Contest
- Letter from the Producer LIVE Part XXIV
- Letter from the Producer LIVE Part XXIII
- Letter from the Producer LIVE Part XXII
- Letter from the Producer LIVE Part XXI
- Memories of Eorzea Screenshot Contest (NA)
- Memories of Eorzea Screenshot Contest (EU)
- Heavensward Free Company Recruitment Contest (NA)
- Heavensward Free Company Recruitment Contest (EU)
- A Realm Redubbed Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XX
- Letter from the Producer LIVE – Special Edition
- The Great Eorzean Cook-Off Contest (EU)
- Be My Valentione Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (EU)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (NA)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XIX
- Letter from the Producer LIVE Part XVIII
- Letter from the Producer LIVE in Las Vegas
- Grant a Wish Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XVII
- Moonfire Faire Screenshot Contest (NA)
- Moonfire Faire Screenshot Contest (EU)
- Fan Festival 2014 (NA)
- Fan Festival 2014 (EU)
- FFXIV: ARR One Year Anniversary Video Contest (NA)
- FFXIV: ARR One Year Anniversary Video Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XVI
- Eorzea IRL Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE: E3 Edition
- Letter from the Producer LIVE Part XV
- Letter from the Producer LIVE Part XIV
- Hatching-tide Screenshot Contest (NA)
- Hatching-tide Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XIII
- Little Ladies' Day Screenshot Contest (NA)
- Little Ladies' Day Screenshot Contest (EU)
- Valentione's Day Screenshot Contest (NA)
- Valentione's Day Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XII
- Heavensturn Screenshot Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (EU)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (NA)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (EU)
- FFXIV: ARR Free Company Recruitment Contest (NA)
- FFXIV: ARR Free Company Recruitment Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XI
- XIII Days – Your Fate is Sealed Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part X
- Doppelganger Screenshot Contest (NA)
- All Saints’ Wake Haiku Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part IX
- Ask Your Questions for the Mini Letter from the Producer LIVE at TGS!
- Sightseeing Screenshot Sweepstakes (NA/EU)
- Forums français
- Informations
- Assistance technique
- Rapports de problèmes
- La lettre du producteur
- Système de jeu
- Classes & Jobs
- Avis et retours sur les sites et l’appli
- Discussion
- Discussion générale
- Mondes (Japon)
- Mondes (Amérique du N./Europe/Océanie)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- Aide aux nouveaux joueurs
- Événements communautaires
- Evénements en cours
- Evénements passés
- Concours et tirages au sort
- Fan Festival 2023 de Londres
- Concours pour la mosaïque du 10e anniversaire
- « La lettre du producteur LIVE » : 68e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 65e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 64e émission
- Concours de captures d’écran d'exploration - Édition 2020
- « La lettre du producteur LIVE » : 60e émission
- Concours de captures d’écran - Une petite fête des étoiles entre amis
- « La lettre du producteur LIVE » : 56e émission
- Concours de captures d’écran – C’est ça la Veillée des Saints
- Mes questions à Yoshi-P et Banri Oda pour le Q&R de gamescom 2019 !
- « La lettre du producteur LIVE » : 53e émission
- Concours de cosplay à la gamescom 2019
- Concours de captures d’écran : De la Lumière aux Ténèbres
- Concours Pistolame à Japan Expo 2019 !
- Concours de Cosplay à Japan Expo 2019
- « Ma Viéra & mon Hrothgar » - Concours Twitter de capture d'écran
- Fabulœuf concours de captures d’écran
- « La lettre du producteur LIVE » : 50e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 49e émission
- Concours des meilleurs moments de l'année 2018
- Concours de BD’pouvante
- Concours de décoration d’intérieur
- Fan Festival 2019 à Paris
- Concours “Les dieux de la mode”
- « La lettre du producteur LIVE » : 44e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 43e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 42e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 41e émission
- Concours de cartes de vœux
- « La lettre du producteur LIVE » : 40e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 39e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 38e émission
- Concours de captures d’écran d’exploration
- « La lettre du producteur LIVE » : 37e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 35e émission
- Concours de captures d’écran spécial « House Party »
- Lettre du producteur LIVE à Francfort
- « La lettre du producteur LIVE » : 34e émission
- Concours de haïkus pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : 33e émission
- Concours d’histoires effrayantes
- Posez vos questions pour la lettre Live à Las Vegas (2016)
- Concours de captures d’écran pour la fête de la Commémoration
- « La lettre du producteur LIVE » : 31e émission
- Concours office de tourisme d’Éorzéa
- « La lettre du producteur LIVE » : 30e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 29e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 28e émission
- Concours de musique d’Heavensward
- « La lettre du producteur LIVE » : 27e émission
- Concours de comic strip pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : 26e émission
- Concours de captures d’écran pour la Veillée des saints
- « La lettre du producteur LIVE » : 25e émission
- Concours « Les aventures de mon servant »
- Concours de création de coupe de cheveux
- « La lettre du producteur LIVE » : 24e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 22e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 23e émission
- Concours de captures d’écran – Souvenirs d’Éorzéa
- Les compagnies libres recrutent pour Heavensward
- « La lettre du producteur LIVE » : 20e émission
- La lettre du producteur LIVE : émission spéciale
- Le grand concours culinaire d’Éorzéa
- Concours de captures d’écran pour la fête de la transition
- Concours de captures d’écran pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : dix-huitième émission
- Posez vos questions pour la lettre Live à Las Vegas
- Concours « Le jeu des souhaits »
- « La lettre du producteur LIVE » : 19e émission
- Fan Festival 2014
- Concours de captures d’écran pour les feux de la mort
- « La lettre du producteur LIVE » : dix-septième émission
- Concours vidéo pour le premier anniversaire
- « La lettre du producteur LIVE » : seizième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : quinzième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : quatorzième émission
- Concours de captures d’écran pour la chasse aux Prœufs
- « La lettre du producteur LIVE » : treizième émission
- Concours de captures d’écran pour la fête des demoiselles
- « La lettre du producteur LIVE » : douzième émission
- Concours de captures d’écran pour la fête de la transition
- Concours de captures d’écran pour la fête des étoiles
- Concours de captures d’écran pour la Valention
- Les compagnies libres recrutent
- « La lettre du producteur LIVE » : onzième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : dixième émission
- Concours Haiku d'Éorzéa - la Veillée des saints
- « La lettre du producteur LIVE » : neuvième émission
- Posez vos questions pour la lettre Live à Makuhari
- Deutsches Forum
- Ankündigungen
- Technischer Support
- Fehler melden
- Briefe des Produzenten
- Spielsystem
- Charakterklassen & Jobs
- Feedback
- Diskussionen
- Allgemeine Diskussionen
- Welten(Group JP)
- Welten(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- Für Einsteiger
- Community-Veranstaltungen
- Aktuelle Veranstaltungen
- Vergangene Veranstaltungen
- Wettbewerbe und Gewinnspiele
- Mosaik-Gewinnspiel zum 10. Jubiläum
- Fan Festival 2023 in London
- Der 68 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 65 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 64 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Reisetagebuch-Screenshot-Gewinnspiel
- Der 60. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sternenlichtertrupp-Screenshot-Wettbewerb
- Der 56. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Allerschutzheiligen Schauer-Spektakel-Screenshot-Wettbewerbs
- Eure Fragen an Naoki Yoshida und Banri Oda für die Q&A-Session auf der gamescom 2019
- Der 53. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Cosplay-Wettbewerb auf der gamescom 2019
- Vom Licht in die Dunkelheit Screenshot-Wettbewerb
- Cosplay-Wettbewerb auf der Japan Expo 2019
- „Viera & Hrothgar Makeover“ Twitter-Screenshot-Wettbewerb
- Wundereiersuche Screenshot-Wettbewerb
- Der 50. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 49. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Highlights des Jahres Wettbewerb
- Spuk und Schabernack Comic-Wettbewerb
- Inneneinrichtungs-Wettbewerb
- Fan Festival 2019 in Paris
- Extravaganza-Wettbewerb
- Der 44. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 43. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 42. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 41. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Wintergrüße-Wettbewerb
- Der 40. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 39. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 38. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sightseeing-Screenshot-Wettbewerb
- Der 37. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 35. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- House Party! Screenshot-Wettbewerb
- Brief des Produzenten LIVE in Frankfurt
- Der 34. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sternenlichtfest Haiku-Wettbewerb
- Der 33. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Gruselgeschichten-Wettbewerb
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Las Vegas (2016)
- Fest der Wiedergeburt Screenshot-Wettbewerb
- Der 31. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Traumurlaub-Wettbewerb
- Der 30. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 29. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 28. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Heavensward Musik-Wettbewerb
- Der 27. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Sternenlichtfest Comicstrip-Wettbwerb
- Der 26. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Allerschutzheiligen-Fest Screenshot-Wettbewerb
- Der 25. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Die Abenteuer des Tapferen Gehilfen–Wettbewerb
- Frisuren-Design-Wettbewerb
- Der 24. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 22. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 23. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Erinnerungen an Eorzea Screenshot-Wettbewerb
- Heavensward-Rekrutierungswettbewerb der freien Gesellschaften
- Der 20. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Brief des Produzenten – LIVE-Sondersendung!
- Großer, eorzäischer Kochwettbewerb
- Himmelswende Screenshot Wettbewerb
- Sternenlichtfest Screenshot-Wettbewerb
- Der 18. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Las Vegas
- Wünsche werden wahr- Wettbewerb
- Der 19. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Fan Festival 2014
- Feuermond-Reigen Screenshot-Wettbewerb
- Der 17. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Video-Wettbewerb zum einjährigen Jubiläum
- Der 16. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 15. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 14. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Wundereiersuche Screenshot-Wettbewerb
- Der 13. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Prinzessinnenfest Screenshot-Wettbewerb
- Valentiontag Screenshot Wettbewerb
- Der 12. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Himmelswende Screenshot Wettbewerb
- Sternenlichtfest Screenshot Wettbewerb
- Rekrutierungsvideo-Wettbewerb der Freien Gesellschaften
- Der 11. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 10. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Allerschutzheiligen-Haiku-Wettbewerb
- Der 9. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Makuhari!
- Version 1.0 Forum Archive
- Japanese Forums
- インフォメーション
- サポート
- アップデート
- ゲームシステム
- クラス&ジョブ
- ウェブサイトフィードバック
- 雑談
- 初心者用
- 写真館
- コミュニティイベント
- 開催中
- 終了
- ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア キャッチフレーズコンテスト
- 第8回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LA
- 第7回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第6回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 創作タマゴコンテスト
- 第5回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- マイ ベスト チョコボ
- ダラガブを探せ!
- エオルゼア メモリーズ
- 第4回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エオルゼア de 五・七・五
- 第3回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 残暑見舞いコンテスト
- Hidden Artifacts ~新生コンセプトアートクイズ~
- ガルーダトライアル
- 宿屋deつぶやき!イベント (JP)
- LSリクルートポスターコンテスト (JP)
- English Forums
- Information
- Support
- Updates
- Gameplay
- Classes & Jobs
- Feedback
- Community
- New Player Help
- In-Game Media
- Community Events
- Current Events
- Past Events
- Letter from the Producer LIVE Part VIII
- Letter from the Producer LIVE Part VII
- Letter from the Producer LIVE Part VI
- Eorzean Egg Decoration Contest
- Letter from the Producer LIVE Part V
- Eorzea Haiku Contest (EU)
- “Chocobos Rule the World” Contest!
- Memories of Eorzea Contest
- Letter from the Producer LIVE Part IV
- What if Dalamud Contest (EU)
- Tales from Eorzea (NA)
- Culinary Creation Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part III
- We Dub to Make it Ours (NA)
- These Grand Company Colors Don't Run!
- Hidden Artifacts
- Grant A Wish Contest (EU)
- Garuda—She's Like the Wind
- Culinary Creation Contest (NA)
- Valentione’s Dialogue Contest (EU)
- Valentione’s Day Love Letter Contest (NA)
- Forums français
- Informations
- Assistance sur le jeu
- Développement
- Système de jeu
- Classes & Jobs
- Avis et retours
- Discussion
- Aide aux nouveaux joueurs
- Galerie multimédia & articles
- Evénements organisés par l'équipe communautaire
- Evénements en cours
- Evénements passés
- « La lettre du producteur LIVE » : huitième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : septième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : sixième émission
- Concours : « Décoration d’Œufs Éorzéens »
- « La lettre du producteur LIVE » : cinquième émission
- Concours « Haïkus d’Eorzéa »
- Concours « Les Chocobos à la Conquête du Monde » !
- Concours « Souvenirs d’Eorzéa »
- « La lettre du producteur LIVE » : quatrième émission
- Concours : « Et si Dalamud était... »
- Concours de création culinaire
- « La lettre du producteur LIVE » : troisième émission
- Soutenons les grandes compagnies !
- Questions pour un Eorzéen
- Concours du jeu des souhaits
- L’épreuve de Garuda
- Concours de dialogue de la Valention
- Deutsches Forum
- Ankündigungen
- Support
- Update
- Spielsystem
- Charakterklassen & Jobs
- Feedback
- Diskussionen
- Für Einsteiger
- Medien
- Community-Veranstaltungen
- Aktuelle Veranstaltungen
- Vergangene Veranstaltungen
- Der 8. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 7. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 6. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Eorzäischer Ei-Dekorations-Wettbewerb
- Der 5. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Eorzea-Haiku-Wettbewerb
- Chocobos, die Herrscher der Welt
- Erinnerungen an Eorzea
- Der 4. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Was, wenn Dalamud … wäre?
- Kulinarische Kreationen
- Der 3. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Farben, die nicht die Segel streichen!
- Verborgene ARTefakte
- Wünsche werden wahr-Wettbewerb
- Garuda – Grausame Herrin der Stürme
- Valentione Dialog-Wettbewerb
- Japanese Forums
«
Previous Thread
|
Next Thread
»


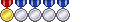

 Reply With Quote
Reply With Quote