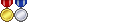- Forum Top
- Japanese Forums
- クラス&ジョブ
- その他バトルシステム
- 冒険を売りにするのなら、RPGらしい冒険が実感できるゲームシステムにして欲しい
-
03-24-2018 10:28 PM #1201(1)
-
03-24-2018 10:29 PM #1202すでに意見されていると思いますが、冒険を売りにしているなら、とタイトルにありますが、売りにしているのはテーマパークなので、前提にある齟齬の修正に掛かっていませんか。
始めから絶叫マシンで揃えるのも、絵本のようなアトラクションで揃える特色はあると思いますが、アトラクションのひとつとして置くならその体裁を持っていないと、施設の一部を工事中にして作り替える必要が出ます。
レイドゲーというメインストリートを体験した上でどこへ行こうというものでなければ、1プレイヤーに提供できる体験の総量が減り価値が低下します。
例えばねこへびさんが中途半端だと感じるエウレカで現状多くのプレイヤーが熱心に遊んでいるのも、メインコンテンツがあればこそです。
そして、エウレカもこのようなふんわりした感想では一切のフィードバックとして実を結びません。
これは本当に困ります。
こういう意見しか出せないのも、現状のコンテンツにそれほど興味がなく、全部破壊してすっぴんを作れと考えているからですよね。
報酬系を考えないのもそうです。
如何に冒険感が出る要素で提案されていても、全部破壊とそんなことは支持出来ないというのが議論の前提で見え隠れするのであれば無駄になるので、明らかにさせるか、一考してください。
テーマパークだという売り文句自体も実現出来ているとは思えません
エウレカスレ見てても、楽しめている人も多いけど、面白くないという意見もやっぱり多いし、僕の周りでもエウレカに対する評価はかなり低かったです
それから、僕は「実装前にエウレカの予想」をちゃんと事細かに書いてますよね、このスレ内で。
その後に「エウレカは予想通りだった」と書いているんだから、僕のエウレカに対するフィードバックは「中途半端で遊ぶ気になれない物でした」という程度のふわっとしたフィードバックではない事は分かるハズです
なにより「実装前にエウレカの予想を書く事」を僕に催促したのはakiraraさん自身ですから、きちんとスレの内容を把握した上で投稿して下さい<(_ _)>(1)
-
03-24-2018 10:30 PM #1203
途中で「ブレスト」という単語がでてきて、自分は良くこの言葉の意味を知らなかったので調べてみたんですが
このブレーンストーミングってのは、相手の意見や案を「否定しない事」などを前提とする事で「より多くのアイデアを引き出す議論方式」の様ですね
#1163あたりからここに至るまでに、「このスレは今からブレーンストーミングである」という共通認識の元でいくつかの案や意見が実際に出てきていますから
そこから今までに出て来た具体案の全てに対しては、僕は否定も質問もしません
ですが、僕がこのスレで出した案は「ブレーンストーミング前提で出した物」ではないので、#1163以降からも当然、反論や質問などがバンバン出てます
このままでは「僕のすっぴん案」はずっと「ブレーンストーミングの範囲外」で語られ、#1163以降に出てくる具体案は全てが「反論などから保護された状態」になってしまいます
これでは平等な議論は出来ませんので、「ブレーンストーミング方式前提としての提案」はここで終了とさせてください
フォーラムでは「案を出したら反論や質問などが飛んでくるのは当たり前」であり、案自体に対する反論などは何ら禁止事項ではありませんから
この先このスレで案を出すのであれば、他のスレ同様にここでも「反論が来ること」を認識した上で投稿を行ってください
※ #1163以降からこの投稿に至るまでの全ての具体案に対しては「反論も問題提起も禁止」という事で構いません<(_ _)>(1)
-
03-24-2018 11:23 PM #1204Player

- Join Date
- Aug 2013
- Location
- ぐりだにゃー
- Posts
- 160
- Character
- Zarje Sarje
- World
- Ridill
- Main Class
- Red Mage Lv 90
すっぴん案は別スレですればいいと思います。議論することが目的ではないです。平等であるかどうかは問題ではありません(そもそも勝ち負けじゃない)
スレ立て時当初の文言はそれだけ大事だと考えます。そこに興味があってもすっぴん案に対しては「そうじゃないんだよなぁ」としか思えません
「今よりも少しだけ良くするにはどうしたらいいかな」という積み重ねでしか多数の賛同は得られないと私は考えています。劇的改善理想論など望みません。(23)
-
03-24-2018 11:37 PM #1205ですのでそれは逆でしょ?と何回も出させていただいてます。
既存のルールをもってMMOを運営が解釈し冒険を形作ってるのが現状のFF14であって
それで納得し遊んでるのが現ユーザーですよね。ルール無用で作った案が果たしてFF14と呼べるのかは
多くの人が疑問視してるのではないでしょうか?
その答えが「別のゲーム探したら?」って返答につながってるのだと思いますが?
前にも書きましたが別段、今のルールに不満も何もありませんから、すっぴんの案なんて無用の長物なんですよ。
というより追加なんて勘弁してほしい位のものなんですよね。
貴方が既存のルールにを疑問視して否定してるのと同様の話をあなたが構築してるルールに対して抱いてるわけです。
えぇ、スレッドで示してるのは分かってるのですが・・・・
なんで前に提示した内容を無視して新規案を構築するのでしょうか?別段、新規ジョブにする必要も何もないのに
軋轢を自ら生み出して否定されたら「前に出したよ。」って独立コンテンツの共有要素としてJobもどきを入れる
ってのと現状のフィールドで使える新規ジョブでは全く話が違いますけど?(16)
-
03-24-2018 11:42 PM #1206
ブレストとして発言された内容とNekohebiさんの主張とでは、そもそもの質が違うのですよ。
ブレストは出されたアイデア単体を「完成形」としてはおらず、そこから連想や発展などをさせてより良いアイデアへと収束させていく目的でやるものです。
対して、
あなたの主張する内容は最初からすでにそれを「正」とした前提で語られており、他のアイデアや意見を一切受け付けません。
それでいて尚且つ、肝心な部分の詳細があなた以外の人間に共有されず、問答を繰り返すごとに新たな後付けが足されていくので第三者をどんどん置いてけぼりにしています。
Nekohebiさんの論調は0か100かの二極でしか語られず、「100ではない以上0である」と言い、「100はすなわち自分である」と、終始このような態度で結論されているように見受けられます。(29)
-
03-24-2018 11:45 PM #1207ユーザーが踏み込むべき場所とそうでない場所は確実に存在します。
ユーザーが踏み込める場所で面白いや否やって話をするのは良いと思いますよ。
「自分が面白くないからFF14のルールは間違ってるんだ」なんて話はゲームを面白くする以前の話。
主観で根本を否定する事のどこに面白さにつながる要素があるんでしょ?
現状に面白さを感じてる人にしてみりゃ余計なお世話でしかない。
相手が明らかに間違ってると感じるなら間違ってるだろって言って当然。
せめて現状のルールでみんなが楽しめる方向で考えてみないって意見が
間違えてるとは思わんけどね。(25)
-
03-25-2018 12:08 AM #1208
どこに面白さがあるのかなんてそれこそ人それぞれの話でしょう。
否定の先に面白さに繋がる要素が生まれないなんてのは貴方が決めつけてるだけです。
既存のルールでは無理だから新しいルールを考えてみるという判断の下で作られたスレッドで、
「私は今のルールに満足してる」っていちいち言うのってそれこそ余計なお世話じゃないですか?
今に満足してるならスレッドを閉じればいいだけでは。
そういう意見がフォーラムの片隅の専用スレッドに書かれているのも許せないですか。
そこにどのような新規案が書かれていても、それを参考にするかどうかは運営が決める事であり、
フォーラムに現状と全然違うアイデアを出してはいけないなんて規則はないはずです。
もしそれを現状のルールで楽しめる方向で考えたいなら、その案を出すのは貴方自身であるべきでは。
※追記
・別のゲームしたら?→それは別のゲームへの誘導であり規約違反です。
・ルールを変える内容だから既存ユーザーがいなくなるので反対→影響がないよう既存部分とは別コンテンツとして提案されています。
・現状で満足だから反対する→「現状」は絶対普遍ではなく、本当にハードやシステム根幹の制約に根ざすGCD等以外は変更可能だし、
ある仕様について現状が本当に満足されているのかアンケートをとって結果を見たわけでもない以上、それは完全に個人の感想です。
その現状について「どう面白くて維持する価値があるか」を提示して話さないなら、何の根拠もだしていないという事です。
「現状」だけを根拠に自分は「現状と違うから」新規案に反対するけれど、 相手はそれに対して反論してはいけないというのは、
自分だけ言葉の責任をもたなくてもいい場を作るための、都合のいいダブルスタンダードにすぎません。(3)Last edited by Roundabout; 03-25-2018 at 05:05 PM. Reason: 何度も同じ事を言い続けてる人のために追記
-
03-25-2018 12:46 AM #1209
特殊マテリアを用いたコンテンツ案
スレッドのテーマにそって一つ具体案を提示します。
バトル
・ソロの1コンボで死ぬ大量の雑魚をサクサク狩っていき、そのドロップを集めるハクスラ/無双型
この形式を目指す理由
FF14はスキル入力周期が早く、バトルでは回避以外の部分にほとんど戦術が存在しない。
空島でもエウレカでも、その状態で雑魚1匹をただ硬くしても一匹あたりの作業量が増えテンポが悪くなっただけだった。
しかし、そのようなバトル中に選択を考える時間がない、戦術を駆使するバトルにできない、雑魚の行動を増やせない場合でも、
ハクスラ形式であれば一匹あたりの戦闘をごく短く設定できるため各敵の行動は1~2パターンでよく、
スキル入力ペースの速さがそのまま殲滅速度と時間あたりの成果数(敵の討伐数)に結びつくので爽快感、達成感を得やすい。
(ex. diablo3/三国無双等)
パーティ
・パーティを組むことを必須にしない。
・ソロは経験値にソロ補正ボーナスを得て、他の人と同じ敵を殴った場合はHP2割ほど削れば経験値が全額入る。
・パーティだとボーナスはないが倒した敵の基本経験値は全員に入る。
・パーティでもソロでもドロップは個別判定で入手しロット制はない。
・雑魚を倒すことでノートリアスモンスターが出現し、それを倒した際はソロ/パーティ関係なく参加者全員が報酬を得る。
この形式を目指す理由
これまでのFATEでは同じ場所にソロとパーティがいた場合、ソロで経験値を得る事が難しく、
またパーティ用に調整されたコンテンツにおいてはソロ参加はバランス上不可能だった。
しかし最初からソロ前提で敵の強さを設計し、パーティの場合は単純に人数分多くの敵を狩れるようにし
経験値に関してはソロ/パーティ間や他パーティ同士の頭割りをしないという事にすれば、
ソロだろうがパーティだろうが同じ場所でプレイした方が効率がいいという状況になる。
このようにすることでFATEパーティのように気軽に参加しやすい環境を作る。
ロットやNM報酬の仕様は、争いなくみんなが得するようにするため。
1プレイの時間
・1プレイ20分程度で1LVあがり、そこで一区切りつくような経験値設定にする。
・そのタイミングで拠点に帰還し、装備の修理/強化、食品(バフ効果)や薬品(ポーション/エーテル/万能薬等)の補充を行うデザインにする。
この形式を目指す理由
FF14はバトルの操作頻度の問題で、一回の連続プレイ時間を長くするほどプレイ負担が大きく大変になる。
(FATEパーティでも連続で続けすぎれば疲れるが、区切りがないのでペースのコントロールができない。)
そこにMOの1プレイ(10~20分)と同様のスパンで一旦の休憩を入れるようなデザインにすることでゲームプレイにメリハリをつける。
拠点
拠点にたき火のようなものを用意し、その付近で休む事で経験値バフを得られる。(2分休むと15分ぶんのバフがつく等)
修理、食品、薬品については通常より影響を重くし、戦闘時必ず使用する前提とする。
これらは拠点で購入できるが、コンテンツ内で入手したアイテムを使って自作もできる。
製作した場合、販売品よりやや高性能な装備、食品やポーションを作れる。
それらはコンテンツ外に持ち出し不可だがコンテンツ内でコンテンツ内貨幣で他人とトレード販売可能にする。
この形式を目指す理由
たき火は人が集まって留まるポイントを作るためのものであり、プレイのペーシングに使用する。
装備の修理は現在の仕様ではギルをシステム回収するための手段になっているがリソース管理の対象として使用できる。
食品や薬品は雰囲気もの=意味のないものではなく、コンディションの持続やリソース回復の手段として価値を持たせ、
雰囲気=その世界のリアリティを感じさせる要素として機能させる。
装備品製作については雑魚との戦闘以外でコンテンツクリアを可能にする方法を用意すること、
拠点(街)に人が集まってコミュニケーションをとる構造を作るため。これらはいずれもFF14でスポイルされている要素。
マップ
マップはエウレカ同様の1マップ。外周部から中央部に向けて次第に標高が高くなり、
地形的には拠点-平原-敵の砦-森林-山岳(渓谷)--洞窟-山岳頂上の城(ボスの居場所)と明確にエリアを形成しレベルデザインを行う。
それらの各エリアでいくつかのイベントを見るとボス戦になり、それをクリアする事でキーとなるアイテムを入手できる。
それによってさらなる奥地に進めるようにする。城のボスを倒すと一応のクリア。
この形式を目指す理由
地形の順番はテンプレート的なもの。大事なのは戦いの舞台がストーリーに連動して広がり、次第に遠く、危険になっていく点。
そのストーリーが「冒険」であるほど、フィールドは舞台装置としても意味を持つようになる。
この例では仮にお話を有名な「英雄の旅路(ジョーゼフ・キャンベルの論)」の形式で作るとする。(詳説は省略)
お話が、1.日常→2.冒険への誘い→3.冒険の拒否→4.賢者との出会い→5.戸口の通過→6.試練・仲間・敵→
7.最も危険な場所への接近→8.最大の試練→9.報酬→10.クライマックス→11.帰還→12.大団円という流れ(一部省略)で進むとき、
1は街、2-4は平原、5は砦、6.は森林、山岳、7は洞窟、8-10は城、11以降は街という風に場所が遷移する事で、
物語をその舞台であるマップによっても表現する事ができ、それにより「冒険」に対する没入感をえやすくなる。
FF11のストーリーは簡潔だが評価が高い。初期ディスクのストーリーである闇王討伐の前提クエストやミッションの場所の推移をみると、
上記のような形式を忠実になぞっているのが見て取れる。「冒険」のためにはこのような構造が必要。
雑魚の挙動および地形ギミック
平原や森林、山岳、洞窟では生態系のイメージ考えて敵を配置し、時間帯や天候で敵の居場所が変わるようにする。
砦やボスの城では見張りの巡回、高所からの射撃、詰め所から敵が出てくる等、配置自体をギミックにする。
建物内ではマップを使った落とし穴やトラップ等を設置する。遮蔽物や天候(霧など)により隠れたり感知を切れるようにする。
マップ構造は高低差を用意し、見晴らしのよい高台や、曲がり角、安全地帯となる隠し部屋を用意するなど、
敵味方の視界の概念を活かすものにする。敵はボスクラスやエリートモンスター以外は常で団体(グループ)で行動。
この形式を目指す理由
プレイ単位をソロにすることで、このようなギミック失敗時の連帯責任に気負わなくてよくなり幅が広がる。
FF14のIDの構造などを見るとプレイヤーの視界がどうなるかほとんど考慮されておらず、建物の立体構造をいかす事もされていない。
地図上ではなく画面で遠くのユニークな目標地点を発見し、後にそこにたどりつけたり、
視界が開けた場所で先の空間にいる敵の配置を見て進むルートを変えたりということがない。
ダンジョンの中に安全な休憩ポイントというものがないためメリハリがなくなってもいる。
そういったものを用意することで冒険している感覚が生まれる。
コンテンツ内アイテム
・コンテンツ内貨幣(装備やアイテムを購入するために使用する)
・コンテンツ内専用装備(確定マテリア穴のみを3-5つもつ)
・消耗品および装備作成用の素材
進行度(一定レベル毎)にあわせて装備を集め、一通り揃ったら次に進む形式。
※これらはコンテンツ内でリソースを完結させるために必要。
入手経路はランダムポップの宝箱、モンスタードロップ。装備はクラフトも可能。
コンテンツ専用マテリア
スキルビルド、万能性、属性武器特性等を表現するためマテリアシステムを利用する。
このコンテンツ内では装備につけるマテリアとして以下のものを用意する。
マテリア種類
・モンスター固有スキルマテリア
それをドロップするモンスターが使う特徴的なスキルが封じられており、装備に装着する事でスキル使用が可能になる。
そのスキル専用のホットバー(マウントや変身時のバーと同じようなもの)を用意する。
NMからはレアなマテリアを入手できる。変身効果などもあり。
・武器属性マテリア
武器に装着する事で「属性攻撃」「打/斬撃効果付与」「追加Dot効果」「一定確率で状態異常付与」等を行えるようになる。
(属性攻撃は追加の属性エフェクトが発生する)
・ステータス向上マテリア
各ステータスを大幅に向上させ、元のジョブのスキルの効果を高める
・特殊効果マテリア
経験値アップ、ドロップ率アップ、移動速度アップ等、あるいはギャザクラ補助、解錠スキルといった補助的効果
マテリア詳細
・マテリアは強力で最終的にキャラ+装備のステータスと同等以上の補正効果を持つ。
・自由に着脱可能。コンテンツ内でトレード可能。
・マテリアにより自分のジョブのロールを無視したスキルの取得が可能となる。
・武器の属性等は相性のよい特定属性の敵にダメージ追加効果のみでマイナス影響はない。
・各装備にマテリアを特定の組み合わせで装着する事でセット効果が発動し、ステータス追加効果を得ることができる。
合成について
・合成は2~5個を材料に1つ作れる。
・同じマテリアを集めて合成すると上位マテリアとなり固有スキル等の効果を強化する事ができる。
・レア固有マテリアも他マテリアを特定の組み合わせで消費することで合成可能とする。組み合わせにはルールを設ける。
・マテリア合成の触媒アイテムを用意する。合成時に触媒を使用する事で結果をよくしたり、別効果マテリアを合成できる。
この形式を目指す理由
FF14は雑魚モンスターを狩る際、「なぜそのモンスターを狩らなければいけないのか」の理由付けがとても薄いし、
ボスを倒してもこれといって感慨がない。貨幣と経験値だけを目的すると雑魚の種類を用意する意味からないので、
モンスター毎にマテリアを用意する事でその意味と価値をもたせる。
合成やセット効果は今自分がやろうとしているスタイルに合わせて最適なものを自分で考えてカスタマイズするゲーム性の実現のため。
以上のようなものを考えました。
ある程度既存システムを流用しつつ、スレ主さんが求める要素も入っているのではないかなと思います。
マテリアは既存システム内では可能性が潰えてしまっていますので上手く応用してほしいです。(4)Last edited by Roundabout; 03-25-2018 at 05:22 PM.
-
03-25-2018 12:49 AM #1210Time to winコンテンツとしては酷評されているということは、そもそもTime to winコンテンツとして作られていないことの証ではないでしょうか。エウレカがT2Wコンテンツと呼べる物だろうが、そうでなかろうが
エウレカには「時間を費やして育てたり蓄積したりする事で有利になっていくゲーム性」が実際にあるわけで、これが成功するかどうかは僕が#1107で書いた要素が重要である事は変わりません
ちなみにですが、エウレカスレを読んでみて下さい
エウレカをT2W的コンテンツと捉えた上でジャッジしている人が沢山いる事が分かると思います
中には
「エウレカアネモス編、フィールド狩りのTime To Winコンテンツであると事前に予告されていたこともあり、あまり期待を感じずに待っていた側でした。」
という発言もみられますから、開発陣側からも事前に「エウレカはT2Wのコンテンツ」って言う趣旨の発言があったのかもしれないです
そもそも本当にTime to winだと言われたところで、FF14全体が定期的にリセットを受ける作りなのを知っていれば、そのうたい文句に「Time to win風」以上の意味がないことはすぐわかることと思います。
実態としてもそうですし、「時間を費やして育てたり蓄積したりする事で有利になっていくゲーム性」など絶対に実装しえないことはもとから明らかです。
そのようなゲーム性はいまなお存在していないように思います。(6)
Quick Navigation
その他バトルシステム
Top
- Forums
- Japanese Forums
- ニュース
- テクニカルサポート
- 不具合報告
- プロデューサーレター
- ゲームシステム
- クラス&ジョブ
- ウェブサイト/アプリフィードバック
- 雑談
- この装備を武具投影したい!!
- あのジョブのUIレイアウトが知りたい!
- みんなとストラテジーボードを共有したい!
- ジェネラルディスカッション
- ワールド(Group JP)
- ワールド(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- 初心者用
- コミュニティイベント
- 開催中
- 終了
- 第8回14時間生放送
- 第68回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第65回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第64回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第60回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第56回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第53回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張!ひろしチャレンジ 応援プレゼント企画
- 第50回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第49回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- ハウジングコーディネートコンテスト
- 第44回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第43回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第42回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第41回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第40回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第39回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第38回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第37回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第35回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- ハウジングデコレーションコンテスト
- 第34回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第33回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LAS VEGAS (2016)
- 髙井浩の○○チャレンジ!応援企画
- 第31回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 紅蓮祭スクリーンショットコンテスト 2016
- 第30回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第28回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- サントラ発売記念!奏天のイシュガルドコンテスト
- 第27回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 星芒祭 4コマスクリーンショットコンテスト
- 第26回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第25回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- パンプキンクッキーコンテスト
- 髪型デザインコンテスト
- 第24回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第23回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第22回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エオルゼア百景 in 装備コーディネートコンテスト
- 第21回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 思い出スクリーンショットコンテスト
- フリーカンパニーPRキャンペーン
- 第20回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- FFXIVプロデューサーレターLIVE特別編
- ヴァレンティオンデーチョコレートコンテスト
- 闘会議2015 予想イベント
- 降神祭スクリーンショットコンテスト
- 星芒祭スクリーンショットコンテスト
- 第19回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第18回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LAS VEGAS
- 新生FFXIV キャプションコンテスト
- 紅蓮祭スクリーンショットコンテスト
- 第17回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 新生FFXIV 1周年記念PVコンテスト
- ミラプリ スクリーンショットコンテスト
- 第16回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第15回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第14回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エッグハントスクリーンショットコンテスト
- 出張プロデューサーレターLIVE
- 第13回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- プリンセスデースクリーンショットコンテスト
- 第12回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 降神祭スクリーンショットコンテスト
- 星芒祭スクリーンショットコンテスト
- ヴァレンティオンデースクリーンショットコンテスト
- フリーカンパニー紹介PVコンテスト
- 第11回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第10回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 守護天節スクリーンショットコンテスト
- 第9回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張プロデューサーレターLIVE in 幕張
- English Forums
- Information
- Technical Support
- Bug Reports
- Letters from the Producer
- Gameplay
- Classes & Jobs
- Feedback
- Community
- General Discussion
- Worlds(Group JP)
- Worlds(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- New Player Help
- Community Events
- Current Events
- Past Events
- Contests and Sweepstakes
- Fan Festival 2023 in London
- 10th Anniversary Mosaic Art Sweepstakes (NA/EU)
- Fan Festival 2023 in Las Vegas
- Ask Your Questions for the PAX East 2023 Q&A
- Crystalline Conflict Community Cup (North America)
- Letter from the Producer LIVE Part LXVIII
- Letter from the Producer LIVE Part LXV
- Letter from the Producer LIVE Part LXIV
- Letter from the Producer LIVE Part LX
- Everything’s on the Line! Screenshot Contest (NA)
- Ask Yusuke Mogi Your Questions for the PAX East 2020 Panel
- “A Star Light Party” Screenshot Contest (EU/PAL)
- Star Companion Screenshot Sweepstakes (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part LVI
- “This is All Saints’ Wake” Screenshot Contest (EU/PAL)
- A Glamourous Guise Screenshot Contest (NA)
- Memoirs of Adventure Creative Writing Contest (NA)
- Ask Yoshi-P and Banri Oda Your Questions for the gamescom 2019 Q&A
- Letter from the Producer LIVE Part LIII
- Cosplay Contest at gamescom 2019 (EU)
- Become the Darkness Screenshot Sweepstakes! (NA)
- From Light to Darkness Screenshot Contest (EU/PAL)
- Frights and Delights Comic Contest (EU/PAL)
- Cosplay Contest at Japan Expo 2019 (EU)
- Ogre Pumpkin Carve Off Contest: The REDUX (NA)
- My new Viera and Hrothgar" Twitter Screenshot Contest (NA/EU)
- ”Sea Breeze Celebration” Screenshot Contest (NA)
- An Egg-Squisite Season Screenshot Contest (EU/PAL)
- The Eorzean Interior Design Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XLIX
- Letter from the Producer LIVE Part L
- FLOWERS FOR ALL SCREENSHOT CONTEST
- The Eorzean Interior Design Contest (EU)
- Highlights of the Year Contest (EU)
- Fan Festival 2018 in Las Vegas (NA)
- Starlight Scenarios Comic Contest (NA)
- Fan Festival 2019 in Paris (EU)
- The "As Good As Gold" Screenshot Contest (NA)
- Glamour Extravaganza Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE: E3 2018 Edition
- Letter from the Producer LIVE Part XLIV
- Letter from the Producer LIVE Part XLIII
- The "Be My Valentione!" Creative Writing Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XLII
- Letter from the Producer LIVE Part XLI
- Holiday Greetings Contest (EU)
- Starlight Starbright Screenshot Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XL
- Ogre Pumpkin Carve Off Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIX
- Letter from the Producer LIVE Part XXXVIII
- PAX West 2017 (NA)
- Sightseeing Screenshot Contest! (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXVII
- And… Action! (NA)
- The Heavensdub Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXV
- House Party Screenshot Contest (EU)
- Bright-Eyed Superstars Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE in Frankfurt (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIV
- Starlight Celebration Haiku Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIII
- The “Eorzean Home Makeover (Extreme)” Contest (NA)
- Fan Festival 2017 (EU)
- Spooky Story Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE in Las Vegas (2016)
- The Rising Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXI
- "Do You Even /Pose?" Showdown! (NA)
- Fan Festival 2016 (NA)
- Dream Holiday Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE: E3 2016 Edition
- Heavensward Primal Haiku Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXX
- Letter from the Producer LIVE Part XXIX
- Letter from the Producer LIVE Part XXVIII
- Heavensward Music Contest (NA)
- Heavensward Music Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXVII
- Starlight Celebration Comic Strip Contest (NA)
- Starlight Celebration Comic Strip Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXVI
- Airship Components: Research and Development (NA)
- All Saints’ Wake Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXV
- Retainer Ad-Venture Contest (EU)
- Cartographers and Seekers Contest (NA)
- Hairstyle Design Contest
- Letter from the Producer LIVE Part XXIV
- Letter from the Producer LIVE Part XXIII
- Letter from the Producer LIVE Part XXII
- Letter from the Producer LIVE Part XXI
- Memories of Eorzea Screenshot Contest (NA)
- Memories of Eorzea Screenshot Contest (EU)
- Heavensward Free Company Recruitment Contest (NA)
- Heavensward Free Company Recruitment Contest (EU)
- A Realm Redubbed Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XX
- Letter from the Producer LIVE – Special Edition
- The Great Eorzean Cook-Off Contest (EU)
- Be My Valentione Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (EU)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (NA)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XIX
- Letter from the Producer LIVE Part XVIII
- Letter from the Producer LIVE in Las Vegas
- Grant a Wish Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XVII
- Moonfire Faire Screenshot Contest (NA)
- Moonfire Faire Screenshot Contest (EU)
- Fan Festival 2014 (NA)
- Fan Festival 2014 (EU)
- FFXIV: ARR One Year Anniversary Video Contest (NA)
- FFXIV: ARR One Year Anniversary Video Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XVI
- Eorzea IRL Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE: E3 Edition
- Letter from the Producer LIVE Part XV
- Letter from the Producer LIVE Part XIV
- Hatching-tide Screenshot Contest (NA)
- Hatching-tide Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XIII
- Little Ladies' Day Screenshot Contest (NA)
- Little Ladies' Day Screenshot Contest (EU)
- Valentione's Day Screenshot Contest (NA)
- Valentione's Day Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XII
- Heavensturn Screenshot Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (EU)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (NA)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (EU)
- FFXIV: ARR Free Company Recruitment Contest (NA)
- FFXIV: ARR Free Company Recruitment Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XI
- XIII Days – Your Fate is Sealed Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part X
- Doppelganger Screenshot Contest (NA)
- All Saints’ Wake Haiku Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part IX
- Ask Your Questions for the Mini Letter from the Producer LIVE at TGS!
- Sightseeing Screenshot Sweepstakes (NA/EU)
- Forums français
- Informations
- Assistance technique
- Rapports de problèmes
- La lettre du producteur
- Système de jeu
- Classes & Jobs
- Avis et retours sur les sites et l’appli
- Discussion
- Discussion générale
- Mondes (Japon)
- Mondes (Amérique du N./Europe/Océanie)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- Aide aux nouveaux joueurs
- Événements communautaires
- Evénements en cours
- Evénements passés
- Concours et tirages au sort
- Fan Festival 2023 de Londres
- Concours pour la mosaïque du 10e anniversaire
- « La lettre du producteur LIVE » : 68e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 65e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 64e émission
- Concours de captures d’écran d'exploration - Édition 2020
- « La lettre du producteur LIVE » : 60e émission
- Concours de captures d’écran - Une petite fête des étoiles entre amis
- « La lettre du producteur LIVE » : 56e émission
- Concours de captures d’écran – C’est ça la Veillée des Saints
- Mes questions à Yoshi-P et Banri Oda pour le Q&R de gamescom 2019 !
- « La lettre du producteur LIVE » : 53e émission
- Concours de cosplay à la gamescom 2019
- Concours de captures d’écran : De la Lumière aux Ténèbres
- Concours Pistolame à Japan Expo 2019 !
- Concours de Cosplay à Japan Expo 2019
- « Ma Viéra & mon Hrothgar » - Concours Twitter de capture d'écran
- Fabulœuf concours de captures d’écran
- « La lettre du producteur LIVE » : 50e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 49e émission
- Concours des meilleurs moments de l'année 2018
- Concours de BD’pouvante
- Concours de décoration d’intérieur
- Fan Festival 2019 à Paris
- Concours “Les dieux de la mode”
- « La lettre du producteur LIVE » : 44e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 43e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 42e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 41e émission
- Concours de cartes de vœux
- « La lettre du producteur LIVE » : 40e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 39e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 38e émission
- Concours de captures d’écran d’exploration
- « La lettre du producteur LIVE » : 37e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 35e émission
- Concours de captures d’écran spécial « House Party »
- Lettre du producteur LIVE à Francfort
- « La lettre du producteur LIVE » : 34e émission
- Concours de haïkus pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : 33e émission
- Concours d’histoires effrayantes
- Posez vos questions pour la lettre Live à Las Vegas (2016)
- Concours de captures d’écran pour la fête de la Commémoration
- « La lettre du producteur LIVE » : 31e émission
- Concours office de tourisme d’Éorzéa
- « La lettre du producteur LIVE » : 30e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 29e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 28e émission
- Concours de musique d’Heavensward
- « La lettre du producteur LIVE » : 27e émission
- Concours de comic strip pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : 26e émission
- Concours de captures d’écran pour la Veillée des saints
- « La lettre du producteur LIVE » : 25e émission
- Concours « Les aventures de mon servant »
- Concours de création de coupe de cheveux
- « La lettre du producteur LIVE » : 24e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 22e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 23e émission
- Concours de captures d’écran – Souvenirs d’Éorzéa
- Les compagnies libres recrutent pour Heavensward
- « La lettre du producteur LIVE » : 20e émission
- La lettre du producteur LIVE : émission spéciale
- Le grand concours culinaire d’Éorzéa
- Concours de captures d’écran pour la fête de la transition
- Concours de captures d’écran pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : dix-huitième émission
- Posez vos questions pour la lettre Live à Las Vegas
- Concours « Le jeu des souhaits »
- « La lettre du producteur LIVE » : 19e émission
- Fan Festival 2014
- Concours de captures d’écran pour les feux de la mort
- « La lettre du producteur LIVE » : dix-septième émission
- Concours vidéo pour le premier anniversaire
- « La lettre du producteur LIVE » : seizième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : quinzième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : quatorzième émission
- Concours de captures d’écran pour la chasse aux Prœufs
- « La lettre du producteur LIVE » : treizième émission
- Concours de captures d’écran pour la fête des demoiselles
- « La lettre du producteur LIVE » : douzième émission
- Concours de captures d’écran pour la fête de la transition
- Concours de captures d’écran pour la fête des étoiles
- Concours de captures d’écran pour la Valention
- Les compagnies libres recrutent
- « La lettre du producteur LIVE » : onzième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : dixième émission
- Concours Haiku d'Éorzéa - la Veillée des saints
- « La lettre du producteur LIVE » : neuvième émission
- Posez vos questions pour la lettre Live à Makuhari
- Deutsches Forum
- Ankündigungen
- Technischer Support
- Fehler melden
- Briefe des Produzenten
- Spielsystem
- Charakterklassen & Jobs
- Feedback
- Diskussionen
- Allgemeine Diskussionen
- Welten(Group JP)
- Welten(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- Für Einsteiger
- Community-Veranstaltungen
- Aktuelle Veranstaltungen
- Vergangene Veranstaltungen
- Wettbewerbe und Gewinnspiele
- Mosaik-Gewinnspiel zum 10. Jubiläum
- Fan Festival 2023 in London
- Der 68 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 65 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 64 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Reisetagebuch-Screenshot-Gewinnspiel
- Der 60. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sternenlichtertrupp-Screenshot-Wettbewerb
- Der 56. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Allerschutzheiligen Schauer-Spektakel-Screenshot-Wettbewerbs
- Eure Fragen an Naoki Yoshida und Banri Oda für die Q&A-Session auf der gamescom 2019
- Der 53. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Cosplay-Wettbewerb auf der gamescom 2019
- Vom Licht in die Dunkelheit Screenshot-Wettbewerb
- Cosplay-Wettbewerb auf der Japan Expo 2019
- „Viera & Hrothgar Makeover“ Twitter-Screenshot-Wettbewerb
- Wundereiersuche Screenshot-Wettbewerb
- Der 50. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 49. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Highlights des Jahres Wettbewerb
- Spuk und Schabernack Comic-Wettbewerb
- Inneneinrichtungs-Wettbewerb
- Fan Festival 2019 in Paris
- Extravaganza-Wettbewerb
- Der 44. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 43. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 42. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 41. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Wintergrüße-Wettbewerb
- Der 40. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 39. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 38. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sightseeing-Screenshot-Wettbewerb
- Der 37. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 35. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- House Party! Screenshot-Wettbewerb
- Brief des Produzenten LIVE in Frankfurt
- Der 34. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sternenlichtfest Haiku-Wettbewerb
- Der 33. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Gruselgeschichten-Wettbewerb
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Las Vegas (2016)
- Fest der Wiedergeburt Screenshot-Wettbewerb
- Der 31. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Traumurlaub-Wettbewerb
- Der 30. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 29. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 28. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Heavensward Musik-Wettbewerb
- Der 27. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Sternenlichtfest Comicstrip-Wettbwerb
- Der 26. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Allerschutzheiligen-Fest Screenshot-Wettbewerb
- Der 25. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Die Abenteuer des Tapferen Gehilfen–Wettbewerb
- Frisuren-Design-Wettbewerb
- Der 24. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 22. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 23. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Erinnerungen an Eorzea Screenshot-Wettbewerb
- Heavensward-Rekrutierungswettbewerb der freien Gesellschaften
- Der 20. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Brief des Produzenten – LIVE-Sondersendung!
- Großer, eorzäischer Kochwettbewerb
- Himmelswende Screenshot Wettbewerb
- Sternenlichtfest Screenshot-Wettbewerb
- Der 18. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Las Vegas
- Wünsche werden wahr- Wettbewerb
- Der 19. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Fan Festival 2014
- Feuermond-Reigen Screenshot-Wettbewerb
- Der 17. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Video-Wettbewerb zum einjährigen Jubiläum
- Der 16. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 15. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 14. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Wundereiersuche Screenshot-Wettbewerb
- Der 13. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Prinzessinnenfest Screenshot-Wettbewerb
- Valentiontag Screenshot Wettbewerb
- Der 12. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Himmelswende Screenshot Wettbewerb
- Sternenlichtfest Screenshot Wettbewerb
- Rekrutierungsvideo-Wettbewerb der Freien Gesellschaften
- Der 11. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 10. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Allerschutzheiligen-Haiku-Wettbewerb
- Der 9. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Makuhari!
- Version 1.0 Forum Archive
- Japanese Forums
- インフォメーション
- サポート
- アップデート
- ゲームシステム
- クラス&ジョブ
- ウェブサイトフィードバック
- 雑談
- 初心者用
- 写真館
- コミュニティイベント
- 開催中
- 終了
- ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア キャッチフレーズコンテスト
- 第8回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LA
- 第7回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第6回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 創作タマゴコンテスト
- 第5回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- マイ ベスト チョコボ
- ダラガブを探せ!
- エオルゼア メモリーズ
- 第4回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エオルゼア de 五・七・五
- 第3回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 残暑見舞いコンテスト
- Hidden Artifacts ~新生コンセプトアートクイズ~
- ガルーダトライアル
- 宿屋deつぶやき!イベント (JP)
- LSリクルートポスターコンテスト (JP)
- English Forums
- Information
- Support
- Updates
- Gameplay
- Classes & Jobs
- Feedback
- Community
- New Player Help
- In-Game Media
- Community Events
- Current Events
- Past Events
- Letter from the Producer LIVE Part VIII
- Letter from the Producer LIVE Part VII
- Letter from the Producer LIVE Part VI
- Eorzean Egg Decoration Contest
- Letter from the Producer LIVE Part V
- Eorzea Haiku Contest (EU)
- “Chocobos Rule the World” Contest!
- Memories of Eorzea Contest
- Letter from the Producer LIVE Part IV
- What if Dalamud Contest (EU)
- Tales from Eorzea (NA)
- Culinary Creation Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part III
- We Dub to Make it Ours (NA)
- These Grand Company Colors Don't Run!
- Hidden Artifacts
- Grant A Wish Contest (EU)
- Garuda—She's Like the Wind
- Culinary Creation Contest (NA)
- Valentione’s Dialogue Contest (EU)
- Valentione’s Day Love Letter Contest (NA)
- Forums français
- Informations
- Assistance sur le jeu
- Développement
- Système de jeu
- Classes & Jobs
- Avis et retours
- Discussion
- Aide aux nouveaux joueurs
- Galerie multimédia & articles
- Evénements organisés par l'équipe communautaire
- Evénements en cours
- Evénements passés
- « La lettre du producteur LIVE » : huitième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : septième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : sixième émission
- Concours : « Décoration d’Œufs Éorzéens »
- « La lettre du producteur LIVE » : cinquième émission
- Concours « Haïkus d’Eorzéa »
- Concours « Les Chocobos à la Conquête du Monde » !
- Concours « Souvenirs d’Eorzéa »
- « La lettre du producteur LIVE » : quatrième émission
- Concours : « Et si Dalamud était... »
- Concours de création culinaire
- « La lettre du producteur LIVE » : troisième émission
- Soutenons les grandes compagnies !
- Questions pour un Eorzéen
- Concours du jeu des souhaits
- L’épreuve de Garuda
- Concours de dialogue de la Valention
- Deutsches Forum
- Ankündigungen
- Support
- Update
- Spielsystem
- Charakterklassen & Jobs
- Feedback
- Diskussionen
- Für Einsteiger
- Medien
- Community-Veranstaltungen
- Aktuelle Veranstaltungen
- Vergangene Veranstaltungen
- Der 8. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 7. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 6. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Eorzäischer Ei-Dekorations-Wettbewerb
- Der 5. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Eorzea-Haiku-Wettbewerb
- Chocobos, die Herrscher der Welt
- Erinnerungen an Eorzea
- Der 4. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Was, wenn Dalamud … wäre?
- Kulinarische Kreationen
- Der 3. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Farben, die nicht die Segel streichen!
- Verborgene ARTefakte
- Wünsche werden wahr-Wettbewerb
- Garuda – Grausame Herrin der Stürme
- Valentione Dialog-Wettbewerb
- Japanese Forums
«
Previous Thread
|
Next Thread
»






 Reply With Quote
Reply With Quote