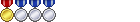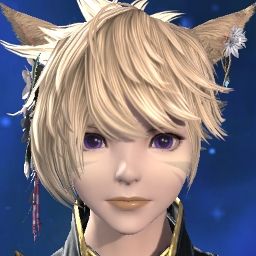- Forum Top
- Japanese Forums
- クラス&ジョブ
- DPS
- 竜騎士改善の具体案
Thread: 竜騎士改善の具体案
-
07-06-2017 01:43 PM #1721Player

- Join Date
- Jul 2015
- Posts
- 148
- Character
- Huracan Junraqan
- World
- Alexander
- Main Class
- Dragoon Lv 88
(22)
-
07-06-2017 01:52 PM #1722
あれ、シナジーのジョブ間比較の流れでしたよね?
合わせ想定でPTDPSが向上するのはリタニーに限った話ではないという単なる補足です
フェルッカさん個人に対する揚げ足取りの意図はないですよ
リタニーの最大効果を想定するなら同様のスキルを持つ赤忍モのシナジー込みDPSも高まる筈なので
リタニーを竜騎士に対するシワ寄せの根拠にするのはちょっと変かな? とは思いましたけどね
こちらにも補足ですが、これらの計算はリタニーや騙しの合わせを想定していない点に加えて
木人DPS基準である事にも注意してください
実戦(極2種)では侍より竜のほうがDPSを落としやすいので少しだけ差が開きます(1.5%程度)(9)世界がララフェルで満たされますように
-
07-06-2017 02:34 PM #1723
何を意識してるのかは知りませんが、すみませんが私はあなたにレスしていませんし
あなたはそのつもりであっても私はリタニーとシナジーの話題が出てるので竜スレですので例にもリタニーを上げて前述のとおり発言しただけです
きちんとリタニーに限らずと断りもちゃんと書いているのにいきなり引用で指摘されたら補足の意図であっても?と思うのは当然だと思います
リタニーに限らずの下に書いてますのでリタニーだけの皺寄せと言っているわけではありません
ちょっと返答が長くなります
まず4.0以降の竜スレ全般の流れをしっかりと読んで竜を触ってるなりして知っていれば……
はっきりいえばこのスレの大半の竜の方は同じ思いだと思います
3.Xにおいて個人DPSでは竜>忍、シナジーでは忍>竜という関係だった(TA詩機構成等特別な状態では逆転してたかもしれませんが)のは
沢山の方々が何度も述べて下さっています
個人DPSもしっかり出せるし、シナジーでも貢献できるバランスの取れた良ジョブだったのです
(その影で個人DPS()なモが劣る形にはなってモ竜間のバランスは壊れてはいましたが)
4.0で個人DPSの火力の爽快感をシナジー職()という形にあてはめることの理由で下げられ
一方忍は個人火力は保持どころか何故か上げられているわけです
そういった竜スレで散々いろんな人が述べてるのと全く同じ竜だけが割り食ったという発言への同意です
「ねー、そうだよねー」という発言です
ですのではしょられてて伝わりにくいと感じられたことは申し訳ないですが繰り返しますが別にあなた宛のレスではありませんし
私に言っているのは他の人の全く同じ発言にも全て突っ込んでることなんですよね
(または等価としてちゃんと全てに突っ込んでいただきたい)
私もあなたに向けて発言していたわけではないので返信は不要がお互い幸せだと思います(6)Last edited by Felucca_Trammel; 07-07-2017 at 12:20 PM.
-
07-06-2017 03:23 PM #1724
-
07-06-2017 04:04 PM #1725
-
07-06-2017 06:17 PM #1726
紅の竜血中の「竜爪竜牙」及び「竜尾大車輪」を「アラ・モーン」等ニーズヘッグが使ってた技にするくらいのファンサービスは有っても良かったと思います!
召喚士のデスフレアを初お披露目した時は凄く盛り上がりましたよね?
前パッチの強敵が使ってきた技を今度は自分が使えるようになるのは凄く燃えますし、よりモチベーションが高まります。
今の状態では紅の竜血中に「竜爪竜牙」及び「竜尾大車輪」を撃つメリットがあまりにも乏しい為、ご検討のほどよろしくお願い致します!(59)
-
07-06-2017 07:12 PM #1727
その①
こんな竜騎士もありかな~という妄想
意味不明だったらゴメンナサイ
ドラゴンアイのスタック上限を3つにする
ドゥームスパイクを62レベルでソニックスラストに更新
蒼の竜血を70レベルで紅の竜血に更新
ゲイルスコグルを70レベルでナーストレンドに更新
()内はスキル更新前のスキル名や数字
・ドラゴンサイト リキャスト180s
自身に「竜の右目を付与」し、対象のモンスターに「竜の左目を付与」する。
「竜の左目」が付与されたモンスターを自分以外のパーティメンバーがウェポンスキルで攻撃時
20%の確率でスパインダイブが使用可能になる
竜の右目効果:自身の与ダメージを10%上昇させる
竜の左目効果:対象のモンスターの被ダメージを3%上昇させる
効果時間20秒 効果の距離制限無し
使用時に「線」がエフェクトで表示されるのではなく、自身と対象の頭上に「竜の目」のようなエフェクトを表示する
スパインダイブがプロックすると自身の頭上にある目が鼓動する。
・紅の竜血(蒼の竜血)
紅の竜血使用不可80sというデバフを自身に付与する
紅の竜血使用不可中はスキルが蒼の竜血に変更される
蒼の竜血は自身に紅の竜血が付与されていない時に使用可能
ドラゴンアイを3つスタックする(蒼の竜血で使用した場合はスタックは増えない)
ミラージュダイブを使用後ドラゴンアイのスタックを1つ追加する
ジャンプ、スパインダイブ、ドラゴンダイブ、ミラージュダイブの威力を25%(20%)上昇させる
※効果に制限時間は無し、70Lvでの蒼の竜血は死亡時の応急処置だと思ってください。
・ナーストレンド(蒼の竜血時はゲイルスコグル) リキャスト1s
発動毎にドラゴンアイを1つ消費する
威力300(250)前方直線範囲攻撃
・ミラージュダイブ リキャスト1s
威力180
・ジャンプ リキャスト25s
スキル使用時70%の確率でリキャストタイムが初期化される
威力200(8)
-
07-06-2017 07:12 PM #1728
その②
・ランスマスタリー
桜華狂咲または、フルスラスト使用後「竜牙竜爪」と「竜尾大車輪」が使用可能になる
※状況に合わせて自身でどちらか1つを選択する仕様
例:ヘヴィスラスト→インパルスドライヴ→ディセムボウル→桜華狂咲→竜牙竜爪or竜尾大車輪→トゥルースラスト・・・
・ディセムボウル
コンボボーナス:次に使用するアビリティの威力が5%上昇する
効果時間30秒
突耐性5%ダウンを削除し、レンジDPSのダメージを5%増やす。
・桜華狂咲
継続ダメージ威力40
効果時間24秒
あまり慣れていないプレイヤー↓
開幕からナーストレンドをガンガン打てるため、爽快感がある・・・かもしれない
とりあえず打てるスキルを使うことによりある程度のダメージを出せる
やりこんでいるプレイヤー↓
リキャスト初期化によるジャンプ、ミラージュダイブの硬直を考慮しタイミングを自分で考えて上手く使うほどダメージが伸びる
ナーストレンドを1s毎にすぐに使うか、タイミングを考えて使うかでダメージに差が出る。
ディセム効果の使い方次第でもDPSが変わる。
現在のスキル回しでもノーミスで回せばかみあって上手く回りますが、少しずれるとかなり差がでるので
リキャストの時間を自分なりに合わせやすくしてみました。
方向指定が楽になり竜血の維持も無くなるので、手数がかなり増えますが小さい積み重ね次第で忍者、モンクに並べるイメージです。
IDでも竜血を維持するという考え方が無くなるので今より気楽に活躍できるかもしれません
ちなみに数字に関してですが暫定で考えた値です。長文失礼しました(9)
-
07-06-2017 07:40 PM #1729
あのー竜騎士同士で言い争いとかやめてー。
ただでさえこんな状況なのに仲間割れはよくないよー。
まぁこんな状況だから発言に敏感なのは分かるけど。
名指しは最低な行為だから名前は言わないけど話の流れがいまいち分かってない人、あるいは自分にKYなところがあるなぁって思う人は発言を控えて頂けると幸いです。
あと、「竜騎士弱いって言ったら私達〇〇はどうなるの?」みたいな場違いな発言する人は自分のメインジョブのスレでやってください。
竜騎士も今大変な時期で構ってられないんで。(47)
-
07-06-2017 07:53 PM #1730
初投稿失礼します。
オープンベータからずっと竜騎士をメインにプレイしてきました。
大型拡張で14の熱が、ジョブのアンバランスにより冷えないためにも投稿しようと思い立ちました。
個人的に気になったところとしてはプレイフィールです。
多数の方向指定とGCD間のアビリティの使用ギミックへの対応の中で、ジャンプという硬直するアビリティを30sec毎に使用するのは大きなストレスで、
竜騎士だけ1つギミックが多いと思うくらいです。
紅の竜血になるべく早くなりたいのにギミックの対応でジャンプの使用を控える間と方向指定を取りに行く時間が硬直により移動時間の制限で楽しくない方向にストレスに感じます。
方向指定が多いので自由に移動できるよう硬直を撤廃し、直感的に操作して楽しいプレイフィールにしてもらいたいです。
突耐性低下による偏重構成でのシナジーでDPS上限低く見積もるならば、DPS下限を上げてDPS出しやすい方向に設計できないでしょうか?(48)
Quick Navigation
DPS
Top
- Forums
- Japanese Forums
- ニュース
- テクニカルサポート
- 不具合報告
- プロデューサーレター
- ゲームシステム
- クラス&ジョブ
- ウェブサイト/アプリフィードバック
- 雑談
- この装備を武具投影したい!!
- あのジョブのUIレイアウトが知りたい!
- ジェネラルディスカッション
- ワールド(Group JP)
- ワールド(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- 初心者用
- コミュニティイベント
- 開催中
- 終了
- 第8回14時間生放送
- 第68回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第65回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第64回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第60回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第56回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第53回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張!ひろしチャレンジ 応援プレゼント企画
- 第50回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第49回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- ハウジングコーディネートコンテスト
- 第44回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第43回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第42回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第41回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第40回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第39回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第38回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第37回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第35回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- ハウジングデコレーションコンテスト
- 第34回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第33回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LAS VEGAS (2016)
- 髙井浩の○○チャレンジ!応援企画
- 第31回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 紅蓮祭スクリーンショットコンテスト 2016
- 第30回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第28回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- サントラ発売記念!奏天のイシュガルドコンテスト
- 第27回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 星芒祭 4コマスクリーンショットコンテスト
- 第26回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第25回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- パンプキンクッキーコンテスト
- 髪型デザインコンテスト
- 第24回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第23回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第22回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エオルゼア百景 in 装備コーディネートコンテスト
- 第21回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 思い出スクリーンショットコンテスト
- フリーカンパニーPRキャンペーン
- 第20回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- FFXIVプロデューサーレターLIVE特別編
- ヴァレンティオンデーチョコレートコンテスト
- 闘会議2015 予想イベント
- 降神祭スクリーンショットコンテスト
- 星芒祭スクリーンショットコンテスト
- 第19回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第18回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LAS VEGAS
- 新生FFXIV キャプションコンテスト
- 紅蓮祭スクリーンショットコンテスト
- 第17回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 新生FFXIV 1周年記念PVコンテスト
- ミラプリ スクリーンショットコンテスト
- 第16回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第15回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第14回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エッグハントスクリーンショットコンテスト
- 出張プロデューサーレターLIVE
- 第13回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- プリンセスデースクリーンショットコンテスト
- 第12回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 降神祭スクリーンショットコンテスト
- 星芒祭スクリーンショットコンテスト
- ヴァレンティオンデースクリーンショットコンテスト
- フリーカンパニー紹介PVコンテスト
- 第11回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第10回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 守護天節スクリーンショットコンテスト
- 第9回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張プロデューサーレターLIVE in 幕張
- English Forums
- Information
- Technical Support
- Bug Reports
- Letters from the Producer
- Gameplay
- Classes & Jobs
- Feedback
- Community
- General Discussion
- Worlds(Group JP)
- Worlds(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- New Player Help
- Community Events
- Current Events
- Past Events
- Contests and Sweepstakes
- Fan Festival 2023 in London
- 10th Anniversary Mosaic Art Sweepstakes (NA/EU)
- Fan Festival 2023 in Las Vegas
- Ask Your Questions for the PAX East 2023 Q&A
- Crystalline Conflict Community Cup (North America)
- Letter from the Producer LIVE Part LXVIII
- Letter from the Producer LIVE Part LXV
- Letter from the Producer LIVE Part LXIV
- Letter from the Producer LIVE Part LX
- Everything’s on the Line! Screenshot Contest (NA)
- Ask Yusuke Mogi Your Questions for the PAX East 2020 Panel
- “A Star Light Party” Screenshot Contest (EU/PAL)
- Star Companion Screenshot Sweepstakes (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part LVI
- “This is All Saints’ Wake” Screenshot Contest (EU/PAL)
- A Glamourous Guise Screenshot Contest (NA)
- Memoirs of Adventure Creative Writing Contest (NA)
- Ask Yoshi-P and Banri Oda Your Questions for the gamescom 2019 Q&A
- Letter from the Producer LIVE Part LIII
- Cosplay Contest at gamescom 2019 (EU)
- Become the Darkness Screenshot Sweepstakes! (NA)
- From Light to Darkness Screenshot Contest (EU/PAL)
- Frights and Delights Comic Contest (EU/PAL)
- Cosplay Contest at Japan Expo 2019 (EU)
- Ogre Pumpkin Carve Off Contest: The REDUX (NA)
- My new Viera and Hrothgar" Twitter Screenshot Contest (NA/EU)
- ”Sea Breeze Celebration” Screenshot Contest (NA)
- An Egg-Squisite Season Screenshot Contest (EU/PAL)
- The Eorzean Interior Design Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XLIX
- Letter from the Producer LIVE Part L
- FLOWERS FOR ALL SCREENSHOT CONTEST
- The Eorzean Interior Design Contest (EU)
- Highlights of the Year Contest (EU)
- Fan Festival 2018 in Las Vegas (NA)
- Starlight Scenarios Comic Contest (NA)
- Fan Festival 2019 in Paris (EU)
- The "As Good As Gold" Screenshot Contest (NA)
- Glamour Extravaganza Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE: E3 2018 Edition
- Letter from the Producer LIVE Part XLIV
- Letter from the Producer LIVE Part XLIII
- The "Be My Valentione!" Creative Writing Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XLII
- Letter from the Producer LIVE Part XLI
- Holiday Greetings Contest (EU)
- Starlight Starbright Screenshot Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XL
- Ogre Pumpkin Carve Off Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIX
- Letter from the Producer LIVE Part XXXVIII
- PAX West 2017 (NA)
- Sightseeing Screenshot Contest! (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXVII
- And… Action! (NA)
- The Heavensdub Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXV
- House Party Screenshot Contest (EU)
- Bright-Eyed Superstars Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE in Frankfurt (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIV
- Starlight Celebration Haiku Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIII
- The “Eorzean Home Makeover (Extreme)” Contest (NA)
- Fan Festival 2017 (EU)
- Spooky Story Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE in Las Vegas (2016)
- The Rising Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXI
- "Do You Even /Pose?" Showdown! (NA)
- Fan Festival 2016 (NA)
- Dream Holiday Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE: E3 2016 Edition
- Heavensward Primal Haiku Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXX
- Letter from the Producer LIVE Part XXIX
- Letter from the Producer LIVE Part XXVIII
- Heavensward Music Contest (NA)
- Heavensward Music Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXVII
- Starlight Celebration Comic Strip Contest (NA)
- Starlight Celebration Comic Strip Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXVI
- Airship Components: Research and Development (NA)
- All Saints’ Wake Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXV
- Retainer Ad-Venture Contest (EU)
- Cartographers and Seekers Contest (NA)
- Hairstyle Design Contest
- Letter from the Producer LIVE Part XXIV
- Letter from the Producer LIVE Part XXIII
- Letter from the Producer LIVE Part XXII
- Letter from the Producer LIVE Part XXI
- Memories of Eorzea Screenshot Contest (NA)
- Memories of Eorzea Screenshot Contest (EU)
- Heavensward Free Company Recruitment Contest (NA)
- Heavensward Free Company Recruitment Contest (EU)
- A Realm Redubbed Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XX
- Letter from the Producer LIVE – Special Edition
- The Great Eorzean Cook-Off Contest (EU)
- Be My Valentione Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (EU)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (NA)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XIX
- Letter from the Producer LIVE Part XVIII
- Letter from the Producer LIVE in Las Vegas
- Grant a Wish Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XVII
- Moonfire Faire Screenshot Contest (NA)
- Moonfire Faire Screenshot Contest (EU)
- Fan Festival 2014 (NA)
- Fan Festival 2014 (EU)
- FFXIV: ARR One Year Anniversary Video Contest (NA)
- FFXIV: ARR One Year Anniversary Video Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XVI
- Eorzea IRL Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE: E3 Edition
- Letter from the Producer LIVE Part XV
- Letter from the Producer LIVE Part XIV
- Hatching-tide Screenshot Contest (NA)
- Hatching-tide Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XIII
- Little Ladies' Day Screenshot Contest (NA)
- Little Ladies' Day Screenshot Contest (EU)
- Valentione's Day Screenshot Contest (NA)
- Valentione's Day Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XII
- Heavensturn Screenshot Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (EU)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (NA)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (EU)
- FFXIV: ARR Free Company Recruitment Contest (NA)
- FFXIV: ARR Free Company Recruitment Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XI
- XIII Days – Your Fate is Sealed Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part X
- Doppelganger Screenshot Contest (NA)
- All Saints’ Wake Haiku Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part IX
- Ask Your Questions for the Mini Letter from the Producer LIVE at TGS!
- Sightseeing Screenshot Sweepstakes (NA/EU)
- Forums français
- Informations
- Assistance technique
- Rapports de problèmes
- La lettre du producteur
- Système de jeu
- Classes & Jobs
- Avis et retours sur les sites et l’appli
- Discussion
- Discussion générale
- Mondes (Japon)
- Mondes (Amérique du N./Europe/Océanie)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- Aide aux nouveaux joueurs
- Événements communautaires
- Evénements en cours
- Evénements passés
- Concours et tirages au sort
- Fan Festival 2023 de Londres
- Concours pour la mosaïque du 10e anniversaire
- « La lettre du producteur LIVE » : 68e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 65e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 64e émission
- Concours de captures d’écran d'exploration - Édition 2020
- « La lettre du producteur LIVE » : 60e émission
- Concours de captures d’écran - Une petite fête des étoiles entre amis
- « La lettre du producteur LIVE » : 56e émission
- Concours de captures d’écran – C’est ça la Veillée des Saints
- Mes questions à Yoshi-P et Banri Oda pour le Q&R de gamescom 2019 !
- « La lettre du producteur LIVE » : 53e émission
- Concours de cosplay à la gamescom 2019
- Concours de captures d’écran : De la Lumière aux Ténèbres
- Concours Pistolame à Japan Expo 2019 !
- Concours de Cosplay à Japan Expo 2019
- « Ma Viéra & mon Hrothgar » - Concours Twitter de capture d'écran
- Fabulœuf concours de captures d’écran
- « La lettre du producteur LIVE » : 50e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 49e émission
- Concours des meilleurs moments de l'année 2018
- Concours de BD’pouvante
- Concours de décoration d’intérieur
- Fan Festival 2019 à Paris
- Concours “Les dieux de la mode”
- « La lettre du producteur LIVE » : 44e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 43e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 42e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 41e émission
- Concours de cartes de vœux
- « La lettre du producteur LIVE » : 40e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 39e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 38e émission
- Concours de captures d’écran d’exploration
- « La lettre du producteur LIVE » : 37e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 35e émission
- Concours de captures d’écran spécial « House Party »
- Lettre du producteur LIVE à Francfort
- « La lettre du producteur LIVE » : 34e émission
- Concours de haïkus pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : 33e émission
- Concours d’histoires effrayantes
- Posez vos questions pour la lettre Live à Las Vegas (2016)
- Concours de captures d’écran pour la fête de la Commémoration
- « La lettre du producteur LIVE » : 31e émission
- Concours office de tourisme d’Éorzéa
- « La lettre du producteur LIVE » : 30e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 29e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 28e émission
- Concours de musique d’Heavensward
- « La lettre du producteur LIVE » : 27e émission
- Concours de comic strip pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : 26e émission
- Concours de captures d’écran pour la Veillée des saints
- « La lettre du producteur LIVE » : 25e émission
- Concours « Les aventures de mon servant »
- Concours de création de coupe de cheveux
- « La lettre du producteur LIVE » : 24e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 22e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 23e émission
- Concours de captures d’écran – Souvenirs d’Éorzéa
- Les compagnies libres recrutent pour Heavensward
- « La lettre du producteur LIVE » : 20e émission
- La lettre du producteur LIVE : émission spéciale
- Le grand concours culinaire d’Éorzéa
- Concours de captures d’écran pour la fête de la transition
- Concours de captures d’écran pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : dix-huitième émission
- Posez vos questions pour la lettre Live à Las Vegas
- Concours « Le jeu des souhaits »
- « La lettre du producteur LIVE » : 19e émission
- Fan Festival 2014
- Concours de captures d’écran pour les feux de la mort
- « La lettre du producteur LIVE » : dix-septième émission
- Concours vidéo pour le premier anniversaire
- « La lettre du producteur LIVE » : seizième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : quinzième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : quatorzième émission
- Concours de captures d’écran pour la chasse aux Prœufs
- « La lettre du producteur LIVE » : treizième émission
- Concours de captures d’écran pour la fête des demoiselles
- « La lettre du producteur LIVE » : douzième émission
- Concours de captures d’écran pour la fête de la transition
- Concours de captures d’écran pour la fête des étoiles
- Concours de captures d’écran pour la Valention
- Les compagnies libres recrutent
- « La lettre du producteur LIVE » : onzième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : dixième émission
- Concours Haiku d'Éorzéa - la Veillée des saints
- « La lettre du producteur LIVE » : neuvième émission
- Posez vos questions pour la lettre Live à Makuhari
- Deutsches Forum
- Ankündigungen
- Technischer Support
- Fehler melden
- Briefe des Produzenten
- Spielsystem
- Charakterklassen & Jobs
- Feedback
- Diskussionen
- Allgemeine Diskussionen
- Welten(Group JP)
- Welten(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- Für Einsteiger
- Community-Veranstaltungen
- Aktuelle Veranstaltungen
- Vergangene Veranstaltungen
- Wettbewerbe und Gewinnspiele
- Mosaik-Gewinnspiel zum 10. Jubiläum
- Fan Festival 2023 in London
- Der 68 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 65 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 64 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Reisetagebuch-Screenshot-Gewinnspiel
- Der 60. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sternenlichtertrupp-Screenshot-Wettbewerb
- Der 56. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Allerschutzheiligen Schauer-Spektakel-Screenshot-Wettbewerbs
- Eure Fragen an Naoki Yoshida und Banri Oda für die Q&A-Session auf der gamescom 2019
- Der 53. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Cosplay-Wettbewerb auf der gamescom 2019
- Vom Licht in die Dunkelheit Screenshot-Wettbewerb
- Cosplay-Wettbewerb auf der Japan Expo 2019
- „Viera & Hrothgar Makeover“ Twitter-Screenshot-Wettbewerb
- Wundereiersuche Screenshot-Wettbewerb
- Der 50. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 49. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Highlights des Jahres Wettbewerb
- Spuk und Schabernack Comic-Wettbewerb
- Inneneinrichtungs-Wettbewerb
- Fan Festival 2019 in Paris
- Extravaganza-Wettbewerb
- Der 44. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 43. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 42. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 41. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Wintergrüße-Wettbewerb
- Der 40. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 39. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 38. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sightseeing-Screenshot-Wettbewerb
- Der 37. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 35. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- House Party! Screenshot-Wettbewerb
- Brief des Produzenten LIVE in Frankfurt
- Der 34. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sternenlichtfest Haiku-Wettbewerb
- Der 33. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Gruselgeschichten-Wettbewerb
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Las Vegas (2016)
- Fest der Wiedergeburt Screenshot-Wettbewerb
- Der 31. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Traumurlaub-Wettbewerb
- Der 30. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 29. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 28. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Heavensward Musik-Wettbewerb
- Der 27. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Sternenlichtfest Comicstrip-Wettbwerb
- Der 26. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Allerschutzheiligen-Fest Screenshot-Wettbewerb
- Der 25. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Die Abenteuer des Tapferen Gehilfen–Wettbewerb
- Frisuren-Design-Wettbewerb
- Der 24. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 22. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 23. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Erinnerungen an Eorzea Screenshot-Wettbewerb
- Heavensward-Rekrutierungswettbewerb der freien Gesellschaften
- Der 20. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Brief des Produzenten – LIVE-Sondersendung!
- Großer, eorzäischer Kochwettbewerb
- Himmelswende Screenshot Wettbewerb
- Sternenlichtfest Screenshot-Wettbewerb
- Der 18. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Las Vegas
- Wünsche werden wahr- Wettbewerb
- Der 19. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Fan Festival 2014
- Feuermond-Reigen Screenshot-Wettbewerb
- Der 17. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Video-Wettbewerb zum einjährigen Jubiläum
- Der 16. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 15. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 14. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Wundereiersuche Screenshot-Wettbewerb
- Der 13. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Prinzessinnenfest Screenshot-Wettbewerb
- Valentiontag Screenshot Wettbewerb
- Der 12. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Himmelswende Screenshot Wettbewerb
- Sternenlichtfest Screenshot Wettbewerb
- Rekrutierungsvideo-Wettbewerb der Freien Gesellschaften
- Der 11. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 10. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Allerschutzheiligen-Haiku-Wettbewerb
- Der 9. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Makuhari!
- Version 1.0 Forum Archive
- Japanese Forums
- インフォメーション
- サポート
- アップデート
- ゲームシステム
- クラス&ジョブ
- ウェブサイトフィードバック
- 雑談
- 初心者用
- 写真館
- コミュニティイベント
- 開催中
- 終了
- ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア キャッチフレーズコンテスト
- 第8回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LA
- 第7回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第6回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 創作タマゴコンテスト
- 第5回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- マイ ベスト チョコボ
- ダラガブを探せ!
- エオルゼア メモリーズ
- 第4回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エオルゼア de 五・七・五
- 第3回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 残暑見舞いコンテスト
- Hidden Artifacts ~新生コンセプトアートクイズ~
- ガルーダトライアル
- 宿屋deつぶやき!イベント (JP)
- LSリクルートポスターコンテスト (JP)
- English Forums
- Information
- Support
- Updates
- Gameplay
- Classes & Jobs
- Feedback
- Community
- New Player Help
- In-Game Media
- Community Events
- Current Events
- Past Events
- Letter from the Producer LIVE Part VIII
- Letter from the Producer LIVE Part VII
- Letter from the Producer LIVE Part VI
- Eorzean Egg Decoration Contest
- Letter from the Producer LIVE Part V
- Eorzea Haiku Contest (EU)
- “Chocobos Rule the World” Contest!
- Memories of Eorzea Contest
- Letter from the Producer LIVE Part IV
- What if Dalamud Contest (EU)
- Tales from Eorzea (NA)
- Culinary Creation Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part III
- We Dub to Make it Ours (NA)
- These Grand Company Colors Don't Run!
- Hidden Artifacts
- Grant A Wish Contest (EU)
- Garuda—She's Like the Wind
- Culinary Creation Contest (NA)
- Valentione’s Dialogue Contest (EU)
- Valentione’s Day Love Letter Contest (NA)
- Forums français
- Informations
- Assistance sur le jeu
- Développement
- Système de jeu
- Classes & Jobs
- Avis et retours
- Discussion
- Aide aux nouveaux joueurs
- Galerie multimédia & articles
- Evénements organisés par l'équipe communautaire
- Evénements en cours
- Evénements passés
- « La lettre du producteur LIVE » : huitième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : septième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : sixième émission
- Concours : « Décoration d’Œufs Éorzéens »
- « La lettre du producteur LIVE » : cinquième émission
- Concours « Haïkus d’Eorzéa »
- Concours « Les Chocobos à la Conquête du Monde » !
- Concours « Souvenirs d’Eorzéa »
- « La lettre du producteur LIVE » : quatrième émission
- Concours : « Et si Dalamud était... »
- Concours de création culinaire
- « La lettre du producteur LIVE » : troisième émission
- Soutenons les grandes compagnies !
- Questions pour un Eorzéen
- Concours du jeu des souhaits
- L’épreuve de Garuda
- Concours de dialogue de la Valention
- Deutsches Forum
- Ankündigungen
- Support
- Update
- Spielsystem
- Charakterklassen & Jobs
- Feedback
- Diskussionen
- Für Einsteiger
- Medien
- Community-Veranstaltungen
- Aktuelle Veranstaltungen
- Vergangene Veranstaltungen
- Der 8. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 7. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 6. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Eorzäischer Ei-Dekorations-Wettbewerb
- Der 5. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Eorzea-Haiku-Wettbewerb
- Chocobos, die Herrscher der Welt
- Erinnerungen an Eorzea
- Der 4. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Was, wenn Dalamud … wäre?
- Kulinarische Kreationen
- Der 3. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Farben, die nicht die Segel streichen!
- Verborgene ARTefakte
- Wünsche werden wahr-Wettbewerb
- Garuda – Grausame Herrin der Stürme
- Valentione Dialog-Wettbewerb
- Japanese Forums
«
Previous Thread
|
Next Thread
»


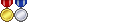


 Reply With Quote
Reply With Quote