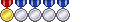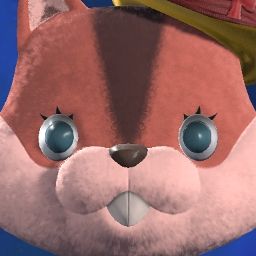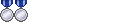今までの、そして黄金でもFF14のキャラクターに敵味方双方に対して入れ込むというか…共感したり好きと思えるキャラクターがいないんですけど、それはそれとして漆黒と暁月はキャラクターの魅せ方が上手かったなと思ってます。
一から十まで説明してくれるので少々くどいくらいなんですが(自分はこれで蚊帳の外感を感じて感情移入が出来なくなった)十全に納得感を与えるくれるというか、余計な事を考えないように思考を誘導してくれるので正直メインストーリーは楽に消化出来ました。
黄金はそういう事がなく、しかも最低限の説明すらなくこっちに全部答え方をぶん投げてくる(しかも答えが無い)のでそういう点では甘えを許してくれず、少し疲れるなとは感じています。
- Forum Top
- Japanese Forums
- ゲームシステム
- クエスト
- 黄金のレガシーのメインクエストの感想について
Thread: 黄金のレガシーのメインクエストの感想について
-
11-26-2024 11:54 AM #1741(31)
-
11-27-2024 02:25 AM #1742
個人的には目の前に広がってる切り拓くべき目標が「道」
切り拓いた後に出来たのが「路」って思ってるのだけど日本語って難しい。
そしてみんなが踏みしめて舗装され揺るぎない「道路」となる…みたいな。(2)Last edited by Eleven_Beef; 11-27-2024 at 02:28 AM.
ここでセーブするか?
-
11-27-2024 05:49 PM #1743Player
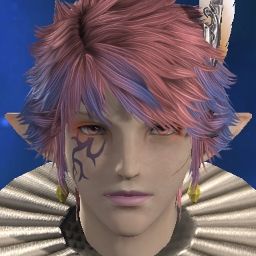
- Join Date
- Oct 2021
- Location
- グリダニア
- Posts
- 335
- Character
- Kill-or Die
- World
- Bahamut
- Main Class
- Viper Lv 100
キャラで言うとシェールとアルカディアの面々は結構良いと思いますが、それ以外は掘り下げが甘くて印象が薄いですね。
(16)
-
11-28-2024 02:48 AM #1744
7.1終わりましたが、7.0ほど酷くはありませんでしたが面白くもなかったです。
淡々と義務的に進めて気がついたら終わってました。
私はウクラマトにもゾラージャにもグルージャにもスフェーンにも感情移入できず興味も持てなかったのでもうダメなんでしょうね。
「どうでもいい、早く終われ」と思いながら進めていました。
7.3までこの関連の話が続くようなので、滅アラやったら7.4まで休止しようと思います。(95)
-
11-28-2024 12:39 PM #1745
7.1の内容を7.0のサカ・トラルでやればよかったんじゃと思いました。
あの自警団?がなんでメインに描かれたのか不思議ですね。面白くないし。
悪い奴がいるって騒ぐ銃だけは才能のあるありきたりのキャラ、
自警団の中に悪がいるのに気づかず何故かヤ・シュトラと連携して良い風にムービーにされたミコッテ。
あのムービー見せられても「はぁ...」って感じでした。
6.x〜7.1までヒカセンずーっと蚊帳の外なんですよね。7.0は特に黄金キャラのカメラマンだったし。
ヒカセンの冒険ではなく王族付きトラルツアー、鏡像世界を巻き込んだ盛大な兄弟喧嘩。
メインストーリーで描かれる冒険者としての新たなる冒険はどこ行っちゃったんでしょうか。
7.1をプレイして思ったのは、この後黄金郷をヤ・シュトラと一緒に旅する....なんて事にはならないですよね。
もうそれ6.xでやったし。
パッチ終わる度に周りのNPCが情報持ってきてなんとか出来るぜ!のノリも辞めてほしい。
6.4だったかの大量エーテルを運ぶ装置の作成も関わらせてよ。
暁のメンバーも適当に描かれるし、このあとのストーリーは全員置いてヒカセン1人で鏡像世界に行かせてください。(65)Last edited by Riki1217; 11-28-2024 at 06:11 PM. Reason: 誤字修正
-
11-28-2024 01:19 PM #1746
ここではどうしても否定的な声の方が大勢になってしまいますが、全体的にはどうなんでしょうね。
7.0は挑戦だったというのは理解しますが、それでも7.0は、8.0までには新生してほしいかも。
全面的な作り直しはもちろん無理ですけど、要所要所、辻褄が合わない部分などの手直しは検討してほしい。
もし作り直されたら、わたしはもう一回7.0をやり直して、脳内を上書きしたい。
ゾラージャが一番もったいなかったですが、ゾラージャ討滅戦がわたしの中で盛り上がらなかった原因は明確です。
例えば、蒼天から暁月に至るまで、メインクエストの主要キャラを討滅するときは、
ゲーム内でしっかりとそのキャラに対して意識が向くように仕向けられていました。
討滅戦の時点でそのキャラへの理解度が上がっていて、後は決着を付けるだけという感じでした。
一方でゾラージャは、直接的なぶつかり合いもないまま消えたので、前半終了時点では、モブキャラが消えたのと同じ感覚でした。
そしてヨカトラル襲撃は、モブキャラがおかしな敵になって戻ってきた、という程度の感覚でした。
ヘリテージファウンドに入ってからも、鏡像世界と融合した街の問題や、スフェーンなどに意識がずっと行っていたので、
ゾラージャに関して話題が出ても、ひどい言い方をすると「モブキャラのサブストーリー」という感じでした。
ゾラージャが行動を起こして二度目の襲撃が発生。結局、そこでもウクラマトとゾラージャの家族としての正直なぶつかり合いもなく、
むしろすぐに「スフェーンが実はxxxだった」という方に意識を向けさせられます。再びゾラージャは意識の外へ。。
結局、ゾラージャ討滅戦を迎えた時点では(リアルタイム進行時は)「モブキャラ討滅戦」という感覚だったんだと思います。
過去の討滅戦に照らし合わせたとき、この感覚は「メインキャラ討滅戦」というより「蛮神討滅戦」、
例えば「真ビスマルク討滅戦」や「ラクシュミ討滅戦」くらいの感覚だったように思います。
7.1のゾラージャの描写は良かったと思いますが、実際のところ、あれは掘り下げや補完などではないと受け取っています。
7.1のストーリーとして、元々必要だった描写だと思います。
もうひとつ、ゾラージャ討滅戦が盛り上がらなかった理由があるのですが、
それは、ヨカトラルの人々、トラル大陸の人々に対して、冒険者として『守らなきゃ!』と思えるような感覚になれなかったということです。
彼らは楽しいキャラですが、例えば紅蓮で圧政に苦しむ民たち、暁月で突然の終末に見舞われ逃げ惑うサベネア島の人たち、
彼らには、しぶとくもそこで「生活している人たち」という感覚がありました。「人間」を感じていました。
でも、トラル大陸の人々にはその感覚を殆ど持てませんでした。民族性や多文化には触れましたが「生ける人」という感じではありませんでした。
単に「トラル大陸を彩るモブキャラたち」という感覚だったんだと思います。「人」というより「デ〇〇ニーのキャラクター」みたいな感覚です。
だから、「トラル大陸の人々を護るためにもゾラージャを討つ!」みたいな感覚にならなかったのだと思います。
わたしが冒険者としてヘリテージファウンドに向かった理由は、トラル大陸の人々のためではなく、唯一、エレンヴィルのためだけでしたから。
(むしろヘリテージファウンドやソリューションナインの方が、そこで生きている人たち、という感覚は持てていました)
追記)トラル大陸では前半、短時間であっちこっち行かなければならず、それぞれの場所が薄味になってしまったのかも。
例えばペルペル族は「金の試練」のために奔走し、アルパカを捕まえ、、、その記憶が中心でした。
ペルペル族の紹介、特産品の紹介、観光としては良いのかもしれませんが、、、
「観光で訪れただけ」の村の人を「護ろう!」とは中々ならないですよね?そんな感じです。
アラミゴやドマ、サベネア島、ガレマルドなどの人たちは、先に問題があり、冒険者としても最初から「寄り添い」、
特に「名前のある特定の人への寄り添い」がありました。
今回は本当に観光旅行であちこち前半をめぐっているようなものなので、
基本的に平和ですし、広く、薄く、色々な人と次から次へと会っていきますし、寄り添う気持ちも不要でした。
単に保護者として同行しているだけでしたし。その結果として、「護る」という感覚に対してのズレが生まれたのだと思います。(58)Last edited by Emoo; 11-28-2024 at 06:07 PM. Reason: 追記
-
11-28-2024 04:54 PM #1747
黄金のレガシー7.0は決して悪い人材や素材を使っているわけではないので
週刊連載の1巻と5巻で絵や構図やコマ割が全然違うように、そういう部分は上手になっていくと思います
7.1でヒントトークに分厚さが出ましたよね、ああいう所です
ですが内容、というか、書きたいものですかね、それについては変わらないでしょう
それを変えたらその人たちが書く意味がなくなるので
黄金のレガシー7.0は7.1まで見ると、ゾラージャのあの終わり方を書きたい話だったんだなと思います
ゾラージャをゾラージャのまま描きたかった
その為に光の戦士という影響力のメテオからウクラマトを巨石の盾にしてゾラージャの孤独を守り
スフェーンという技術力の矛を手にするまで路を整えて進ませてやった
ゾラージャがわからなくて当然なんですよ、そのわからない所をそのまま描きたくてこっちに見せなかったんだから
ああいう描き方、終わり方をさせたかった部分というのは変えようがないです
作家性とも言えますが、繰り返しますがそれを変えてしまうとその人が書いている意味がないんです
その個性がつまらなかった人もしんどかった人も見たい人も楽しい人もいるので、賛否は別です
でも黄金のレガシー7.0では忘れられているんですけどFF14ってゲームなんですよね
少なくともゲーム体験という部分では黄金のレガシー7.0はゲームを騙った高画質小説映画モドキでした
当たり前の話ですが、本の読者、映画の観客、ゲームのプレイヤーではそれぞれ体験が違います
開発シナリオ班の書きたいもの書けるものと
「自分たちが作っているのはプレイヤーがいるゲームである」っていう自覚と
そのふたつの擦り合わせが出来ない限りは8.0も9.0もこのモドキは続くんですよ
「主役はステージに立つ人たちではなく遊んだ人のゲーム体験である」
意訳ですが、嬉しい言葉ですね。さて誰の言葉だったでしょう
キャラクターの在り方に向ける執念をもう少しプレイヤーの心の動きに向けていただけると嬉しいです(78)Last edited by tatuhito; 11-28-2024 at 04:56 PM. Reason: 脱字
-
11-28-2024 05:22 PM #1748(28)
Last edited by Emoo; 11-28-2024 at 05:25 PM.
-
11-28-2024 08:26 PM
Player
-
11-29-2024 03:34 AM #1749Player

- Join Date
- Aug 2019
- Posts
- 116
- Character
- Tubatania Sora
- World
- Yojimbo
- Main Class
- Thaumaturge Lv 70
7.1クリアまで見させて頂きました。
グルージャに関する謎の一つが解けて、この調子で色々あった謎の部分を解明して頂きたいと思いますが、正直手遅れな部分、以前指摘したマムージャ関連含めあまり深堀りされそうにないので残念ではあります。
まぁ、もう過ぎ去ったものなのでこれ以上はどうこう言いません。
が、コーナのお話に関して、置き去りにされた理由が語られましたが、それだけ大きな騒ぎになったのに、当のコーナは何も覚えていないのか?と疑問に思いました。
赤ん坊だったのかな?とも思ったのですが、あのときの僕は理解できなかった…というセリフから考えても、物心ついているなら覚えていておかしくないと思うのですけど…。
まさか、集落が魔物に襲われている間、ぐっすり眠っていたなんて言いませんよね?それに、仮に眠っていたとしても、起きた後、一切争った痕跡がなかったとは考えられにくいし
いくつかのテント等が壊れていたり、ロネークや人の遺体など、周りに襲撃されたような跡があったら、置き去りにされたとは思わなそうですが…
ちゃんと深く考えられたストーリーなのでしょうか?
それにロネークを線路に近づけないようにする策が、囲いを作るとかではなく、天敵のエーテル照射ということで……
ロネークってすごく繊細な生き物なんですよね?列車の音だけで不安定になるような生き物なのに、天敵のエーテルは照射されてもストレスにならないのですか?
部族的な理由から囲いや柵は作れないという事でしたが、逆にロネークにとっては負担になるような策だと思ったのは自分だけでしょうか?
柵があることより、天敵が近くを常にうろついているとロネーク達に認識させるような行為だと思ったので、そこもおかしく感じました。
これまで聞いてきた話から、なんだかそっちの方が問題が大きくなりそう。
かと言って、ロネーク達に配慮し続けるうちは、正直問題解決が出来そうではないので、何かしらの方法は必要だったと思いますが…
でも、まだ柵があって、線路に入れないようにしておいた方が、負担はなさそうだと思ったのですけれど…どうなんでしょ。
いちいち重箱の角をつつくような真似はしたくありませんが、パッと聞いてすぐ違和感を持ってしまうようなお話は…
暁月までは個人的にそんな事なかったので困惑してます。今後のお話もちょっと不安になってきて怖いです。(56)
-
11-29-2024 04:32 AM #1750Player

- Join Date
- May 2020
- Posts
- 1,866
- Character
- Nanami Nanananami
- World
- Atomos
- Main Class
- Botanist Lv 100
友好部族クエで王女誘拐犯の人の背景とその後が描かれ、次いでラザハンとの国交についての具体性も薄く語られてこれで終わりにさせられそう。
アライアンスでサレージャその後が明かされて、新しいバクージャジャの生活を垣間見て、あとは7.15のお得意様も列車野郎どものとこのアフターエピソードが語られるような事を匂わされています。
これらはメインシナリオクエストでやってほしかった。
駆け足で色々広げ過ぎたから、こういった点がメインから零れ落ちて全体的に薄味になった、やってたらもう少しいいものになってた気がする、7.1メインもそう思わせるコーナ兄さんのバックボーン描写ありましたし、色々手を付ければ付けるほどそんな印象が強くなっていきます。
以前も、派手な絵変わりがないと不安に思ったんだろうかみたいな事を書いた覚えがあるのですが、今回の一般フィールド戦闘曲については、表題曲の中から伊藤友馬さんのバイオリンパートを選んで使ったのが「渋いね」とか、Primalsのライブだったかで言ってた覚えがあります。
これで戦闘するのを良しとしてくれるプレイヤーは通だね、みたいな。
そこら辺はプレイヤーを信頼してくれるのであれば、シナリオに関しても後半の超展開がなくて本当に王位継承戦一本、トラルの大冒険だけでもきちんとモノづくりすれば、あの戦闘曲を良しとするプレイヤーなら納得してくれると、なぜここでは信頼はしてくれなかったのだろうかと、どうにも残念に思います。(27)
Quick Navigation
クエスト
Top
- Forums
- Japanese Forums
- ニュース
- テクニカルサポート
- 不具合報告
- プロデューサーレター
- ゲームシステム
- クラス&ジョブ
- ウェブサイト/アプリフィードバック
- 雑談
- この装備を武具投影したい!!
- あのジョブのUIレイアウトが知りたい!
- ジェネラルディスカッション
- ワールド(Group JP)
- ワールド(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- 初心者用
- コミュニティイベント
- 開催中
- 終了
- 第8回14時間生放送
- 第68回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第65回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第64回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第60回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第56回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第53回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張!ひろしチャレンジ 応援プレゼント企画
- 第50回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第49回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- ハウジングコーディネートコンテスト
- 第44回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第43回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第42回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第41回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第40回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第39回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第38回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第37回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第35回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- ハウジングデコレーションコンテスト
- 第34回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第33回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LAS VEGAS (2016)
- 髙井浩の○○チャレンジ!応援企画
- 第31回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 紅蓮祭スクリーンショットコンテスト 2016
- 第30回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第28回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- サントラ発売記念!奏天のイシュガルドコンテスト
- 第27回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 星芒祭 4コマスクリーンショットコンテスト
- 第26回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第25回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- パンプキンクッキーコンテスト
- 髪型デザインコンテスト
- 第24回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第23回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第22回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エオルゼア百景 in 装備コーディネートコンテスト
- 第21回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 思い出スクリーンショットコンテスト
- フリーカンパニーPRキャンペーン
- 第20回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- FFXIVプロデューサーレターLIVE特別編
- ヴァレンティオンデーチョコレートコンテスト
- 闘会議2015 予想イベント
- 降神祭スクリーンショットコンテスト
- 星芒祭スクリーンショットコンテスト
- 第19回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第18回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LAS VEGAS
- 新生FFXIV キャプションコンテスト
- 紅蓮祭スクリーンショットコンテスト
- 第17回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 新生FFXIV 1周年記念PVコンテスト
- ミラプリ スクリーンショットコンテスト
- 第16回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第15回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第14回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エッグハントスクリーンショットコンテスト
- 出張プロデューサーレターLIVE
- 第13回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- プリンセスデースクリーンショットコンテスト
- 第12回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 降神祭スクリーンショットコンテスト
- 星芒祭スクリーンショットコンテスト
- ヴァレンティオンデースクリーンショットコンテスト
- フリーカンパニー紹介PVコンテスト
- 第11回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第10回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 守護天節スクリーンショットコンテスト
- 第9回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張プロデューサーレターLIVE in 幕張
- English Forums
- Information
- Technical Support
- Bug Reports
- Letters from the Producer
- Gameplay
- Classes & Jobs
- Feedback
- Community
- General Discussion
- Worlds(Group JP)
- Worlds(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- New Player Help
- Community Events
- Current Events
- Past Events
- Contests and Sweepstakes
- Fan Festival 2023 in London
- 10th Anniversary Mosaic Art Sweepstakes (NA/EU)
- Fan Festival 2023 in Las Vegas
- Ask Your Questions for the PAX East 2023 Q&A
- Crystalline Conflict Community Cup (North America)
- Letter from the Producer LIVE Part LXVIII
- Letter from the Producer LIVE Part LXV
- Letter from the Producer LIVE Part LXIV
- Letter from the Producer LIVE Part LX
- Everything’s on the Line! Screenshot Contest (NA)
- Ask Yusuke Mogi Your Questions for the PAX East 2020 Panel
- “A Star Light Party” Screenshot Contest (EU/PAL)
- Star Companion Screenshot Sweepstakes (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part LVI
- “This is All Saints’ Wake” Screenshot Contest (EU/PAL)
- A Glamourous Guise Screenshot Contest (NA)
- Memoirs of Adventure Creative Writing Contest (NA)
- Ask Yoshi-P and Banri Oda Your Questions for the gamescom 2019 Q&A
- Letter from the Producer LIVE Part LIII
- Cosplay Contest at gamescom 2019 (EU)
- Become the Darkness Screenshot Sweepstakes! (NA)
- From Light to Darkness Screenshot Contest (EU/PAL)
- Frights and Delights Comic Contest (EU/PAL)
- Cosplay Contest at Japan Expo 2019 (EU)
- Ogre Pumpkin Carve Off Contest: The REDUX (NA)
- My new Viera and Hrothgar" Twitter Screenshot Contest (NA/EU)
- ”Sea Breeze Celebration” Screenshot Contest (NA)
- An Egg-Squisite Season Screenshot Contest (EU/PAL)
- The Eorzean Interior Design Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XLIX
- Letter from the Producer LIVE Part L
- FLOWERS FOR ALL SCREENSHOT CONTEST
- The Eorzean Interior Design Contest (EU)
- Highlights of the Year Contest (EU)
- Fan Festival 2018 in Las Vegas (NA)
- Starlight Scenarios Comic Contest (NA)
- Fan Festival 2019 in Paris (EU)
- The "As Good As Gold" Screenshot Contest (NA)
- Glamour Extravaganza Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE: E3 2018 Edition
- Letter from the Producer LIVE Part XLIV
- Letter from the Producer LIVE Part XLIII
- The "Be My Valentione!" Creative Writing Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XLII
- Letter from the Producer LIVE Part XLI
- Holiday Greetings Contest (EU)
- Starlight Starbright Screenshot Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XL
- Ogre Pumpkin Carve Off Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIX
- Letter from the Producer LIVE Part XXXVIII
- PAX West 2017 (NA)
- Sightseeing Screenshot Contest! (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXVII
- And… Action! (NA)
- The Heavensdub Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXV
- House Party Screenshot Contest (EU)
- Bright-Eyed Superstars Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE in Frankfurt (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIV
- Starlight Celebration Haiku Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIII
- The “Eorzean Home Makeover (Extreme)” Contest (NA)
- Fan Festival 2017 (EU)
- Spooky Story Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE in Las Vegas (2016)
- The Rising Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXI
- "Do You Even /Pose?" Showdown! (NA)
- Fan Festival 2016 (NA)
- Dream Holiday Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE: E3 2016 Edition
- Heavensward Primal Haiku Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXX
- Letter from the Producer LIVE Part XXIX
- Letter from the Producer LIVE Part XXVIII
- Heavensward Music Contest (NA)
- Heavensward Music Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXVII
- Starlight Celebration Comic Strip Contest (NA)
- Starlight Celebration Comic Strip Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXVI
- Airship Components: Research and Development (NA)
- All Saints’ Wake Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXV
- Retainer Ad-Venture Contest (EU)
- Cartographers and Seekers Contest (NA)
- Hairstyle Design Contest
- Letter from the Producer LIVE Part XXIV
- Letter from the Producer LIVE Part XXIII
- Letter from the Producer LIVE Part XXII
- Letter from the Producer LIVE Part XXI
- Memories of Eorzea Screenshot Contest (NA)
- Memories of Eorzea Screenshot Contest (EU)
- Heavensward Free Company Recruitment Contest (NA)
- Heavensward Free Company Recruitment Contest (EU)
- A Realm Redubbed Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XX
- Letter from the Producer LIVE – Special Edition
- The Great Eorzean Cook-Off Contest (EU)
- Be My Valentione Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (EU)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (NA)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XIX
- Letter from the Producer LIVE Part XVIII
- Letter from the Producer LIVE in Las Vegas
- Grant a Wish Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XVII
- Moonfire Faire Screenshot Contest (NA)
- Moonfire Faire Screenshot Contest (EU)
- Fan Festival 2014 (NA)
- Fan Festival 2014 (EU)
- FFXIV: ARR One Year Anniversary Video Contest (NA)
- FFXIV: ARR One Year Anniversary Video Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XVI
- Eorzea IRL Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE: E3 Edition
- Letter from the Producer LIVE Part XV
- Letter from the Producer LIVE Part XIV
- Hatching-tide Screenshot Contest (NA)
- Hatching-tide Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XIII
- Little Ladies' Day Screenshot Contest (NA)
- Little Ladies' Day Screenshot Contest (EU)
- Valentione's Day Screenshot Contest (NA)
- Valentione's Day Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XII
- Heavensturn Screenshot Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (EU)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (NA)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (EU)
- FFXIV: ARR Free Company Recruitment Contest (NA)
- FFXIV: ARR Free Company Recruitment Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XI
- XIII Days – Your Fate is Sealed Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part X
- Doppelganger Screenshot Contest (NA)
- All Saints’ Wake Haiku Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part IX
- Ask Your Questions for the Mini Letter from the Producer LIVE at TGS!
- Sightseeing Screenshot Sweepstakes (NA/EU)
- Forums français
- Informations
- Assistance technique
- Rapports de problèmes
- La lettre du producteur
- Système de jeu
- Classes & Jobs
- Avis et retours sur les sites et l’appli
- Discussion
- Discussion générale
- Mondes (Japon)
- Mondes (Amérique du N./Europe/Océanie)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- Aide aux nouveaux joueurs
- Événements communautaires
- Evénements en cours
- Evénements passés
- Concours et tirages au sort
- Fan Festival 2023 de Londres
- Concours pour la mosaïque du 10e anniversaire
- « La lettre du producteur LIVE » : 68e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 65e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 64e émission
- Concours de captures d’écran d'exploration - Édition 2020
- « La lettre du producteur LIVE » : 60e émission
- Concours de captures d’écran - Une petite fête des étoiles entre amis
- « La lettre du producteur LIVE » : 56e émission
- Concours de captures d’écran – C’est ça la Veillée des Saints
- Mes questions à Yoshi-P et Banri Oda pour le Q&R de gamescom 2019 !
- « La lettre du producteur LIVE » : 53e émission
- Concours de cosplay à la gamescom 2019
- Concours de captures d’écran : De la Lumière aux Ténèbres
- Concours Pistolame à Japan Expo 2019 !
- Concours de Cosplay à Japan Expo 2019
- « Ma Viéra & mon Hrothgar » - Concours Twitter de capture d'écran
- Fabulœuf concours de captures d’écran
- « La lettre du producteur LIVE » : 50e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 49e émission
- Concours des meilleurs moments de l'année 2018
- Concours de BD’pouvante
- Concours de décoration d’intérieur
- Fan Festival 2019 à Paris
- Concours “Les dieux de la mode”
- « La lettre du producteur LIVE » : 44e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 43e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 42e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 41e émission
- Concours de cartes de vœux
- « La lettre du producteur LIVE » : 40e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 39e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 38e émission
- Concours de captures d’écran d’exploration
- « La lettre du producteur LIVE » : 37e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 35e émission
- Concours de captures d’écran spécial « House Party »
- Lettre du producteur LIVE à Francfort
- « La lettre du producteur LIVE » : 34e émission
- Concours de haïkus pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : 33e émission
- Concours d’histoires effrayantes
- Posez vos questions pour la lettre Live à Las Vegas (2016)
- Concours de captures d’écran pour la fête de la Commémoration
- « La lettre du producteur LIVE » : 31e émission
- Concours office de tourisme d’Éorzéa
- « La lettre du producteur LIVE » : 30e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 29e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 28e émission
- Concours de musique d’Heavensward
- « La lettre du producteur LIVE » : 27e émission
- Concours de comic strip pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : 26e émission
- Concours de captures d’écran pour la Veillée des saints
- « La lettre du producteur LIVE » : 25e émission
- Concours « Les aventures de mon servant »
- Concours de création de coupe de cheveux
- « La lettre du producteur LIVE » : 24e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 22e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 23e émission
- Concours de captures d’écran – Souvenirs d’Éorzéa
- Les compagnies libres recrutent pour Heavensward
- « La lettre du producteur LIVE » : 20e émission
- La lettre du producteur LIVE : émission spéciale
- Le grand concours culinaire d’Éorzéa
- Concours de captures d’écran pour la fête de la transition
- Concours de captures d’écran pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : dix-huitième émission
- Posez vos questions pour la lettre Live à Las Vegas
- Concours « Le jeu des souhaits »
- « La lettre du producteur LIVE » : 19e émission
- Fan Festival 2014
- Concours de captures d’écran pour les feux de la mort
- « La lettre du producteur LIVE » : dix-septième émission
- Concours vidéo pour le premier anniversaire
- « La lettre du producteur LIVE » : seizième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : quinzième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : quatorzième émission
- Concours de captures d’écran pour la chasse aux Prœufs
- « La lettre du producteur LIVE » : treizième émission
- Concours de captures d’écran pour la fête des demoiselles
- « La lettre du producteur LIVE » : douzième émission
- Concours de captures d’écran pour la fête de la transition
- Concours de captures d’écran pour la fête des étoiles
- Concours de captures d’écran pour la Valention
- Les compagnies libres recrutent
- « La lettre du producteur LIVE » : onzième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : dixième émission
- Concours Haiku d'Éorzéa - la Veillée des saints
- « La lettre du producteur LIVE » : neuvième émission
- Posez vos questions pour la lettre Live à Makuhari
- Deutsches Forum
- Ankündigungen
- Technischer Support
- Fehler melden
- Briefe des Produzenten
- Spielsystem
- Charakterklassen & Jobs
- Feedback
- Diskussionen
- Allgemeine Diskussionen
- Welten(Group JP)
- Welten(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- Für Einsteiger
- Community-Veranstaltungen
- Aktuelle Veranstaltungen
- Vergangene Veranstaltungen
- Wettbewerbe und Gewinnspiele
- Mosaik-Gewinnspiel zum 10. Jubiläum
- Fan Festival 2023 in London
- Der 68 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 65 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 64 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Reisetagebuch-Screenshot-Gewinnspiel
- Der 60. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sternenlichtertrupp-Screenshot-Wettbewerb
- Der 56. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Allerschutzheiligen Schauer-Spektakel-Screenshot-Wettbewerbs
- Eure Fragen an Naoki Yoshida und Banri Oda für die Q&A-Session auf der gamescom 2019
- Der 53. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Cosplay-Wettbewerb auf der gamescom 2019
- Vom Licht in die Dunkelheit Screenshot-Wettbewerb
- Cosplay-Wettbewerb auf der Japan Expo 2019
- „Viera & Hrothgar Makeover“ Twitter-Screenshot-Wettbewerb
- Wundereiersuche Screenshot-Wettbewerb
- Der 50. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 49. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Highlights des Jahres Wettbewerb
- Spuk und Schabernack Comic-Wettbewerb
- Inneneinrichtungs-Wettbewerb
- Fan Festival 2019 in Paris
- Extravaganza-Wettbewerb
- Der 44. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 43. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 42. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 41. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Wintergrüße-Wettbewerb
- Der 40. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 39. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 38. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sightseeing-Screenshot-Wettbewerb
- Der 37. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 35. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- House Party! Screenshot-Wettbewerb
- Brief des Produzenten LIVE in Frankfurt
- Der 34. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sternenlichtfest Haiku-Wettbewerb
- Der 33. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Gruselgeschichten-Wettbewerb
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Las Vegas (2016)
- Fest der Wiedergeburt Screenshot-Wettbewerb
- Der 31. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Traumurlaub-Wettbewerb
- Der 30. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 29. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 28. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Heavensward Musik-Wettbewerb
- Der 27. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Sternenlichtfest Comicstrip-Wettbwerb
- Der 26. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Allerschutzheiligen-Fest Screenshot-Wettbewerb
- Der 25. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Die Abenteuer des Tapferen Gehilfen–Wettbewerb
- Frisuren-Design-Wettbewerb
- Der 24. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 22. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 23. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Erinnerungen an Eorzea Screenshot-Wettbewerb
- Heavensward-Rekrutierungswettbewerb der freien Gesellschaften
- Der 20. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Brief des Produzenten – LIVE-Sondersendung!
- Großer, eorzäischer Kochwettbewerb
- Himmelswende Screenshot Wettbewerb
- Sternenlichtfest Screenshot-Wettbewerb
- Der 18. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Las Vegas
- Wünsche werden wahr- Wettbewerb
- Der 19. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Fan Festival 2014
- Feuermond-Reigen Screenshot-Wettbewerb
- Der 17. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Video-Wettbewerb zum einjährigen Jubiläum
- Der 16. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 15. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 14. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Wundereiersuche Screenshot-Wettbewerb
- Der 13. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Prinzessinnenfest Screenshot-Wettbewerb
- Valentiontag Screenshot Wettbewerb
- Der 12. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Himmelswende Screenshot Wettbewerb
- Sternenlichtfest Screenshot Wettbewerb
- Rekrutierungsvideo-Wettbewerb der Freien Gesellschaften
- Der 11. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 10. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Allerschutzheiligen-Haiku-Wettbewerb
- Der 9. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Makuhari!
- Version 1.0 Forum Archive
- Japanese Forums
- インフォメーション
- サポート
- アップデート
- ゲームシステム
- クラス&ジョブ
- ウェブサイトフィードバック
- 雑談
- 初心者用
- 写真館
- コミュニティイベント
- 開催中
- 終了
- ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア キャッチフレーズコンテスト
- 第8回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LA
- 第7回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第6回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 創作タマゴコンテスト
- 第5回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- マイ ベスト チョコボ
- ダラガブを探せ!
- エオルゼア メモリーズ
- 第4回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エオルゼア de 五・七・五
- 第3回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 残暑見舞いコンテスト
- Hidden Artifacts ~新生コンセプトアートクイズ~
- ガルーダトライアル
- 宿屋deつぶやき!イベント (JP)
- LSリクルートポスターコンテスト (JP)
- English Forums
- Information
- Support
- Updates
- Gameplay
- Classes & Jobs
- Feedback
- Community
- New Player Help
- In-Game Media
- Community Events
- Current Events
- Past Events
- Letter from the Producer LIVE Part VIII
- Letter from the Producer LIVE Part VII
- Letter from the Producer LIVE Part VI
- Eorzean Egg Decoration Contest
- Letter from the Producer LIVE Part V
- Eorzea Haiku Contest (EU)
- “Chocobos Rule the World” Contest!
- Memories of Eorzea Contest
- Letter from the Producer LIVE Part IV
- What if Dalamud Contest (EU)
- Tales from Eorzea (NA)
- Culinary Creation Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part III
- We Dub to Make it Ours (NA)
- These Grand Company Colors Don't Run!
- Hidden Artifacts
- Grant A Wish Contest (EU)
- Garuda—She's Like the Wind
- Culinary Creation Contest (NA)
- Valentione’s Dialogue Contest (EU)
- Valentione’s Day Love Letter Contest (NA)
- Forums français
- Informations
- Assistance sur le jeu
- Développement
- Système de jeu
- Classes & Jobs
- Avis et retours
- Discussion
- Aide aux nouveaux joueurs
- Galerie multimédia & articles
- Evénements organisés par l'équipe communautaire
- Evénements en cours
- Evénements passés
- « La lettre du producteur LIVE » : huitième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : septième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : sixième émission
- Concours : « Décoration d’Œufs Éorzéens »
- « La lettre du producteur LIVE » : cinquième émission
- Concours « Haïkus d’Eorzéa »
- Concours « Les Chocobos à la Conquête du Monde » !
- Concours « Souvenirs d’Eorzéa »
- « La lettre du producteur LIVE » : quatrième émission
- Concours : « Et si Dalamud était... »
- Concours de création culinaire
- « La lettre du producteur LIVE » : troisième émission
- Soutenons les grandes compagnies !
- Questions pour un Eorzéen
- Concours du jeu des souhaits
- L’épreuve de Garuda
- Concours de dialogue de la Valention
- Deutsches Forum
- Ankündigungen
- Support
- Update
- Spielsystem
- Charakterklassen & Jobs
- Feedback
- Diskussionen
- Für Einsteiger
- Medien
- Community-Veranstaltungen
- Aktuelle Veranstaltungen
- Vergangene Veranstaltungen
- Der 8. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 7. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 6. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Eorzäischer Ei-Dekorations-Wettbewerb
- Der 5. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Eorzea-Haiku-Wettbewerb
- Chocobos, die Herrscher der Welt
- Erinnerungen an Eorzea
- Der 4. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Was, wenn Dalamud … wäre?
- Kulinarische Kreationen
- Der 3. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Farben, die nicht die Segel streichen!
- Verborgene ARTefakte
- Wünsche werden wahr-Wettbewerb
- Garuda – Grausame Herrin der Stürme
- Valentione Dialog-Wettbewerb
- Japanese Forums
«
Previous Thread
|
Next Thread
»


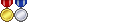

 Reply With Quote
Reply With Quote