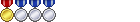いっそ浄化のリキャストを大幅に早くして、かわりに近接職はTP キャスターはMPで使用とかどない?
あと全ジョブのアクションに方向指定廃止
- Forum Top
- Japanese Forums
- ゲームシステム
- PvP
- PVPを本気で修正希望の人のための要望スレ
Thread: PVPを本気で修正希望の人のための要望スレ
-
06-01-2014 12:07 AM #551(2)
-
06-01-2014 11:44 AM #552Player

- Join Date
- Sep 2013
- Location
- グリダニア、森の都!
- Posts
- 706
- Character
- Chiara Chiaro
- World
- Alexander
- Main Class
- Fisher Lv 50
浄化のリキャストをただ早くするとデバフやCCスキル全般がただ死亡するだけですよね。
方向指定スキルがそもそもあるのが竜モのみで廃止したら現在弱いわけではないこの2職が単純に強くなるだけで絶賛死亡中の詩人のメリットがまたひとつ消えて意味不明の距離補正だけ残ることになりますね。
CCは効果や影響は高くていいんですよ。
問題はその効果に見合ったリスクや決めるための難度が伴っていない点ですから。
ガンはやっぱり迅速魔がのることと効果時間や最もCCに注意しなければならないヒーラーに対抗策が少ないことですね。
短時間での解除は全員が出来る必要がなくヒーラーの解除能力を上げればいいと思いますよ。(0)
-
06-01-2014 12:00 PM #553Player
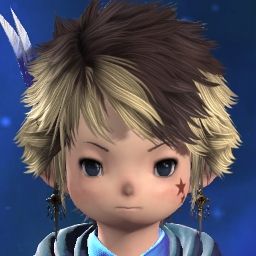
- Join Date
- Aug 2013
- Location
- ウルダハ
- Posts
- 585
- Character
- Lu'na Fact
- World
- Chocobo
- Main Class
- Arcanist Lv 70
・ヒーラーのみ、浄化を範囲スキル化に可能
・詩人の影縫いのリキャストを元の12秒に戻す
・スリプル・バインドの更新は効果中および効果終了5秒以内は更新不可
・ゲームバランスが崩れている40制限以下の廃止、50マッチングのみにし、モラル有マッチングとモラル無マッチングに分ける
→報酬はモラル無マッチングの勝ち分がモラル有マッチングの負け分になるように調整
多分これだけで全然違うと思いますけどね。
あとは耐性を上げることによる睡眠時間の低下率を上げてもいいぐらいかと思います。(5)Last edited by LunaWells; 06-01-2014 at 12:06 PM.
-
06-01-2014 12:59 PM #554
弓術士PvPアクションのファーショット、事実上はミザリーエンド程度のダメージを1回与えるアビリティでしかないので、振り直ししてブラストショットに変えました
使用後に射程30m距離減衰無視になるバフがつく、ぐらいにしないと、使いどころがないですよね、これ
まあ、弓にかぎらず、PvPアクションは微妙なものが多かったりするんですけど(1)ボクの常識はボクだけの常識
キミの常識はキミだけの常識にゃ
-
06-01-2014 05:58 PM #555
-
06-02-2014 02:35 AM #556
斧はアクアオーラ無い学者相手ならソロで瞬殺できる事もありますからね
ヒラやった事ある人なら分ると思いますが
竜とコンビで来られると絶望しかないですよね
フルスイングの変わりに味方を守る別のPvPアクションを追加
もしくは学にアクアオーラ追加でまだマシになりそうですかね
あとウルヴズジェイル係船場にPvPアクションが使える木人が欲しいですねー
死にエリアになってるので是非お願いします(0)Last edited by ff11-CarbuncleUser; 06-02-2014 at 03:25 AM.
-
06-02-2014 07:56 AM #557Player
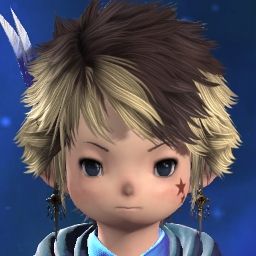
- Join Date
- Aug 2013
- Location
- ウルダハ
- Posts
- 585
- Character
- Lu'na Fact
- World
- Chocobo
- Main Class
- Arcanist Lv 70
別スレでも散々述べられてますが、学者は先読みが大事です。
それとPVPスキルを見てもわかるように、学に関しては特に攻撃は最大の防御という言葉も当てはまります。
恐らく40制限の話をしているのだとは思いますが、40制限では確かに3タゲに捕まれば浄化、調和、専心を組み合わせても、そのあとも何の支援もなければまず生き残るのは厳しいかとは思います。
となると、囲まれる前に学者がソロで対処できるのは、
・事前にゴウナントや囁きをいれる
・囲まれそうだなというタイミングでウイルスを使う
・相手のHPを削る
→ベインを広げて捨身を使いづらくさせる
→ヒールをもらいに行かせたり、ヒールを分散させて相手ヒラの自己ヒールを減らす
白とは違って火力が出ますから、うまく守ればヒラに対して4タゲ、もしくはヒラ2タゲ、レンジ2タゲのように攻めることができるということをDPSタンク勢が理解していて、それに合わせて動きをしていれば勝率は上がるかと思います。
まあもっとも、40制限がスキルの封じられ方からして、白と比べて学者の難易度だけオカシイのは事実ですけども。
40制限さえなくなれば、アクアオーラを移植などしなくても、50に関しては耐える方法はいくらでもあるとは思うのですがね。(3)Last edited by LunaWells; 06-02-2014 at 08:01 AM.
-
06-02-2014 08:19 AM #558Player

- Join Date
- Jan 2014
- Location
- ウルダハ
- Posts
- 966
- Character
- Labbit Zulu
- World
- Titan
- Main Class
- Gunbreaker Lv 100
あくまでもPvPコンテンツを、このゲームの柱としてこれからやっていくのであれば、最優先としては
・PVPの人口を増やすこと
これ以外にありませんよね。これに関してはおそらく、スレッドの方すべてが同意していただけるかと思います。
で、話の流れを見ていてPvPとPvEの装備云々、って話を見かけたのですが私としては装備は共通でもいいのではないかと考えています。
(先に言っておくと、結果として今までPvPで頑張って装備を集めた方を否定する形になるのですが、あくまでもPvPのこれからを考える上での主張であることをご考慮頂きたいです。)
正直に言いますと、コンテンツが面白い面白くない以前にまずプレイヤーは「そのコンテンツをやる必要があるか」という判断基準を下してそのコンテンツを「まずはかじってみよう」という段階に入ります。
で、「やる必要がない」と感じたらやる人はいなくなります。現状のPvPは、PvPをやってPvP装備を手に入れて、PvPをやるという形なので、PvPをやる必要性というのをPvPに見出だせなければやらないんですよね。
これはケースを入れ替えれば現状のエンドコンテンツと同じで、バハムート侵攻編を攻略しようと思わない層は4層をクリアするための防具であるハイアラガン防具を手に入れに、1-3層をやりません。現に侵攻編のユーザーは5%程度だと言われています。
続きます。次のポストで具体的な改善案、これからの方向性の提案をします。(11)
-
06-02-2014 08:20 AM #559Player

- Join Date
- Jan 2014
- Location
- ウルダハ
- Posts
- 966
- Character
- Labbit Zulu
- World
- Titan
- Main Class
- Gunbreaker Lv 100
ですので、まずPvPコンテンツを復興させるために手っ取り早いのはもっと広い戸口での「やる意味を与える」ことだと思っています。
「わたしのかんがえたさいきょうのぴーぶいぴー」程度に見てもらえれば構いませんが、具体例を出していくのであれば、
1. モラルを廃止したPvP報酬限定のPvE装備を用意する(基本性能はPvEで、PvP専用マテリアのみはめられるようにする)
簡単に言うと、PvE装備の入手手段、いわばパッチごとの最強装備の入手手段にしてしまうことでその装備が欲しい層というものを取り込んでいきます。
コンテンツというのは、人数が増えていけば「一緒にやろうぜ」という作用が働くので、PvPに関してもフレンドを誘ってやっていこう!といった流れを作ることはできるかと思います。
エンドコンテンツと違い大縄跳びでやる必要もなく、1回1回も短く終わるのでバハムートみたいに時間制約が無いのもいいですよね。
2. 公式がPvPにスポットを当てたイベントを開催し、そのイベント報酬で実用的な武器を配布する
例えばチーム戦で大会を開くなどをし、1ヶ月に1回、2ヶ月に1回といったペースでもいいでしょう。公式でPvP大会をデータセンターごとでもワールドごとでも開き、優勝チームにはそのパッチでの一番高いILを持った武器を入手させるといったことをしてもよいかと思います。
現状で言うならハイアラガン武器に匹敵するIL115武器でしょうか。
今のPvPで、ララ♀黒魔道士のアニマル装備がかわいい!ということでPvPをやる人は周りではちらほらと増えているので、PvP自体に興味があるかないかは置いといてもキッカケを作ることでやる人は増えると思います。
きっかけを持ってやる人が増えないことにはこの先のコンテンツ設計も何もかもやることも出来ませんし、何より不人気コンテンツに開発リソースをこれから割くわけにも行かないでしょう。
あくまでも私のは、今PvPをやっている人に対してというよりはこれからのPvPをコンテンツとしてどうたて直すかという意見であることを改めて置いておきます。
ですので、おそらく今PvPをかなりやりこんでる方からすれば「は?ふざけんな!」となることも重々承知していることを前置きさせていただきます。(8)
-
06-04-2014 11:45 PM #560
初心者やカジュアルユーザーを呼び込むことを考えたら、もう少し分かりやすいUIにしないといけないように思います。
味方がどこにいて、敵がどこにいて、どこで戦っていて、いまどういう状況なのか、そういう把握が慣れないと非常に難しいですよね。
たぶん大半のユーザーには「訳が分からないうちに、ボコられて終わった……」みたいな経験が多いのではないでしょうか。それで、「もう二度と行かない」みたいな気持ちにさせてしまっているケースも多いように思います。
そこを乗り越えて、ある程度把握できるようになるまでには何百戦もしないといけないと思いますが、そこまで辛抱できる人は限られていますよね。(7)
Quick Navigation
PvP
Top
- Forums
- Japanese Forums
- ニュース
- テクニカルサポート
- 不具合報告
- プロデューサーレター
- ゲームシステム
- クラス&ジョブ
- ウェブサイト/アプリフィードバック
- 雑談
- この装備を武具投影したい!!
- あのジョブのUIレイアウトが知りたい!
- ジェネラルディスカッション
- ワールド(Group JP)
- ワールド(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- 初心者用
- コミュニティイベント
- 開催中
- 終了
- 第8回14時間生放送
- 第68回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第65回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第64回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第60回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第56回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第53回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張!ひろしチャレンジ 応援プレゼント企画
- 第50回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第49回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- ハウジングコーディネートコンテスト
- 第44回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第43回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第42回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第41回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第40回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第39回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第38回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第37回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第35回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- ハウジングデコレーションコンテスト
- 第34回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第33回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LAS VEGAS (2016)
- 髙井浩の○○チャレンジ!応援企画
- 第31回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 紅蓮祭スクリーンショットコンテスト 2016
- 第30回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第28回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- サントラ発売記念!奏天のイシュガルドコンテスト
- 第27回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 星芒祭 4コマスクリーンショットコンテスト
- 第26回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第25回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- パンプキンクッキーコンテスト
- 髪型デザインコンテスト
- 第24回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第23回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第22回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エオルゼア百景 in 装備コーディネートコンテスト
- 第21回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 思い出スクリーンショットコンテスト
- フリーカンパニーPRキャンペーン
- 第20回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- FFXIVプロデューサーレターLIVE特別編
- ヴァレンティオンデーチョコレートコンテスト
- 闘会議2015 予想イベント
- 降神祭スクリーンショットコンテスト
- 星芒祭スクリーンショットコンテスト
- 第19回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第18回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LAS VEGAS
- 新生FFXIV キャプションコンテスト
- 紅蓮祭スクリーンショットコンテスト
- 第17回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 新生FFXIV 1周年記念PVコンテスト
- ミラプリ スクリーンショットコンテスト
- 第16回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第15回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第14回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エッグハントスクリーンショットコンテスト
- 出張プロデューサーレターLIVE
- 第13回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- プリンセスデースクリーンショットコンテスト
- 第12回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 降神祭スクリーンショットコンテスト
- 星芒祭スクリーンショットコンテスト
- ヴァレンティオンデースクリーンショットコンテスト
- フリーカンパニー紹介PVコンテスト
- 第11回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第10回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 守護天節スクリーンショットコンテスト
- 第9回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張プロデューサーレターLIVE in 幕張
- English Forums
- Information
- Technical Support
- Bug Reports
- Letters from the Producer
- Gameplay
- Classes & Jobs
- Feedback
- Community
- General Discussion
- Worlds(Group JP)
- Worlds(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- New Player Help
- Community Events
- Current Events
- Past Events
- Contests and Sweepstakes
- Fan Festival 2023 in London
- 10th Anniversary Mosaic Art Sweepstakes (NA/EU)
- Fan Festival 2023 in Las Vegas
- Ask Your Questions for the PAX East 2023 Q&A
- Crystalline Conflict Community Cup (North America)
- Letter from the Producer LIVE Part LXVIII
- Letter from the Producer LIVE Part LXV
- Letter from the Producer LIVE Part LXIV
- Letter from the Producer LIVE Part LX
- Everything’s on the Line! Screenshot Contest (NA)
- Ask Yusuke Mogi Your Questions for the PAX East 2020 Panel
- “A Star Light Party” Screenshot Contest (EU/PAL)
- Star Companion Screenshot Sweepstakes (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part LVI
- “This is All Saints’ Wake” Screenshot Contest (EU/PAL)
- A Glamourous Guise Screenshot Contest (NA)
- Memoirs of Adventure Creative Writing Contest (NA)
- Ask Yoshi-P and Banri Oda Your Questions for the gamescom 2019 Q&A
- Letter from the Producer LIVE Part LIII
- Cosplay Contest at gamescom 2019 (EU)
- Become the Darkness Screenshot Sweepstakes! (NA)
- From Light to Darkness Screenshot Contest (EU/PAL)
- Frights and Delights Comic Contest (EU/PAL)
- Cosplay Contest at Japan Expo 2019 (EU)
- Ogre Pumpkin Carve Off Contest: The REDUX (NA)
- My new Viera and Hrothgar" Twitter Screenshot Contest (NA/EU)
- ”Sea Breeze Celebration” Screenshot Contest (NA)
- An Egg-Squisite Season Screenshot Contest (EU/PAL)
- The Eorzean Interior Design Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XLIX
- Letter from the Producer LIVE Part L
- FLOWERS FOR ALL SCREENSHOT CONTEST
- The Eorzean Interior Design Contest (EU)
- Highlights of the Year Contest (EU)
- Fan Festival 2018 in Las Vegas (NA)
- Starlight Scenarios Comic Contest (NA)
- Fan Festival 2019 in Paris (EU)
- The "As Good As Gold" Screenshot Contest (NA)
- Glamour Extravaganza Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE: E3 2018 Edition
- Letter from the Producer LIVE Part XLIV
- Letter from the Producer LIVE Part XLIII
- The "Be My Valentione!" Creative Writing Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XLII
- Letter from the Producer LIVE Part XLI
- Holiday Greetings Contest (EU)
- Starlight Starbright Screenshot Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XL
- Ogre Pumpkin Carve Off Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIX
- Letter from the Producer LIVE Part XXXVIII
- PAX West 2017 (NA)
- Sightseeing Screenshot Contest! (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXVII
- And… Action! (NA)
- The Heavensdub Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXV
- House Party Screenshot Contest (EU)
- Bright-Eyed Superstars Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE in Frankfurt (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIV
- Starlight Celebration Haiku Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIII
- The “Eorzean Home Makeover (Extreme)” Contest (NA)
- Fan Festival 2017 (EU)
- Spooky Story Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE in Las Vegas (2016)
- The Rising Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXI
- "Do You Even /Pose?" Showdown! (NA)
- Fan Festival 2016 (NA)
- Dream Holiday Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE: E3 2016 Edition
- Heavensward Primal Haiku Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXX
- Letter from the Producer LIVE Part XXIX
- Letter from the Producer LIVE Part XXVIII
- Heavensward Music Contest (NA)
- Heavensward Music Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXVII
- Starlight Celebration Comic Strip Contest (NA)
- Starlight Celebration Comic Strip Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXVI
- Airship Components: Research and Development (NA)
- All Saints’ Wake Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXV
- Retainer Ad-Venture Contest (EU)
- Cartographers and Seekers Contest (NA)
- Hairstyle Design Contest
- Letter from the Producer LIVE Part XXIV
- Letter from the Producer LIVE Part XXIII
- Letter from the Producer LIVE Part XXII
- Letter from the Producer LIVE Part XXI
- Memories of Eorzea Screenshot Contest (NA)
- Memories of Eorzea Screenshot Contest (EU)
- Heavensward Free Company Recruitment Contest (NA)
- Heavensward Free Company Recruitment Contest (EU)
- A Realm Redubbed Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XX
- Letter from the Producer LIVE – Special Edition
- The Great Eorzean Cook-Off Contest (EU)
- Be My Valentione Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (EU)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (NA)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XIX
- Letter from the Producer LIVE Part XVIII
- Letter from the Producer LIVE in Las Vegas
- Grant a Wish Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XVII
- Moonfire Faire Screenshot Contest (NA)
- Moonfire Faire Screenshot Contest (EU)
- Fan Festival 2014 (NA)
- Fan Festival 2014 (EU)
- FFXIV: ARR One Year Anniversary Video Contest (NA)
- FFXIV: ARR One Year Anniversary Video Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XVI
- Eorzea IRL Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE: E3 Edition
- Letter from the Producer LIVE Part XV
- Letter from the Producer LIVE Part XIV
- Hatching-tide Screenshot Contest (NA)
- Hatching-tide Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XIII
- Little Ladies' Day Screenshot Contest (NA)
- Little Ladies' Day Screenshot Contest (EU)
- Valentione's Day Screenshot Contest (NA)
- Valentione's Day Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XII
- Heavensturn Screenshot Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (EU)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (NA)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (EU)
- FFXIV: ARR Free Company Recruitment Contest (NA)
- FFXIV: ARR Free Company Recruitment Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XI
- XIII Days – Your Fate is Sealed Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part X
- Doppelganger Screenshot Contest (NA)
- All Saints’ Wake Haiku Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part IX
- Ask Your Questions for the Mini Letter from the Producer LIVE at TGS!
- Sightseeing Screenshot Sweepstakes (NA/EU)
- Forums français
- Informations
- Assistance technique
- Rapports de problèmes
- La lettre du producteur
- Système de jeu
- Classes & Jobs
- Avis et retours sur les sites et l’appli
- Discussion
- Discussion générale
- Mondes (Japon)
- Mondes (Amérique du N./Europe/Océanie)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- Aide aux nouveaux joueurs
- Événements communautaires
- Evénements en cours
- Evénements passés
- Concours et tirages au sort
- Fan Festival 2023 de Londres
- Concours pour la mosaïque du 10e anniversaire
- « La lettre du producteur LIVE » : 68e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 65e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 64e émission
- Concours de captures d’écran d'exploration - Édition 2020
- « La lettre du producteur LIVE » : 60e émission
- Concours de captures d’écran - Une petite fête des étoiles entre amis
- « La lettre du producteur LIVE » : 56e émission
- Concours de captures d’écran – C’est ça la Veillée des Saints
- Mes questions à Yoshi-P et Banri Oda pour le Q&R de gamescom 2019 !
- « La lettre du producteur LIVE » : 53e émission
- Concours de cosplay à la gamescom 2019
- Concours de captures d’écran : De la Lumière aux Ténèbres
- Concours Pistolame à Japan Expo 2019 !
- Concours de Cosplay à Japan Expo 2019
- « Ma Viéra & mon Hrothgar » - Concours Twitter de capture d'écran
- Fabulœuf concours de captures d’écran
- « La lettre du producteur LIVE » : 50e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 49e émission
- Concours des meilleurs moments de l'année 2018
- Concours de BD’pouvante
- Concours de décoration d’intérieur
- Fan Festival 2019 à Paris
- Concours “Les dieux de la mode”
- « La lettre du producteur LIVE » : 44e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 43e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 42e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 41e émission
- Concours de cartes de vœux
- « La lettre du producteur LIVE » : 40e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 39e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 38e émission
- Concours de captures d’écran d’exploration
- « La lettre du producteur LIVE » : 37e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 35e émission
- Concours de captures d’écran spécial « House Party »
- Lettre du producteur LIVE à Francfort
- « La lettre du producteur LIVE » : 34e émission
- Concours de haïkus pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : 33e émission
- Concours d’histoires effrayantes
- Posez vos questions pour la lettre Live à Las Vegas (2016)
- Concours de captures d’écran pour la fête de la Commémoration
- « La lettre du producteur LIVE » : 31e émission
- Concours office de tourisme d’Éorzéa
- « La lettre du producteur LIVE » : 30e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 29e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 28e émission
- Concours de musique d’Heavensward
- « La lettre du producteur LIVE » : 27e émission
- Concours de comic strip pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : 26e émission
- Concours de captures d’écran pour la Veillée des saints
- « La lettre du producteur LIVE » : 25e émission
- Concours « Les aventures de mon servant »
- Concours de création de coupe de cheveux
- « La lettre du producteur LIVE » : 24e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 22e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 23e émission
- Concours de captures d’écran – Souvenirs d’Éorzéa
- Les compagnies libres recrutent pour Heavensward
- « La lettre du producteur LIVE » : 20e émission
- La lettre du producteur LIVE : émission spéciale
- Le grand concours culinaire d’Éorzéa
- Concours de captures d’écran pour la fête de la transition
- Concours de captures d’écran pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : dix-huitième émission
- Posez vos questions pour la lettre Live à Las Vegas
- Concours « Le jeu des souhaits »
- « La lettre du producteur LIVE » : 19e émission
- Fan Festival 2014
- Concours de captures d’écran pour les feux de la mort
- « La lettre du producteur LIVE » : dix-septième émission
- Concours vidéo pour le premier anniversaire
- « La lettre du producteur LIVE » : seizième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : quinzième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : quatorzième émission
- Concours de captures d’écran pour la chasse aux Prœufs
- « La lettre du producteur LIVE » : treizième émission
- Concours de captures d’écran pour la fête des demoiselles
- « La lettre du producteur LIVE » : douzième émission
- Concours de captures d’écran pour la fête de la transition
- Concours de captures d’écran pour la fête des étoiles
- Concours de captures d’écran pour la Valention
- Les compagnies libres recrutent
- « La lettre du producteur LIVE » : onzième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : dixième émission
- Concours Haiku d'Éorzéa - la Veillée des saints
- « La lettre du producteur LIVE » : neuvième émission
- Posez vos questions pour la lettre Live à Makuhari
- Deutsches Forum
- Ankündigungen
- Technischer Support
- Fehler melden
- Briefe des Produzenten
- Spielsystem
- Charakterklassen & Jobs
- Feedback
- Diskussionen
- Allgemeine Diskussionen
- Welten(Group JP)
- Welten(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- Für Einsteiger
- Community-Veranstaltungen
- Aktuelle Veranstaltungen
- Vergangene Veranstaltungen
- Wettbewerbe und Gewinnspiele
- Mosaik-Gewinnspiel zum 10. Jubiläum
- Fan Festival 2023 in London
- Der 68 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 65 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 64 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Reisetagebuch-Screenshot-Gewinnspiel
- Der 60. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sternenlichtertrupp-Screenshot-Wettbewerb
- Der 56. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Allerschutzheiligen Schauer-Spektakel-Screenshot-Wettbewerbs
- Eure Fragen an Naoki Yoshida und Banri Oda für die Q&A-Session auf der gamescom 2019
- Der 53. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Cosplay-Wettbewerb auf der gamescom 2019
- Vom Licht in die Dunkelheit Screenshot-Wettbewerb
- Cosplay-Wettbewerb auf der Japan Expo 2019
- „Viera & Hrothgar Makeover“ Twitter-Screenshot-Wettbewerb
- Wundereiersuche Screenshot-Wettbewerb
- Der 50. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 49. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Highlights des Jahres Wettbewerb
- Spuk und Schabernack Comic-Wettbewerb
- Inneneinrichtungs-Wettbewerb
- Fan Festival 2019 in Paris
- Extravaganza-Wettbewerb
- Der 44. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 43. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 42. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 41. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Wintergrüße-Wettbewerb
- Der 40. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 39. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 38. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sightseeing-Screenshot-Wettbewerb
- Der 37. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 35. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- House Party! Screenshot-Wettbewerb
- Brief des Produzenten LIVE in Frankfurt
- Der 34. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sternenlichtfest Haiku-Wettbewerb
- Der 33. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Gruselgeschichten-Wettbewerb
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Las Vegas (2016)
- Fest der Wiedergeburt Screenshot-Wettbewerb
- Der 31. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Traumurlaub-Wettbewerb
- Der 30. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 29. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 28. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Heavensward Musik-Wettbewerb
- Der 27. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Sternenlichtfest Comicstrip-Wettbwerb
- Der 26. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Allerschutzheiligen-Fest Screenshot-Wettbewerb
- Der 25. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Die Abenteuer des Tapferen Gehilfen–Wettbewerb
- Frisuren-Design-Wettbewerb
- Der 24. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 22. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 23. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Erinnerungen an Eorzea Screenshot-Wettbewerb
- Heavensward-Rekrutierungswettbewerb der freien Gesellschaften
- Der 20. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Brief des Produzenten – LIVE-Sondersendung!
- Großer, eorzäischer Kochwettbewerb
- Himmelswende Screenshot Wettbewerb
- Sternenlichtfest Screenshot-Wettbewerb
- Der 18. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Las Vegas
- Wünsche werden wahr- Wettbewerb
- Der 19. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Fan Festival 2014
- Feuermond-Reigen Screenshot-Wettbewerb
- Der 17. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Video-Wettbewerb zum einjährigen Jubiläum
- Der 16. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 15. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 14. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Wundereiersuche Screenshot-Wettbewerb
- Der 13. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Prinzessinnenfest Screenshot-Wettbewerb
- Valentiontag Screenshot Wettbewerb
- Der 12. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Himmelswende Screenshot Wettbewerb
- Sternenlichtfest Screenshot Wettbewerb
- Rekrutierungsvideo-Wettbewerb der Freien Gesellschaften
- Der 11. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 10. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Allerschutzheiligen-Haiku-Wettbewerb
- Der 9. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Makuhari!
- Version 1.0 Forum Archive
- Japanese Forums
- インフォメーション
- サポート
- アップデート
- ゲームシステム
- クラス&ジョブ
- ウェブサイトフィードバック
- 雑談
- 初心者用
- 写真館
- コミュニティイベント
- 開催中
- 終了
- ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア キャッチフレーズコンテスト
- 第8回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LA
- 第7回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第6回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 創作タマゴコンテスト
- 第5回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- マイ ベスト チョコボ
- ダラガブを探せ!
- エオルゼア メモリーズ
- 第4回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エオルゼア de 五・七・五
- 第3回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 残暑見舞いコンテスト
- Hidden Artifacts ~新生コンセプトアートクイズ~
- ガルーダトライアル
- 宿屋deつぶやき!イベント (JP)
- LSリクルートポスターコンテスト (JP)
- English Forums
- Information
- Support
- Updates
- Gameplay
- Classes & Jobs
- Feedback
- Community
- New Player Help
- In-Game Media
- Community Events
- Current Events
- Past Events
- Letter from the Producer LIVE Part VIII
- Letter from the Producer LIVE Part VII
- Letter from the Producer LIVE Part VI
- Eorzean Egg Decoration Contest
- Letter from the Producer LIVE Part V
- Eorzea Haiku Contest (EU)
- “Chocobos Rule the World” Contest!
- Memories of Eorzea Contest
- Letter from the Producer LIVE Part IV
- What if Dalamud Contest (EU)
- Tales from Eorzea (NA)
- Culinary Creation Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part III
- We Dub to Make it Ours (NA)
- These Grand Company Colors Don't Run!
- Hidden Artifacts
- Grant A Wish Contest (EU)
- Garuda—She's Like the Wind
- Culinary Creation Contest (NA)
- Valentione’s Dialogue Contest (EU)
- Valentione’s Day Love Letter Contest (NA)
- Forums français
- Informations
- Assistance sur le jeu
- Développement
- Système de jeu
- Classes & Jobs
- Avis et retours
- Discussion
- Aide aux nouveaux joueurs
- Galerie multimédia & articles
- Evénements organisés par l'équipe communautaire
- Evénements en cours
- Evénements passés
- « La lettre du producteur LIVE » : huitième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : septième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : sixième émission
- Concours : « Décoration d’Œufs Éorzéens »
- « La lettre du producteur LIVE » : cinquième émission
- Concours « Haïkus d’Eorzéa »
- Concours « Les Chocobos à la Conquête du Monde » !
- Concours « Souvenirs d’Eorzéa »
- « La lettre du producteur LIVE » : quatrième émission
- Concours : « Et si Dalamud était... »
- Concours de création culinaire
- « La lettre du producteur LIVE » : troisième émission
- Soutenons les grandes compagnies !
- Questions pour un Eorzéen
- Concours du jeu des souhaits
- L’épreuve de Garuda
- Concours de dialogue de la Valention
- Deutsches Forum
- Ankündigungen
- Support
- Update
- Spielsystem
- Charakterklassen & Jobs
- Feedback
- Diskussionen
- Für Einsteiger
- Medien
- Community-Veranstaltungen
- Aktuelle Veranstaltungen
- Vergangene Veranstaltungen
- Der 8. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 7. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 6. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Eorzäischer Ei-Dekorations-Wettbewerb
- Der 5. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Eorzea-Haiku-Wettbewerb
- Chocobos, die Herrscher der Welt
- Erinnerungen an Eorzea
- Der 4. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Was, wenn Dalamud … wäre?
- Kulinarische Kreationen
- Der 3. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Farben, die nicht die Segel streichen!
- Verborgene ARTefakte
- Wünsche werden wahr-Wettbewerb
- Garuda – Grausame Herrin der Stürme
- Valentione Dialog-Wettbewerb
- Japanese Forums
«
Previous Thread
|
Next Thread
»

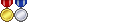

 Reply With Quote
Reply With Quote