- Forum Top
- Japanese Forums
- ゲームシステム
- ハウジング
- ハウスフレンドさんに譲渡システム
Thread: ハウスフレンドさんに譲渡システム
-
03-01-2022 12:01 PM #21Player

- Join Date
- May 2012
- Posts
- 1,015
- Character
- Kamo'ne Nabetsukami
- World
- Pandaemonium
- Main Class
- Black Mage Lv 100
(11)
-
03-02-2022 07:22 AM #22
おはようございます。
え~と、スレ主さんとKamoneさんのご意見は一理あるとは思いますが、ちょっと前提が違っていると思いました。
他のハウジングスレでも言われてますが、土地を購入するギルは【土地を所有する権利】ではなくて、その【土地を使用する権利】ではないかと。
つまり所有者はあくまでもGC、クガネ、こんどの新エリアはイシュガルドということになります。
ましてや、1アカウント1キャラ(1ワールド)に1か所の土地の仕様上、恐らく複数の土地を持つキャラは転居や新エリアの購入が出来ないはず……新しい1つ以外が放棄されるはず(たぶん)
そしてシステム上ソースの公平さから時間撤去を定めていることに、譲渡することで抜け道を作る要望になってしまうのでは…?
ハウスキーパー的なことをお願いすることはプレイヤー同士で構いませんが、その方が土地を持つ権利と機会をフレンドの都合で無くしてしまうということにもなります。
プレイヤー同士の公平性等を考慮するなら、特定のプレイヤーに譲渡するので無く、一度GC等に返還してください、ということになるのではないでしょうか?
その反面で、確かに世界遺産的なハウジング内装もあり、それを世界(サーバー)的に保護したい! というものありますし、ハウジングのプロ的な方がプロデュースした新築物件を購入してみたい!という要望もあるかもしれません。
そんな訳で個人的には、課金によるサービスの提供ということにしました。(3)Last edited by Arth; 03-02-2022 at 12:35 PM. Reason: 「返還」を「変換」に変換間違い…すまん><
-
03-02-2022 11:28 AM #23Player

- Join Date
- May 2012
- Posts
- 1,015
- Character
- Kamo'ne Nabetsukami
- World
- Pandaemonium
- Main Class
- Black Mage Lv 100
なるほど。所有ではなく使用する権利という点については一理あると思います。
ただ譲渡は譲渡ですので、自分の土地を使用する権利を放棄して他の方に譲るのでその点は何も違いが無いと思いますがどうでしょう。
これについても友人間で合意の上で行われる譲渡であれば、特に機会損失などを気にする事もないと思われます。
公平性と言う面においては、別にオンラインゲーム上でプレイヤー同士のやり取りによって土地を得る事にはなんら不公平は無いと私は思っています。
とはいえこういった問答を続けていても前に進まないので、Arthさんの課金サービス案に意見に乗るかたちで私からも提案させて下さい。
もし譲渡システムを仮に実装するのであればこれくらいは必要かなという目安です。
1)「譲渡する側」が課金サービスである「ハウジング譲渡権※」を購入する
2)「譲渡する側」が「譲渡される側」に対して申請を行う
3)「譲渡される側」が認証を行う
4)40日間の譲渡準備期間が発生する、この間両者の継続課金サービスが有効で有ることを条件とする、また期間中は家具や庭具の設置・移動・撤去が不可能となる
5)譲渡準備期間が40日経過すると譲渡完了、そこから40日間の譲渡禁止期間が発生する
※ハウジング譲渡権の購入及び、譲渡される側にはビギナーでない事を条件とする等、厳しい条件を設ける必要があると思います。(3)
-
03-02-2022 02:57 PM #24Player
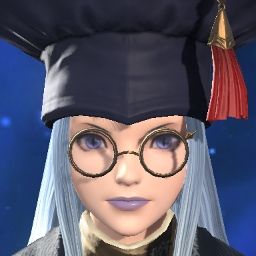
- Join Date
- Jun 2020
- Location
- イシュガルド
- Posts
- 1,154
- Character
- Zio Te
- World
- Gungnir
- Main Class
- Arcanist Lv 53
使用権って事は土地を借りているってことですよね。譲渡という発想がおかしいのだと思います。
たぶん各個人的にあるのはハウス所有権なんですよね。その為の土地の使用権を購入が出来る。
ハウスを手放す=土地使用権の放棄ですから放棄後の運用先や運用方法には口出せないですよね。
なので今回の目的でいえば家主のハウス所有権以外に自由な使用の対価はないのだと思います。
そういう時に使うのがハウスシェアリングなんでしょうし、権利内で出来る家主の自由の範疇だと思います。(1)
-
03-02-2022 03:18 PM #25Player

- Join Date
- May 2012
- Posts
- 1,015
- Character
- Kamo'ne Nabetsukami
- World
- Pandaemonium
- Main Class
- Black Mage Lv 100
なるほど、では土地は元のプレイヤーに帰属したままハウスの所有権を他の方に移し、
40日間の経過をもって放棄された土地の上に立っているハウスの所有者に土地の権利を移動させると考えるのはどうでしょう。
システム的にはこんな感じでしょうか。
1)「土地・ハウス所有者」が「ハウス」の所有権を「フレンド」に譲渡する
2)「土地所有者」はハウスの所有権を持たない為ハウス及び土地の維持が不能となる
3)40日の経過をもってハウス及び土地の放棄判定がされる
4)ハウスの所有権を持っているフレンドは一定期間の間に元の土地の代金を支払う(支払わなければ期間超過で更地となる)
5)土地の代金を支払えばそのまま土地・ハウスを維持し所有することが出来る
40日経過後に土地の代金を払わなければ強制立ち退きさせられるという感じですかね。(0)
-
03-02-2022 04:17 PM #26Player
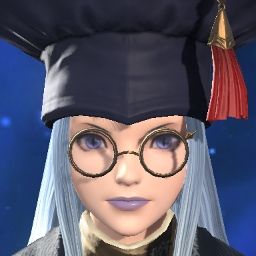
- Join Date
- Jun 2020
- Location
- イシュガルド
- Posts
- 1,154
- Character
- Zio Te
- World
- Gungnir
- Main Class
- Arcanist Lv 53
読みましたけどユーザー間の個人取引がそもそも難しいのだと思います。
あとフレンドって別に特別な関係ではないですよね。申請許可でなれる機能なので。
当事者同士の関係性はフレンドの呼称では測れないですし。
本当に親しい人にハウス渡せたらと思いますしそういう方いますけど、その方とはハウスシェアで自由に使ってもらってます。
私のハウス所有権を対価に親しい人にハウジング楽しんでもらっているという形です。
心情は別としてどう考えても個人取引認めることは業者、プレイヤー問わず土地商売を公認したことになるのではないかと。
特に業者の場合アカウントを捨てるのもおそらく容易なので日数による制約も効果は薄いですし。
ちなみにFCハウスは所有権を渡せますけど、それも個人的には所有者が放棄したら消失でいいいう考えです。今回関係ないのでFCハウスはどうでも良いですが。(5)
-
03-02-2022 04:28 PM #27
土地の所有権とか使用権とかそこまで難しく考えなくてもいいと思いますけどね。
根本には土地総量の不足があるのは否めないのですが、ハウジングというコンテンツに積極的なプレイヤーに
土地・家を回していくと考えたときに、仲の良いフレンドなら譲渡しても良いって人に対して後押し出来る仕組みと考えるのは
とても有用と思います。
複数家を所持して持て余している人に対しても穏当に権利を譲れる手段があれば、欲しい人に家が回る手段にはなるかと。
この仕組が、RMT業者の隠れ蓑や1人でより多くの家を収集する手段となってはならないでしょうけど、利益考えたらマイナスになるけど、
それこそ採算度外視でのプレイヤー間譲渡についてはもう少しサポートしてもいいのかなとは思います。(4)
-
03-02-2022 05:03 PM #28Player

- Join Date
- Nov 2019
- Location
- ウルダハ
- Posts
- 942
- Character
- Ribel Zibel
- World
- Spriggan
- Main Class
- Summoner Lv 50
仮に譲渡機能が実装されたとして、業者を抜きに考えて
・複数垢で抽選に応募し、当選したらメイン垢へ譲渡
・長期休止期間フレンドへの譲渡でハウス保持
・フレンドにプールする為にハウスの確保(抽選に参加)
が出来てしまうわけで、正規の手段でハウスが欲しいと思ってる新参プレイヤーには余計ハウスが回らなくなるのでは?(2)
-
03-02-2022 05:08 PM #29Player
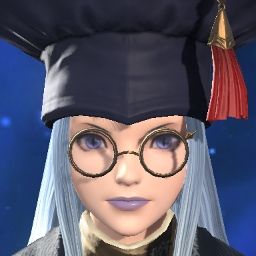
- Join Date
- Jun 2020
- Location
- イシュガルド
- Posts
- 1,154
- Character
- Zio Te
- World
- Gungnir
- Main Class
- Arcanist Lv 53
そうですね。仰る根本の土地総数が増えて行けば買えるくらいになれば何でも出来るようにはなると思います。
今だから難しいところ思うだけで......。(2)
-
03-02-2022 05:27 PM #30Player

- Join Date
- May 2012
- Posts
- 1,015
- Character
- Kamo'ne Nabetsukami
- World
- Pandaemonium
- Main Class
- Black Mage Lv 100
FF14では特に複数アカウントの所持は禁止されておりませんし、
それだけ信頼のおけるフレンドがいる環境を作るというのもハウジングをプレイする上での一つの努力だと思っているので別に良いかなとは思っています。
譲渡と言うシステムがハウジングを手に入れる一つの手段となるのはプレイヤー同士のコミュニケーションあってこそだと思うので、
そこに(規約違反絡みの)トラブルが発生しやすい状況が無い限りはアリだと思っているスタンスです。
もちろん皆さんが仰るように現状難しいと言うのは承知しています。
今後ハウジングエリアが拡大されてどうなっていくかも分からない状態ではありますが、
土地が足りていない今だからこそ出せる意見・要望というのもあると思うので譲渡システム自体には賛同しています。(2)
Quick Navigation
ハウジング
Top
- Forums
- Japanese Forums
- ニュース
- テクニカルサポート
- 不具合報告
- プロデューサーレター
- ゲームシステム
- クラス&ジョブ
- ウェブサイト/アプリフィードバック
- 雑談
- この装備を武具投影したい!!
- あのジョブのUIレイアウトが知りたい!
- ジェネラルディスカッション
- ワールド(Group JP)
- ワールド(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- 初心者用
- コミュニティイベント
- 開催中
- 終了
- 第8回14時間生放送
- 第68回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第65回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第64回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第60回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第56回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第53回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張!ひろしチャレンジ 応援プレゼント企画
- 第50回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第49回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- ハウジングコーディネートコンテスト
- 第44回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第43回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第42回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第41回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第40回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第39回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第38回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第37回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第35回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- ハウジングデコレーションコンテスト
- 第34回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第33回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LAS VEGAS (2016)
- 髙井浩の○○チャレンジ!応援企画
- 第31回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 紅蓮祭スクリーンショットコンテスト 2016
- 第30回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第28回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- サントラ発売記念!奏天のイシュガルドコンテスト
- 第27回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 星芒祭 4コマスクリーンショットコンテスト
- 第26回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第25回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- パンプキンクッキーコンテスト
- 髪型デザインコンテスト
- 第24回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第23回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第22回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エオルゼア百景 in 装備コーディネートコンテスト
- 第21回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 思い出スクリーンショットコンテスト
- フリーカンパニーPRキャンペーン
- 第20回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- FFXIVプロデューサーレターLIVE特別編
- ヴァレンティオンデーチョコレートコンテスト
- 闘会議2015 予想イベント
- 降神祭スクリーンショットコンテスト
- 星芒祭スクリーンショットコンテスト
- 第19回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第18回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LAS VEGAS
- 新生FFXIV キャプションコンテスト
- 紅蓮祭スクリーンショットコンテスト
- 第17回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 新生FFXIV 1周年記念PVコンテスト
- ミラプリ スクリーンショットコンテスト
- 第16回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第15回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第14回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エッグハントスクリーンショットコンテスト
- 出張プロデューサーレターLIVE
- 第13回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- プリンセスデースクリーンショットコンテスト
- 第12回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 降神祭スクリーンショットコンテスト
- 星芒祭スクリーンショットコンテスト
- ヴァレンティオンデースクリーンショットコンテスト
- フリーカンパニー紹介PVコンテスト
- 第11回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第10回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 守護天節スクリーンショットコンテスト
- 第9回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張プロデューサーレターLIVE in 幕張
- English Forums
- Information
- Technical Support
- Bug Reports
- Letters from the Producer
- Gameplay
- Classes & Jobs
- Feedback
- Community
- General Discussion
- Worlds(Group JP)
- Worlds(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- New Player Help
- Community Events
- Current Events
- Past Events
- Contests and Sweepstakes
- Fan Festival 2023 in London
- 10th Anniversary Mosaic Art Sweepstakes (NA/EU)
- Fan Festival 2023 in Las Vegas
- Ask Your Questions for the PAX East 2023 Q&A
- Crystalline Conflict Community Cup (North America)
- Letter from the Producer LIVE Part LXVIII
- Letter from the Producer LIVE Part LXV
- Letter from the Producer LIVE Part LXIV
- Letter from the Producer LIVE Part LX
- Everything’s on the Line! Screenshot Contest (NA)
- Ask Yusuke Mogi Your Questions for the PAX East 2020 Panel
- “A Star Light Party” Screenshot Contest (EU/PAL)
- Star Companion Screenshot Sweepstakes (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part LVI
- “This is All Saints’ Wake” Screenshot Contest (EU/PAL)
- A Glamourous Guise Screenshot Contest (NA)
- Memoirs of Adventure Creative Writing Contest (NA)
- Ask Yoshi-P and Banri Oda Your Questions for the gamescom 2019 Q&A
- Letter from the Producer LIVE Part LIII
- Cosplay Contest at gamescom 2019 (EU)
- Become the Darkness Screenshot Sweepstakes! (NA)
- From Light to Darkness Screenshot Contest (EU/PAL)
- Frights and Delights Comic Contest (EU/PAL)
- Cosplay Contest at Japan Expo 2019 (EU)
- Ogre Pumpkin Carve Off Contest: The REDUX (NA)
- My new Viera and Hrothgar" Twitter Screenshot Contest (NA/EU)
- ”Sea Breeze Celebration” Screenshot Contest (NA)
- An Egg-Squisite Season Screenshot Contest (EU/PAL)
- The Eorzean Interior Design Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XLIX
- Letter from the Producer LIVE Part L
- FLOWERS FOR ALL SCREENSHOT CONTEST
- The Eorzean Interior Design Contest (EU)
- Highlights of the Year Contest (EU)
- Fan Festival 2018 in Las Vegas (NA)
- Starlight Scenarios Comic Contest (NA)
- Fan Festival 2019 in Paris (EU)
- The "As Good As Gold" Screenshot Contest (NA)
- Glamour Extravaganza Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE: E3 2018 Edition
- Letter from the Producer LIVE Part XLIV
- Letter from the Producer LIVE Part XLIII
- The "Be My Valentione!" Creative Writing Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XLII
- Letter from the Producer LIVE Part XLI
- Holiday Greetings Contest (EU)
- Starlight Starbright Screenshot Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XL
- Ogre Pumpkin Carve Off Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIX
- Letter from the Producer LIVE Part XXXVIII
- PAX West 2017 (NA)
- Sightseeing Screenshot Contest! (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXVII
- And… Action! (NA)
- The Heavensdub Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXV
- House Party Screenshot Contest (EU)
- Bright-Eyed Superstars Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE in Frankfurt (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIV
- Starlight Celebration Haiku Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIII
- The “Eorzean Home Makeover (Extreme)” Contest (NA)
- Fan Festival 2017 (EU)
- Spooky Story Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE in Las Vegas (2016)
- The Rising Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXI
- "Do You Even /Pose?" Showdown! (NA)
- Fan Festival 2016 (NA)
- Dream Holiday Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE: E3 2016 Edition
- Heavensward Primal Haiku Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXX
- Letter from the Producer LIVE Part XXIX
- Letter from the Producer LIVE Part XXVIII
- Heavensward Music Contest (NA)
- Heavensward Music Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXVII
- Starlight Celebration Comic Strip Contest (NA)
- Starlight Celebration Comic Strip Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXVI
- Airship Components: Research and Development (NA)
- All Saints’ Wake Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXV
- Retainer Ad-Venture Contest (EU)
- Cartographers and Seekers Contest (NA)
- Hairstyle Design Contest
- Letter from the Producer LIVE Part XXIV
- Letter from the Producer LIVE Part XXIII
- Letter from the Producer LIVE Part XXII
- Letter from the Producer LIVE Part XXI
- Memories of Eorzea Screenshot Contest (NA)
- Memories of Eorzea Screenshot Contest (EU)
- Heavensward Free Company Recruitment Contest (NA)
- Heavensward Free Company Recruitment Contest (EU)
- A Realm Redubbed Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XX
- Letter from the Producer LIVE – Special Edition
- The Great Eorzean Cook-Off Contest (EU)
- Be My Valentione Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (EU)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (NA)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XIX
- Letter from the Producer LIVE Part XVIII
- Letter from the Producer LIVE in Las Vegas
- Grant a Wish Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XVII
- Moonfire Faire Screenshot Contest (NA)
- Moonfire Faire Screenshot Contest (EU)
- Fan Festival 2014 (NA)
- Fan Festival 2014 (EU)
- FFXIV: ARR One Year Anniversary Video Contest (NA)
- FFXIV: ARR One Year Anniversary Video Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XVI
- Eorzea IRL Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE: E3 Edition
- Letter from the Producer LIVE Part XV
- Letter from the Producer LIVE Part XIV
- Hatching-tide Screenshot Contest (NA)
- Hatching-tide Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XIII
- Little Ladies' Day Screenshot Contest (NA)
- Little Ladies' Day Screenshot Contest (EU)
- Valentione's Day Screenshot Contest (NA)
- Valentione's Day Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XII
- Heavensturn Screenshot Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (EU)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (NA)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (EU)
- FFXIV: ARR Free Company Recruitment Contest (NA)
- FFXIV: ARR Free Company Recruitment Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XI
- XIII Days – Your Fate is Sealed Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part X
- Doppelganger Screenshot Contest (NA)
- All Saints’ Wake Haiku Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part IX
- Ask Your Questions for the Mini Letter from the Producer LIVE at TGS!
- Sightseeing Screenshot Sweepstakes (NA/EU)
- Forums français
- Informations
- Assistance technique
- Rapports de problèmes
- La lettre du producteur
- Système de jeu
- Classes & Jobs
- Avis et retours sur les sites et l’appli
- Discussion
- Discussion générale
- Mondes (Japon)
- Mondes (Amérique du N./Europe/Océanie)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- Aide aux nouveaux joueurs
- Événements communautaires
- Evénements en cours
- Evénements passés
- Concours et tirages au sort
- Fan Festival 2023 de Londres
- Concours pour la mosaïque du 10e anniversaire
- « La lettre du producteur LIVE » : 68e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 65e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 64e émission
- Concours de captures d’écran d'exploration - Édition 2020
- « La lettre du producteur LIVE » : 60e émission
- Concours de captures d’écran - Une petite fête des étoiles entre amis
- « La lettre du producteur LIVE » : 56e émission
- Concours de captures d’écran – C’est ça la Veillée des Saints
- Mes questions à Yoshi-P et Banri Oda pour le Q&R de gamescom 2019 !
- « La lettre du producteur LIVE » : 53e émission
- Concours de cosplay à la gamescom 2019
- Concours de captures d’écran : De la Lumière aux Ténèbres
- Concours Pistolame à Japan Expo 2019 !
- Concours de Cosplay à Japan Expo 2019
- « Ma Viéra & mon Hrothgar » - Concours Twitter de capture d'écran
- Fabulœuf concours de captures d’écran
- « La lettre du producteur LIVE » : 50e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 49e émission
- Concours des meilleurs moments de l'année 2018
- Concours de BD’pouvante
- Concours de décoration d’intérieur
- Fan Festival 2019 à Paris
- Concours “Les dieux de la mode”
- « La lettre du producteur LIVE » : 44e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 43e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 42e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 41e émission
- Concours de cartes de vœux
- « La lettre du producteur LIVE » : 40e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 39e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 38e émission
- Concours de captures d’écran d’exploration
- « La lettre du producteur LIVE » : 37e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 35e émission
- Concours de captures d’écran spécial « House Party »
- Lettre du producteur LIVE à Francfort
- « La lettre du producteur LIVE » : 34e émission
- Concours de haïkus pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : 33e émission
- Concours d’histoires effrayantes
- Posez vos questions pour la lettre Live à Las Vegas (2016)
- Concours de captures d’écran pour la fête de la Commémoration
- « La lettre du producteur LIVE » : 31e émission
- Concours office de tourisme d’Éorzéa
- « La lettre du producteur LIVE » : 30e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 29e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 28e émission
- Concours de musique d’Heavensward
- « La lettre du producteur LIVE » : 27e émission
- Concours de comic strip pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : 26e émission
- Concours de captures d’écran pour la Veillée des saints
- « La lettre du producteur LIVE » : 25e émission
- Concours « Les aventures de mon servant »
- Concours de création de coupe de cheveux
- « La lettre du producteur LIVE » : 24e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 22e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 23e émission
- Concours de captures d’écran – Souvenirs d’Éorzéa
- Les compagnies libres recrutent pour Heavensward
- « La lettre du producteur LIVE » : 20e émission
- La lettre du producteur LIVE : émission spéciale
- Le grand concours culinaire d’Éorzéa
- Concours de captures d’écran pour la fête de la transition
- Concours de captures d’écran pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : dix-huitième émission
- Posez vos questions pour la lettre Live à Las Vegas
- Concours « Le jeu des souhaits »
- « La lettre du producteur LIVE » : 19e émission
- Fan Festival 2014
- Concours de captures d’écran pour les feux de la mort
- « La lettre du producteur LIVE » : dix-septième émission
- Concours vidéo pour le premier anniversaire
- « La lettre du producteur LIVE » : seizième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : quinzième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : quatorzième émission
- Concours de captures d’écran pour la chasse aux Prœufs
- « La lettre du producteur LIVE » : treizième émission
- Concours de captures d’écran pour la fête des demoiselles
- « La lettre du producteur LIVE » : douzième émission
- Concours de captures d’écran pour la fête de la transition
- Concours de captures d’écran pour la fête des étoiles
- Concours de captures d’écran pour la Valention
- Les compagnies libres recrutent
- « La lettre du producteur LIVE » : onzième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : dixième émission
- Concours Haiku d'Éorzéa - la Veillée des saints
- « La lettre du producteur LIVE » : neuvième émission
- Posez vos questions pour la lettre Live à Makuhari
- Deutsches Forum
- Ankündigungen
- Technischer Support
- Fehler melden
- Briefe des Produzenten
- Spielsystem
- Charakterklassen & Jobs
- Feedback
- Diskussionen
- Allgemeine Diskussionen
- Welten(Group JP)
- Welten(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- Für Einsteiger
- Community-Veranstaltungen
- Aktuelle Veranstaltungen
- Vergangene Veranstaltungen
- Wettbewerbe und Gewinnspiele
- Mosaik-Gewinnspiel zum 10. Jubiläum
- Fan Festival 2023 in London
- Der 68 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 65 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 64 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Reisetagebuch-Screenshot-Gewinnspiel
- Der 60. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sternenlichtertrupp-Screenshot-Wettbewerb
- Der 56. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Allerschutzheiligen Schauer-Spektakel-Screenshot-Wettbewerbs
- Eure Fragen an Naoki Yoshida und Banri Oda für die Q&A-Session auf der gamescom 2019
- Der 53. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Cosplay-Wettbewerb auf der gamescom 2019
- Vom Licht in die Dunkelheit Screenshot-Wettbewerb
- Cosplay-Wettbewerb auf der Japan Expo 2019
- „Viera & Hrothgar Makeover“ Twitter-Screenshot-Wettbewerb
- Wundereiersuche Screenshot-Wettbewerb
- Der 50. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 49. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Highlights des Jahres Wettbewerb
- Spuk und Schabernack Comic-Wettbewerb
- Inneneinrichtungs-Wettbewerb
- Fan Festival 2019 in Paris
- Extravaganza-Wettbewerb
- Der 44. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 43. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 42. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 41. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Wintergrüße-Wettbewerb
- Der 40. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 39. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 38. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sightseeing-Screenshot-Wettbewerb
- Der 37. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 35. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- House Party! Screenshot-Wettbewerb
- Brief des Produzenten LIVE in Frankfurt
- Der 34. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sternenlichtfest Haiku-Wettbewerb
- Der 33. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Gruselgeschichten-Wettbewerb
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Las Vegas (2016)
- Fest der Wiedergeburt Screenshot-Wettbewerb
- Der 31. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Traumurlaub-Wettbewerb
- Der 30. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 29. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 28. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Heavensward Musik-Wettbewerb
- Der 27. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Sternenlichtfest Comicstrip-Wettbwerb
- Der 26. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Allerschutzheiligen-Fest Screenshot-Wettbewerb
- Der 25. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Die Abenteuer des Tapferen Gehilfen–Wettbewerb
- Frisuren-Design-Wettbewerb
- Der 24. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 22. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 23. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Erinnerungen an Eorzea Screenshot-Wettbewerb
- Heavensward-Rekrutierungswettbewerb der freien Gesellschaften
- Der 20. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Brief des Produzenten – LIVE-Sondersendung!
- Großer, eorzäischer Kochwettbewerb
- Himmelswende Screenshot Wettbewerb
- Sternenlichtfest Screenshot-Wettbewerb
- Der 18. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Las Vegas
- Wünsche werden wahr- Wettbewerb
- Der 19. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Fan Festival 2014
- Feuermond-Reigen Screenshot-Wettbewerb
- Der 17. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Video-Wettbewerb zum einjährigen Jubiläum
- Der 16. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 15. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 14. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Wundereiersuche Screenshot-Wettbewerb
- Der 13. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Prinzessinnenfest Screenshot-Wettbewerb
- Valentiontag Screenshot Wettbewerb
- Der 12. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Himmelswende Screenshot Wettbewerb
- Sternenlichtfest Screenshot Wettbewerb
- Rekrutierungsvideo-Wettbewerb der Freien Gesellschaften
- Der 11. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 10. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Allerschutzheiligen-Haiku-Wettbewerb
- Der 9. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Makuhari!
- Version 1.0 Forum Archive
- Japanese Forums
- インフォメーション
- サポート
- アップデート
- ゲームシステム
- クラス&ジョブ
- ウェブサイトフィードバック
- 雑談
- 初心者用
- 写真館
- コミュニティイベント
- 開催中
- 終了
- ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア キャッチフレーズコンテスト
- 第8回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LA
- 第7回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第6回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 創作タマゴコンテスト
- 第5回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- マイ ベスト チョコボ
- ダラガブを探せ!
- エオルゼア メモリーズ
- 第4回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エオルゼア de 五・七・五
- 第3回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 残暑見舞いコンテスト
- Hidden Artifacts ~新生コンセプトアートクイズ~
- ガルーダトライアル
- 宿屋deつぶやき!イベント (JP)
- LSリクルートポスターコンテスト (JP)
- English Forums
- Information
- Support
- Updates
- Gameplay
- Classes & Jobs
- Feedback
- Community
- New Player Help
- In-Game Media
- Community Events
- Current Events
- Past Events
- Letter from the Producer LIVE Part VIII
- Letter from the Producer LIVE Part VII
- Letter from the Producer LIVE Part VI
- Eorzean Egg Decoration Contest
- Letter from the Producer LIVE Part V
- Eorzea Haiku Contest (EU)
- “Chocobos Rule the World” Contest!
- Memories of Eorzea Contest
- Letter from the Producer LIVE Part IV
- What if Dalamud Contest (EU)
- Tales from Eorzea (NA)
- Culinary Creation Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part III
- We Dub to Make it Ours (NA)
- These Grand Company Colors Don't Run!
- Hidden Artifacts
- Grant A Wish Contest (EU)
- Garuda—She's Like the Wind
- Culinary Creation Contest (NA)
- Valentione’s Dialogue Contest (EU)
- Valentione’s Day Love Letter Contest (NA)
- Forums français
- Informations
- Assistance sur le jeu
- Développement
- Système de jeu
- Classes & Jobs
- Avis et retours
- Discussion
- Aide aux nouveaux joueurs
- Galerie multimédia & articles
- Evénements organisés par l'équipe communautaire
- Evénements en cours
- Evénements passés
- « La lettre du producteur LIVE » : huitième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : septième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : sixième émission
- Concours : « Décoration d’Œufs Éorzéens »
- « La lettre du producteur LIVE » : cinquième émission
- Concours « Haïkus d’Eorzéa »
- Concours « Les Chocobos à la Conquête du Monde » !
- Concours « Souvenirs d’Eorzéa »
- « La lettre du producteur LIVE » : quatrième émission
- Concours : « Et si Dalamud était... »
- Concours de création culinaire
- « La lettre du producteur LIVE » : troisième émission
- Soutenons les grandes compagnies !
- Questions pour un Eorzéen
- Concours du jeu des souhaits
- L’épreuve de Garuda
- Concours de dialogue de la Valention
- Deutsches Forum
- Ankündigungen
- Support
- Update
- Spielsystem
- Charakterklassen & Jobs
- Feedback
- Diskussionen
- Für Einsteiger
- Medien
- Community-Veranstaltungen
- Aktuelle Veranstaltungen
- Vergangene Veranstaltungen
- Der 8. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 7. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 6. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Eorzäischer Ei-Dekorations-Wettbewerb
- Der 5. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Eorzea-Haiku-Wettbewerb
- Chocobos, die Herrscher der Welt
- Erinnerungen an Eorzea
- Der 4. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Was, wenn Dalamud … wäre?
- Kulinarische Kreationen
- Der 3. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Farben, die nicht die Segel streichen!
- Verborgene ARTefakte
- Wünsche werden wahr-Wettbewerb
- Garuda – Grausame Herrin der Stürme
- Valentione Dialog-Wettbewerb
- Japanese Forums
«
Previous Thread
|
Next Thread
»





 Reply With Quote
Reply With Quote






