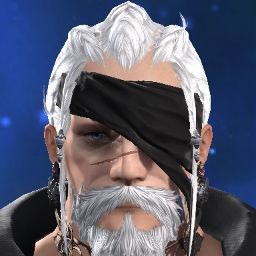極ベースですと対1体のダメージがほとんどなので、対複数での性能を考えるとまた変わってきそうですね。
まだモンクのみしか上げてないのでイメージだと、召喚・詩人あたりはじわっと上がりそう?一か所に敵を集められる状況があれば黒・召喚・機工士もぐいっと上がるのかもですね。
(まとめることができる場面だと近接も範囲が使えるので近接と遠隔の差はそんなに広がりそうにないですが)
- Forum Top
- Japanese Forums
- クラス&ジョブ
- DPS
- DPSジョブバランス総合・検証・要望スレ
Thread: DPSジョブバランス総合・検証・要望スレ
-
07-14-2017 08:50 PM #301(4)
-
07-14-2017 09:00 PM #302範囲は零式で範囲シーンそれ自体が全体の1%もない事に加えて、「範囲が弱いキャラクターがクリアー出来ないようには作らない」ので
まあRaidにおいては無価値な長所ですよね。範囲性能って
2体同時沸きや分裂するタイプ(カドゥケウス、起動1層のアレ)で長時間戦うボスならDoT複数撒きの強さが影響するかな? と思いますが
オメガ零式には今のところなさそう。ショーさん・・・(8)Last edited by emanyon; 07-14-2017 at 09:05 PM.
世界がララフェルで満たされますように
-
07-14-2017 11:27 PM #303こちらの下落幅についてですが
竜騎士はドラゴンサイトがソロで使用できないことを想定し木人HPはその分低く設定されていることが推測されますが
ドラゴンサイトを使用できる実践DPSにおいて他ジョブと同等以上の下落幅を示していることから
実際のギミックからの影響は9.58%という数字よりも大きく受けているであろうことを補足させていただきます
またモンクの桃園結義にも同様の性質があるかと思います
ちなみに竜騎士の木人想定DPS3400に単純に3400*0.1*20/120を加算したものから下落幅を計算すると11%程度になります(6)Last edited by coldfish; 07-14-2017 at 11:35 PM. Reason: 誤字
-
07-15-2017 02:34 AM #304
DPS合算表について更に補足
実戦DPSベースは基本水物で、コンテンツ相性、シナジー差、編成トレンドなどによるブレが入ります
先程掲載したこちらは極ラクシュミ&極スサノオの平均、かつ雑魚除外で出来る限り汎用性を高めています

これを遠隔向けの極ラクシュミに限定&雑魚を含む、という条件にしたパターンも作ってみました

コンテンツ相性によって「赤、詩」が侍に迫ります。やっぱりこの赤「詩人」側だよ
忍者は雑魚をカウントする事によって「騙し」のシナジーがやや過大に出ちゃってますね。序列に変化はない筈です
遠隔向けシナジーで竜がモンクをやや上回りますが、こちらも雑魚フェーズでシナジーが有効ではない分高めに出ていると言えます
機、黒、召は少し伸ばすも相変わらず負け組です、悲しい。機の本体DPSが詩に比べて厳しいですね
と、こんな感じで、ブレ幅はあるものの序列が一変するような変化は起きない事がわかると思います
大きなバランス調整が入らない限りは現行の序列は零式でもそのまま有効だと推測されますが、どうなる事やら(21)Last edited by emanyon; 07-15-2017 at 02:39 AM.
世界がララフェルで満たされますように
-
07-15-2017 03:05 AM #305
一定時間、自身と周囲のパーティメンバーが攻撃を受けた場合に、攻撃者に反撃ダメージを与える。
威力:50
効果時間:20秒
追加効果:対象が受ける物理ダメージを2%上昇させる。
効果時間:4秒
「セミオーダー」状態では命令を受けるまで実行しない。
これは召喚士のイフエギがつかう「光輝の盾」というスキルの詳細なのですが、これを1分ごとに使えます。
スサノオの3連続の「宇気比」は丁度1分ごとに撃ってきます。
つまり、8人全員に光輝の盾が付与されたと仮定して、宇気比1発あたり400、3発合計で1200の威力のダメージを与えていることになります。おまけに対物理シナジーまで。
これってかなり強いですよね。木人を想定したシミュレーションだとこの分だけ下がるんだと思います。なんせ木人は殴ってきませんし。
この分を加味して現在の序列なのだとしたら、召喚に対しては相当気合の入った上方修正が必要だと思います。(5)Last edited by Lily-F; 07-15-2017 at 03:09 AM.
-
07-15-2017 03:09 AM #306
-
07-15-2017 04:11 AM #307
斬ダウンはほぼ常時かかってるのが前提みたいなもんだからノーカウントでdps設定されている
突はレンジドの数で効果が上がっていくから最大効果の二人分に合わせてリューサンの性能を調整した
ついでに詩機もそれに合わせて弱くした
なるほど、PLで言われた侍はシナジーがないとか逆に竜は強いとかってこの前提で見返せば根拠が見えてきますね
まあ妄想の域を出ないんですが案外いろいろ符合しちゃったりするのが面白いですね
さて仮にこの通りだったとして修正をかけるならどうするか
竜の存在によって大きく変わるdpsを縮める方向ならやはりレンジに突ダウンを持たせる方向がベストかな?
でもそれだと全員が属性ダウンを持ってることになり、なくても一緒ってことですよね
やっぱり属性デバフはいらないんじゃ・・・(28)
-
07-15-2017 11:19 AM #308Player
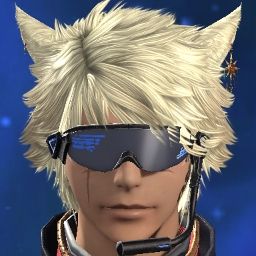
- Join Date
- Aug 2013
- Location
- ウルダハ
- Posts
- 1,028
- Character
- Ashen Kahr
- World
- Fenrir
- Main Class
- Fisher Lv 62
表の提示、たいへん有意義でありがたいと思います。
表の色分け部分の解説も表につけてもらえると嬉しいです。
(どのシナジー加算なのか、ある程度はわかりますが、誤解してるとなんなので。このレスの数では解説してあるレスにたどり着くのもたいへんです)
現在は召喚士やってますが、こうして見ると自ジョブの低さにへこみますね(^^;
(ないに等しい)シナジー込みでもこの差とは・・・
正直、シナジー込みでの各DPSの設計、それも零式8人PTを基準にした設計とかやめてほしいです。
色々なPT構成を楽しんでほしい、PT編成する楽しみを知ってほしいってことかもですが、編成を偏らせたくないならLBゲージで既に実現してましたし、
PT編成を楽しんでほしいってことならRPGではなく、シミュレーションゲームをやればよいのでは、とかとか。
RPGを遊ぶ以上、ほとんどのプレイヤーは「勇者なりたがり」属性を大なり小なり持っているかと思いますし、運営の匙加減1つで脇役を強制されてしまう「編成される側」はたまったもんじゃない。
PS差ならまだ諦められますが、最初から超えられない壁があってはモチベーションも駄々下がりですわ。(21)Last edited by xxSouxx; 07-15-2017 at 11:23 AM.
-
07-15-2017 11:40 AM #309Player

- Join Date
- Aug 2013
- Location
- ウルダハ
- Posts
- 20
- Character
- Love Rio
- World
- Durandal
- Main Class
- Gladiator Lv 70
シナジーによる強化というのは本来「性能をアップして一段階強さを引き上げクリアを助ける」ものだと思うのだけど、FF14は正直、シナジー込みでの各DPSの設計、それも零式8人PTを基準にした設計とかやめてほしいです。
色々なPT構成を楽しんでほしい、PT編成する楽しみを知ってほしいってことかもですが、編成を偏らせたくないならLBゲージで既に実現してましたし、
PT編成を楽しんでほしいってことならRPGではなく、シミュレーションゲームをやればよいのでは、とかとか。
RPGを遊ぶ以上、ほとんどのプレイヤーは「勇者なりたがり」属性を大なり小なり持っているかと思いますし、運営の匙加減1つで脇役を強制されてしまう「編成される側」はたまったもんじゃない。
PS差ならまだ諦められますが、最初から超えられない壁があってはモチベーションも駄々下がりですわ。
最初に「コンテンツの難易度がすべての基準」として考えられていてそれを破壊することは許さない、という感じになっていますよね。
本当なら「普段の性能を基準としてコンテンツを作って、シナジーによりそれがクリアしやすくなる」というのがあるべき姿だと思うけど
前述の通り「運営が決めた難易度は壊させない」「楽にさせない」から、性能アップした状態が基準でコンテンツを作っている。
ちょっと違うんじゃないかなぁと感じますね・・・
性能アップした状態が基準になるなら、それこそシナジーなんて一切いらない、なくしてしまったほうが作る方もプレイする方も楽になるんじゃないかなぁって。(41)Last edited by LoveRio; 07-15-2017 at 11:46 AM.
-
07-15-2017 12:00 PM #310
召喚士ってバハを出しづらい状況もDPSに影響してたりするんですかね…??
極で召喚士2人いるのにあまりバハ見かけない(おそらく離れたところに出したり、ギミック時は避けたり)PTとかあったりしたので…(5)
Quick Navigation
DPS
Top
- Forums
- Japanese Forums
- ニュース
- テクニカルサポート
- 不具合報告
- プロデューサーレター
- ゲームシステム
- クラス&ジョブ
- ウェブサイト/アプリフィードバック
- 雑談
- この装備を武具投影したい!!
- あのジョブのUIレイアウトが知りたい!
- ジェネラルディスカッション
- ワールド(Group JP)
- ワールド(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- 初心者用
- コミュニティイベント
- 開催中
- 終了
- 第8回14時間生放送
- 第68回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第65回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第64回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第60回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第56回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第53回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張!ひろしチャレンジ 応援プレゼント企画
- 第50回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第49回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- ハウジングコーディネートコンテスト
- 第44回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第43回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第42回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第41回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第40回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第39回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第38回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第37回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第35回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- ハウジングデコレーションコンテスト
- 第34回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第33回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LAS VEGAS (2016)
- 髙井浩の○○チャレンジ!応援企画
- 第31回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 紅蓮祭スクリーンショットコンテスト 2016
- 第30回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第28回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- サントラ発売記念!奏天のイシュガルドコンテスト
- 第27回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 星芒祭 4コマスクリーンショットコンテスト
- 第26回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第25回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- パンプキンクッキーコンテスト
- 髪型デザインコンテスト
- 第24回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第23回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第22回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エオルゼア百景 in 装備コーディネートコンテスト
- 第21回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 思い出スクリーンショットコンテスト
- フリーカンパニーPRキャンペーン
- 第20回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- FFXIVプロデューサーレターLIVE特別編
- ヴァレンティオンデーチョコレートコンテスト
- 闘会議2015 予想イベント
- 降神祭スクリーンショットコンテスト
- 星芒祭スクリーンショットコンテスト
- 第19回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第18回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LAS VEGAS
- 新生FFXIV キャプションコンテスト
- 紅蓮祭スクリーンショットコンテスト
- 第17回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 新生FFXIV 1周年記念PVコンテスト
- ミラプリ スクリーンショットコンテスト
- 第16回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第15回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第14回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エッグハントスクリーンショットコンテスト
- 出張プロデューサーレターLIVE
- 第13回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- プリンセスデースクリーンショットコンテスト
- 第12回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 降神祭スクリーンショットコンテスト
- 星芒祭スクリーンショットコンテスト
- ヴァレンティオンデースクリーンショットコンテスト
- フリーカンパニー紹介PVコンテスト
- 第11回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第10回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 守護天節スクリーンショットコンテスト
- 第9回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張プロデューサーレターLIVE in 幕張
- English Forums
- Information
- Technical Support
- Bug Reports
- Letters from the Producer
- Gameplay
- Classes & Jobs
- Feedback
- Community
- General Discussion
- Worlds(Group JP)
- Worlds(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- New Player Help
- Community Events
- Current Events
- Past Events
- Contests and Sweepstakes
- Fan Festival 2023 in London
- 10th Anniversary Mosaic Art Sweepstakes (NA/EU)
- Fan Festival 2023 in Las Vegas
- Ask Your Questions for the PAX East 2023 Q&A
- Crystalline Conflict Community Cup (North America)
- Letter from the Producer LIVE Part LXVIII
- Letter from the Producer LIVE Part LXV
- Letter from the Producer LIVE Part LXIV
- Letter from the Producer LIVE Part LX
- Everything’s on the Line! Screenshot Contest (NA)
- Ask Yusuke Mogi Your Questions for the PAX East 2020 Panel
- “A Star Light Party” Screenshot Contest (EU/PAL)
- Star Companion Screenshot Sweepstakes (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part LVI
- “This is All Saints’ Wake” Screenshot Contest (EU/PAL)
- A Glamourous Guise Screenshot Contest (NA)
- Memoirs of Adventure Creative Writing Contest (NA)
- Ask Yoshi-P and Banri Oda Your Questions for the gamescom 2019 Q&A
- Letter from the Producer LIVE Part LIII
- Cosplay Contest at gamescom 2019 (EU)
- Become the Darkness Screenshot Sweepstakes! (NA)
- From Light to Darkness Screenshot Contest (EU/PAL)
- Frights and Delights Comic Contest (EU/PAL)
- Cosplay Contest at Japan Expo 2019 (EU)
- Ogre Pumpkin Carve Off Contest: The REDUX (NA)
- My new Viera and Hrothgar" Twitter Screenshot Contest (NA/EU)
- ”Sea Breeze Celebration” Screenshot Contest (NA)
- An Egg-Squisite Season Screenshot Contest (EU/PAL)
- The Eorzean Interior Design Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XLIX
- Letter from the Producer LIVE Part L
- FLOWERS FOR ALL SCREENSHOT CONTEST
- The Eorzean Interior Design Contest (EU)
- Highlights of the Year Contest (EU)
- Fan Festival 2018 in Las Vegas (NA)
- Starlight Scenarios Comic Contest (NA)
- Fan Festival 2019 in Paris (EU)
- The "As Good As Gold" Screenshot Contest (NA)
- Glamour Extravaganza Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE: E3 2018 Edition
- Letter from the Producer LIVE Part XLIV
- Letter from the Producer LIVE Part XLIII
- The "Be My Valentione!" Creative Writing Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XLII
- Letter from the Producer LIVE Part XLI
- Holiday Greetings Contest (EU)
- Starlight Starbright Screenshot Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XL
- Ogre Pumpkin Carve Off Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIX
- Letter from the Producer LIVE Part XXXVIII
- PAX West 2017 (NA)
- Sightseeing Screenshot Contest! (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXVII
- And… Action! (NA)
- The Heavensdub Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXV
- House Party Screenshot Contest (EU)
- Bright-Eyed Superstars Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE in Frankfurt (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIV
- Starlight Celebration Haiku Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXIII
- The “Eorzean Home Makeover (Extreme)” Contest (NA)
- Fan Festival 2017 (EU)
- Spooky Story Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE in Las Vegas (2016)
- The Rising Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXXI
- "Do You Even /Pose?" Showdown! (NA)
- Fan Festival 2016 (NA)
- Dream Holiday Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE: E3 2016 Edition
- Heavensward Primal Haiku Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XXX
- Letter from the Producer LIVE Part XXIX
- Letter from the Producer LIVE Part XXVIII
- Heavensward Music Contest (NA)
- Heavensward Music Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXVII
- Starlight Celebration Comic Strip Contest (NA)
- Starlight Celebration Comic Strip Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXVI
- Airship Components: Research and Development (NA)
- All Saints’ Wake Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XXV
- Retainer Ad-Venture Contest (EU)
- Cartographers and Seekers Contest (NA)
- Hairstyle Design Contest
- Letter from the Producer LIVE Part XXIV
- Letter from the Producer LIVE Part XXIII
- Letter from the Producer LIVE Part XXII
- Letter from the Producer LIVE Part XXI
- Memories of Eorzea Screenshot Contest (NA)
- Memories of Eorzea Screenshot Contest (EU)
- Heavensward Free Company Recruitment Contest (NA)
- Heavensward Free Company Recruitment Contest (EU)
- A Realm Redubbed Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part XX
- Letter from the Producer LIVE – Special Edition
- The Great Eorzean Cook-Off Contest (EU)
- Be My Valentione Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (EU)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (NA)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XIX
- Letter from the Producer LIVE Part XVIII
- Letter from the Producer LIVE in Las Vegas
- Grant a Wish Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XVII
- Moonfire Faire Screenshot Contest (NA)
- Moonfire Faire Screenshot Contest (EU)
- Fan Festival 2014 (NA)
- Fan Festival 2014 (EU)
- FFXIV: ARR One Year Anniversary Video Contest (NA)
- FFXIV: ARR One Year Anniversary Video Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XVI
- Eorzea IRL Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE: E3 Edition
- Letter from the Producer LIVE Part XV
- Letter from the Producer LIVE Part XIV
- Hatching-tide Screenshot Contest (NA)
- Hatching-tide Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XIII
- Little Ladies' Day Screenshot Contest (NA)
- Little Ladies' Day Screenshot Contest (EU)
- Valentione's Day Screenshot Contest (NA)
- Valentione's Day Screenshot Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XII
- Heavensturn Screenshot Contest (NA)
- Heavensturn Screenshot Contest (EU)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (NA)
- Starlight Celebration Screenshot Contest (EU)
- FFXIV: ARR Free Company Recruitment Contest (NA)
- FFXIV: ARR Free Company Recruitment Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part XI
- XIII Days – Your Fate is Sealed Contest (NA)
- Letter from the Producer LIVE Part X
- Doppelganger Screenshot Contest (NA)
- All Saints’ Wake Haiku Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part IX
- Ask Your Questions for the Mini Letter from the Producer LIVE at TGS!
- Sightseeing Screenshot Sweepstakes (NA/EU)
- Forums français
- Informations
- Assistance technique
- Rapports de problèmes
- La lettre du producteur
- Système de jeu
- Classes & Jobs
- Avis et retours sur les sites et l’appli
- Discussion
- Discussion générale
- Mondes (Japon)
- Mondes (Amérique du N./Europe/Océanie)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- Aide aux nouveaux joueurs
- Événements communautaires
- Evénements en cours
- Evénements passés
- Concours et tirages au sort
- Fan Festival 2023 de Londres
- Concours pour la mosaïque du 10e anniversaire
- « La lettre du producteur LIVE » : 68e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 65e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 64e émission
- Concours de captures d’écran d'exploration - Édition 2020
- « La lettre du producteur LIVE » : 60e émission
- Concours de captures d’écran - Une petite fête des étoiles entre amis
- « La lettre du producteur LIVE » : 56e émission
- Concours de captures d’écran – C’est ça la Veillée des Saints
- Mes questions à Yoshi-P et Banri Oda pour le Q&R de gamescom 2019 !
- « La lettre du producteur LIVE » : 53e émission
- Concours de cosplay à la gamescom 2019
- Concours de captures d’écran : De la Lumière aux Ténèbres
- Concours Pistolame à Japan Expo 2019 !
- Concours de Cosplay à Japan Expo 2019
- « Ma Viéra & mon Hrothgar » - Concours Twitter de capture d'écran
- Fabulœuf concours de captures d’écran
- « La lettre du producteur LIVE » : 50e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 49e émission
- Concours des meilleurs moments de l'année 2018
- Concours de BD’pouvante
- Concours de décoration d’intérieur
- Fan Festival 2019 à Paris
- Concours “Les dieux de la mode”
- « La lettre du producteur LIVE » : 44e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 43e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 42e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 41e émission
- Concours de cartes de vœux
- « La lettre du producteur LIVE » : 40e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 39e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 38e émission
- Concours de captures d’écran d’exploration
- « La lettre du producteur LIVE » : 37e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 35e émission
- Concours de captures d’écran spécial « House Party »
- Lettre du producteur LIVE à Francfort
- « La lettre du producteur LIVE » : 34e émission
- Concours de haïkus pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : 33e émission
- Concours d’histoires effrayantes
- Posez vos questions pour la lettre Live à Las Vegas (2016)
- Concours de captures d’écran pour la fête de la Commémoration
- « La lettre du producteur LIVE » : 31e émission
- Concours office de tourisme d’Éorzéa
- « La lettre du producteur LIVE » : 30e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 29e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 28e émission
- Concours de musique d’Heavensward
- « La lettre du producteur LIVE » : 27e émission
- Concours de comic strip pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : 26e émission
- Concours de captures d’écran pour la Veillée des saints
- « La lettre du producteur LIVE » : 25e émission
- Concours « Les aventures de mon servant »
- Concours de création de coupe de cheveux
- « La lettre du producteur LIVE » : 24e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 22e émission
- « La lettre du producteur LIVE » : 23e émission
- Concours de captures d’écran – Souvenirs d’Éorzéa
- Les compagnies libres recrutent pour Heavensward
- « La lettre du producteur LIVE » : 20e émission
- La lettre du producteur LIVE : émission spéciale
- Le grand concours culinaire d’Éorzéa
- Concours de captures d’écran pour la fête de la transition
- Concours de captures d’écran pour la fête des étoiles
- « La lettre du producteur LIVE » : dix-huitième émission
- Posez vos questions pour la lettre Live à Las Vegas
- Concours « Le jeu des souhaits »
- « La lettre du producteur LIVE » : 19e émission
- Fan Festival 2014
- Concours de captures d’écran pour les feux de la mort
- « La lettre du producteur LIVE » : dix-septième émission
- Concours vidéo pour le premier anniversaire
- « La lettre du producteur LIVE » : seizième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : quinzième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : quatorzième émission
- Concours de captures d’écran pour la chasse aux Prœufs
- « La lettre du producteur LIVE » : treizième émission
- Concours de captures d’écran pour la fête des demoiselles
- « La lettre du producteur LIVE » : douzième émission
- Concours de captures d’écran pour la fête de la transition
- Concours de captures d’écran pour la fête des étoiles
- Concours de captures d’écran pour la Valention
- Les compagnies libres recrutent
- « La lettre du producteur LIVE » : onzième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : dixième émission
- Concours Haiku d'Éorzéa - la Veillée des saints
- « La lettre du producteur LIVE » : neuvième émission
- Posez vos questions pour la lettre Live à Makuhari
- Deutsches Forum
- Ankündigungen
- Technischer Support
- Fehler melden
- Briefe des Produzenten
- Spielsystem
- Charakterklassen & Jobs
- Feedback
- Diskussionen
- Allgemeine Diskussionen
- Welten(Group JP)
- Welten(Group NA/EU/OC)
- Sargatanas(LEGACY)
- Balmung(LEGACY)
- Hyperion(LEGACY)
- Excalibur(LEGACY)
- Ragnarok(LEGACY/EU)
- Adamantoise
- Behemoth
- Cactuar
- Cerberus(EU)
- Coeurl
- Goblin
- Malboro
- Moogle(EU)
- Ultros
- Diabolos
- Gilgamesh
- Leviathan
- Midgardsormr
- Odin(EU)
- Shiva(EU)
- Exodus
- Faerie
- Lamia
- Phoenix(EU)
- Siren
- Famfrit
- Lich(EU)
- Mateus
- Brynhildr
- Zalera
- Jenova
- Zodiark
- Omega(EU)
- Louisoix(EU)
- Spriggan(EU)
- Twintania(EU)
- Phantom(EU)
- Sagittarius(EU)
- Alpha(EU)
- Raiden(EU)
- Bismarck(OC)
- Ravana(OC)
- Sephirot(OC)
- Sophia(OC)
- Zurvan(OC)
- Halicarnassus
- Maduin
- Marilith
- Seraph
- Für Einsteiger
- Community-Veranstaltungen
- Aktuelle Veranstaltungen
- Vergangene Veranstaltungen
- Wettbewerbe und Gewinnspiele
- Mosaik-Gewinnspiel zum 10. Jubiläum
- Fan Festival 2023 in London
- Der 68 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 65 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 64 Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Reisetagebuch-Screenshot-Gewinnspiel
- Der 60. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sternenlichtertrupp-Screenshot-Wettbewerb
- Der 56. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Allerschutzheiligen Schauer-Spektakel-Screenshot-Wettbewerbs
- Eure Fragen an Naoki Yoshida und Banri Oda für die Q&A-Session auf der gamescom 2019
- Der 53. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Cosplay-Wettbewerb auf der gamescom 2019
- Vom Licht in die Dunkelheit Screenshot-Wettbewerb
- Cosplay-Wettbewerb auf der Japan Expo 2019
- „Viera & Hrothgar Makeover“ Twitter-Screenshot-Wettbewerb
- Wundereiersuche Screenshot-Wettbewerb
- Der 50. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 49. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Highlights des Jahres Wettbewerb
- Spuk und Schabernack Comic-Wettbewerb
- Inneneinrichtungs-Wettbewerb
- Fan Festival 2019 in Paris
- Extravaganza-Wettbewerb
- Der 44. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 43. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 42. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 41. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Wintergrüße-Wettbewerb
- Der 40. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 39. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 38. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sightseeing-Screenshot-Wettbewerb
- Der 37. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 35. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- House Party! Screenshot-Wettbewerb
- Brief des Produzenten LIVE in Frankfurt
- Der 34. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Sternenlichtfest Haiku-Wettbewerb
- Der 33. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Gruselgeschichten-Wettbewerb
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Las Vegas (2016)
- Fest der Wiedergeburt Screenshot-Wettbewerb
- Der 31. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Traumurlaub-Wettbewerb
- Der 30. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 29. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE”
- Der 28. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Heavensward Musik-Wettbewerb
- Der 27. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Sternenlichtfest Comicstrip-Wettbwerb
- Der 26. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Allerschutzheiligen-Fest Screenshot-Wettbewerb
- Der 25. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Die Abenteuer des Tapferen Gehilfen–Wettbewerb
- Frisuren-Design-Wettbewerb
- Der 24. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 22. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 23. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Erinnerungen an Eorzea Screenshot-Wettbewerb
- Heavensward-Rekrutierungswettbewerb der freien Gesellschaften
- Der 20. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Brief des Produzenten – LIVE-Sondersendung!
- Großer, eorzäischer Kochwettbewerb
- Himmelswende Screenshot Wettbewerb
- Sternenlichtfest Screenshot-Wettbewerb
- Der 18. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Las Vegas
- Wünsche werden wahr- Wettbewerb
- Der 19. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Fan Festival 2014
- Feuermond-Reigen Screenshot-Wettbewerb
- Der 17. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Video-Wettbewerb zum einjährigen Jubiläum
- Der 16. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 15. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 14. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Wundereiersuche Screenshot-Wettbewerb
- Der 13. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Prinzessinnenfest Screenshot-Wettbewerb
- Valentiontag Screenshot Wettbewerb
- Der 12. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Himmelswende Screenshot Wettbewerb
- Sternenlichtfest Screenshot Wettbewerb
- Rekrutierungsvideo-Wettbewerb der Freien Gesellschaften
- Der 11. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 10. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Allerschutzheiligen-Haiku-Wettbewerb
- Der 9. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Stellt eure Fragen für den Brief des Produzenten – Live in Makuhari!
- Version 1.0 Forum Archive
- Japanese Forums
- インフォメーション
- サポート
- アップデート
- ゲームシステム
- クラス&ジョブ
- ウェブサイトフィードバック
- 雑談
- 初心者用
- 写真館
- コミュニティイベント
- 開催中
- 終了
- ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア キャッチフレーズコンテスト
- 第8回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 出張FFXIVプロデューサーレターLIVE in LA
- 第7回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 第6回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 創作タマゴコンテスト
- 第5回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- マイ ベスト チョコボ
- ダラガブを探せ!
- エオルゼア メモリーズ
- 第4回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- エオルゼア de 五・七・五
- 第3回FFXIVプロデューサーレターLIVE
- 残暑見舞いコンテスト
- Hidden Artifacts ~新生コンセプトアートクイズ~
- ガルーダトライアル
- 宿屋deつぶやき!イベント (JP)
- LSリクルートポスターコンテスト (JP)
- English Forums
- Information
- Support
- Updates
- Gameplay
- Classes & Jobs
- Feedback
- Community
- New Player Help
- In-Game Media
- Community Events
- Current Events
- Past Events
- Letter from the Producer LIVE Part VIII
- Letter from the Producer LIVE Part VII
- Letter from the Producer LIVE Part VI
- Eorzean Egg Decoration Contest
- Letter from the Producer LIVE Part V
- Eorzea Haiku Contest (EU)
- “Chocobos Rule the World” Contest!
- Memories of Eorzea Contest
- Letter from the Producer LIVE Part IV
- What if Dalamud Contest (EU)
- Tales from Eorzea (NA)
- Culinary Creation Contest (EU)
- Letter from the Producer LIVE Part III
- We Dub to Make it Ours (NA)
- These Grand Company Colors Don't Run!
- Hidden Artifacts
- Grant A Wish Contest (EU)
- Garuda—She's Like the Wind
- Culinary Creation Contest (NA)
- Valentione’s Dialogue Contest (EU)
- Valentione’s Day Love Letter Contest (NA)
- Forums français
- Informations
- Assistance sur le jeu
- Développement
- Système de jeu
- Classes & Jobs
- Avis et retours
- Discussion
- Aide aux nouveaux joueurs
- Galerie multimédia & articles
- Evénements organisés par l'équipe communautaire
- Evénements en cours
- Evénements passés
- « La lettre du producteur LIVE » : huitième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : septième émission
- « La lettre du producteur LIVE » : sixième émission
- Concours : « Décoration d’Œufs Éorzéens »
- « La lettre du producteur LIVE » : cinquième émission
- Concours « Haïkus d’Eorzéa »
- Concours « Les Chocobos à la Conquête du Monde » !
- Concours « Souvenirs d’Eorzéa »
- « La lettre du producteur LIVE » : quatrième émission
- Concours : « Et si Dalamud était... »
- Concours de création culinaire
- « La lettre du producteur LIVE » : troisième émission
- Soutenons les grandes compagnies !
- Questions pour un Eorzéen
- Concours du jeu des souhaits
- L’épreuve de Garuda
- Concours de dialogue de la Valention
- Deutsches Forum
- Ankündigungen
- Support
- Update
- Spielsystem
- Charakterklassen & Jobs
- Feedback
- Diskussionen
- Für Einsteiger
- Medien
- Community-Veranstaltungen
- Aktuelle Veranstaltungen
- Vergangene Veranstaltungen
- Der 8. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 7. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Der 6. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE
- Eorzäischer Ei-Dekorations-Wettbewerb
- Der 5. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Eorzea-Haiku-Wettbewerb
- Chocobos, die Herrscher der Welt
- Erinnerungen an Eorzea
- Der 4. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Was, wenn Dalamud … wäre?
- Kulinarische Kreationen
- Der 3. Teil des „FINAL FANTASY XIV Produzentenbriefs LIVE“
- Farben, die nicht die Segel streichen!
- Verborgene ARTefakte
- Wünsche werden wahr-Wettbewerb
- Garuda – Grausame Herrin der Stürme
- Valentione Dialog-Wettbewerb
- Japanese Forums
«
Previous Thread
|
Next Thread
»




 Reply With Quote
Reply With Quote